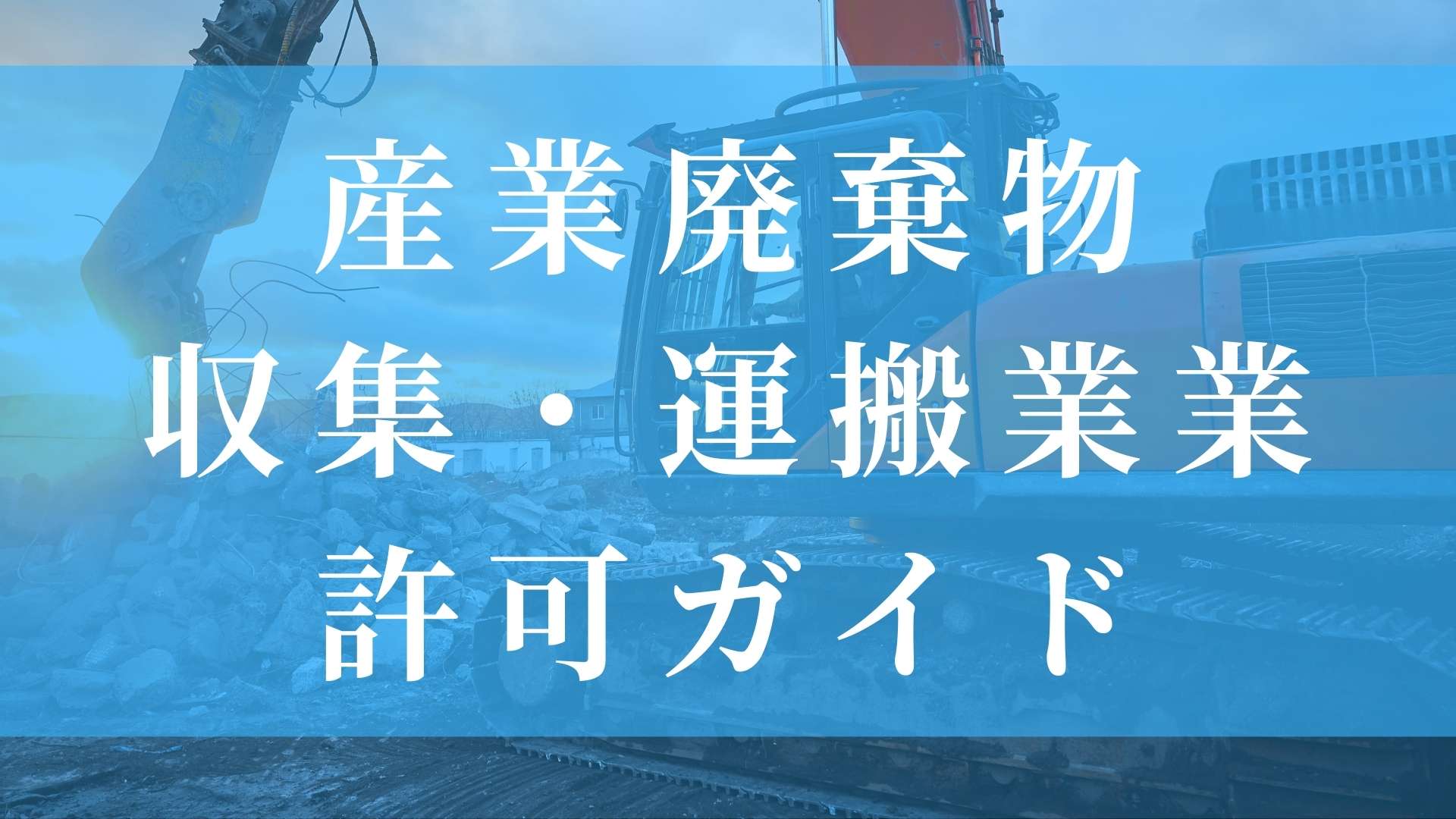こんにちは、行政書士の三澤です!
「建設現場で出た産業廃棄物、どうやって処理するのがベストなんだろう?」 「委託コストがかかるし、いちいち手配するのも面倒だな…」 そんな疑問や悩みを感じていませんか?
この記事では、
・建設業を営む中で産業廃棄物の処理にも自社対応を検討している方
・産業廃棄物収集運搬業の許可を取ってコストを抑えたいと考えている方
・法令を守りつつ、より効率的な体制を整えたい方
といった建設業者様向けに、「建設業と産廃業の兼業で注意すべきこと」について、初めての方でもわかりやすいよう実務の視点で丁寧に解説していきます。
この記事を読むことで、
- 建設業者が産廃業を兼業する際の法的枠組み
- 許可取得・維持に必要な具体的な準備や注意点
- 兼業によるリスクとメリットの見極め方 がわかります。
「うちでも許可を取るべきか?」「今の運用で法令違反になっていないか心配…」という方にとって、判断材料として役立つ内容になっています。
それでは、さっそく見ていきましょう!
第1章 兼業の全体像と背景
建設業者が産業廃棄物収集運搬業の許可を取得して兼業する動きは、年々広がりを見せています。その背景には、現場で発生する廃棄物の「排出事業者責任(元請責任)」に対応するための法的義務、そして業務効率やコスト削減といった実務上のメリットがあります。
なぜ建設業者が産廃業を兼業したいのか?
建設現場では、がれき類、木くず、廃プラスチックなど多様な産業廃棄物が大量に発生します。これらの処理を外部業者に委託する場合、手配の手間や委託費用がかさみ、工期やコスト管理に支障をきたすことがあります。
そこで、収集運搬業の許可を取得して「自社で運搬」することで、
- 廃棄物処理のスケジュールを自社主導で組める
- 委託費用の削減が見込める
- 顧客へのワンストップ対応(工事+処理)を提供できる といった利点が生まれます。
ただし、その分、廃棄物処理法に基づく厳格なルールを守らなければならず、十分な知識と管理体制が求められます。
排出事業者責任(元請責任)とは?
廃棄物処理法では「排出した者が、その廃棄物の適正処理まで責任を負う」という原則が定められており、これを「排出事業者責任」と呼びます。
建設工事においては、現場で発生した廃棄物について、原則として元請業者が排出事業者とされます。そのため、
- 不適正処理や不法投棄が起これば、たとえ下請が行った場合でも元請が責任を問われる
- 処理業者との契約やマニフェスト管理、処分完了までの確認が義務 となります。
つまり「下請に任せたから知らない」は通用せず、元請として主体的に処理責任を果たす必要があります。
「自社運搬」と「業としての運搬」の違い
収集運搬に関して最も誤解されやすいのが、「許可の要否」です。
以下のように整理されます:
- 自社運搬(許可不要):元請業者が自ら排出した廃棄物を、自社の従業員と車両で運ぶ場合。あくまで「自己責任のもとでの処理」に該当します。
- 業としての運搬(許可必要):他人の廃棄物を運ぶ、あるいは対価を得て運ぶ場合。
例外的に「軽微な工事(請負500万円以下)かつ1立米以下の廃棄物を下請が運搬する」場合などもありますが、条件が非常に限定的であり、実務上はほとんどのケースで許可が必要と考えたほうが安全です。
許可が不要な場面でも、「車両表示義務」や「運搬書類の携帯義務」などが課される点に注意が必要です。
第2章 許可の取得に必要な手続きとハードル
建設業者が産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するには、専用の制度に基づく申請手続きが必要です。建設業許可とは異なる制度であるため、混同せずに手続きを進めることが重要です。
許可取得の流れ(講習・書類・申請)
- 講習会の受講と修了証の取得
- 申請者本人や役員等が、(公財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「許可申請講習会(収集・運搬課程)」を受講し、修了証を取得する必要があります。
- 新規講習の修了証は有効期間5年、更新講習は2年です。
- 申請書類の作成と添付資料の準備
- 添付資料には、住民票、登記簿謄本、財務諸表、車検証写し、事業計画書などが含まれます。
- 積替え保管を行う場合は、より詳細な施設図面や管理体制資料が必要です。
- 事前相談(自治体により任意)
- 審査が複雑なケース(例:積替え保管あり、債務超過等)では、許可行政庁との事前相談が必要です。
- 申請書の提出と審査
- 窓口は許可を受けようとする都道府県または政令市。申請受付後、書類審査と場合によっては現地調査が行われます。
- 標準処理期間は60日程度が目安です。
- 許可証の交付
- 審査に合格すると許可証が交付され、業としての収集運搬が可能になります。
建設業許可との違い、別制度である点に注意
建設業許可と産廃業許可は、それぞれ異なる法律に基づく独立した制度です。
| 比較項目 | 建設業許可 | 産業廃棄物収集運搬業許可 |
|---|---|---|
| 根拠法 | 建設業法 | 廃棄物処理法 |
| 許可単位 | 営業所所在地(知事/大臣) | 積込・積卸場所の都道府県ごと |
| 必要要件 | 経営業務管理責任者、専任技術者、資本金要件など | 講習修了者、経理的基礎、運搬設備など |
| 更新手続 | 5年ごと、決算変更届など | 5年ごと、有効な修了証が必要、財務状況の再審査あり |
特に注意が必要なのは、許可の“対象区域”が建設業とは異なる点です。建設業は営業所ベースで許可が管理されますが、産廃業では積込み・積卸しの両地点で都道府県単位の許可が必要となります。
事務所・車両・駐車場・財務状況などの審査基準
事務所
- 申請には、業務を継続的に行う実体のある事務所が必要です。
- 他業種との共有スペースでは不可とされるケースもあり、間取り図や現地写真の提出が求められます。
車両・運搬設備
- 廃棄物の性状に応じた構造(密閉容器や防水処理など)が必要です。
- 車両は自己所有でなくてもリースでも可。ただし使用権原の証明書類が必要。
駐車場
- 車両の台数に応じた駐車スペースが必要です。
- 賃貸の場合は、契約書に「廃棄物処理業目的」の記載が求められる自治体もあります。
財務状況(経理的基礎)
- 債務超過ではないこと、最近の決算で利益が出ていることが求められます。
- 自治体によっては、債務超過でも改善計画や融資証明があれば許可されるケースもあります。
このように、建設業許可とは異なる視点での審査が行われるため、制度上の違いを理解し、必要な準備を事前に整えておくことが重要です。
第3章 建設業との兼業で特に注意すべきポイント
建設業と産廃業を兼業する際は、表面上は許可が別制度であっても、行政手続き上の取り扱いや実務において“つながっている”部分がいくつもあります。特に次の3点は、見落とすと大きなトラブルになりかねない注意点です。
売上の区分(虚偽申請リスク)
建設業許可においては「完成工事高」、つまり建設工事としての売上高が経営事項審査や更新時の基礎資料となります。
産廃収集運搬業による売上は、建設工事の一部とはみなされないため、別枠で「兼業事業売上」として集計しなければなりません。これを誤って建設工事高に合算してしまうと、虚偽の申請と見なされ、場合によっては行政指導や処分の対象となるおそれがあります。
兼業を始めた直後は特に、会計上の区分管理があいまいになりやすいため、注意が必要です。
経営業務管理責任者や専任技術者の実務経験に含められない点
建設業許可では、要件として「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」を配置することが求められますが、
- 産廃収集運搬業としての実務経験
- 廃棄物運搬にかかる売上 は、建設工事の実績とは認められません。
たとえば、産廃事業を担当していた役員が「経営業務管理責任者」としての実績を主張しても、その経験が建設工事に直接関係していないと判断されれば、要件不適合とされる可能性があります。
許可申請時には、実務経験の内容を細かく区分し、建設工事としての業務と、それ以外の業務を明確に整理した書類を準備することが重要です。
許可の維持・更新に必要な管理体制
建設業と違い、産廃収集運搬業の許可は、
- 運搬車両の仕様や保管場所の使用権原
- 財務状況(債務超過や赤字の有無)
- 有効な講習修了証の保持 といった要件を継続的に満たす必要があります。
たとえば、赤字決算が続いたり、更新講習を受けずに修了証が期限切れになると、更新時に不許可となるおそれがあります。
また、産廃業の違反(例:無許可営業、帳簿不備など)が発覚した場合、それが社会的信用の失墜につながり、建設業の経営事項審査や公共工事入札にも悪影響を及ぼす可能性があります。
したがって、両事業をきちんと区分しながらも、連携して法令順守を徹底できる社内体制の構築が求められます。
第4章 「自社運搬」のルールと誤解しやすい点
建設業者が自社工事で発生した産業廃棄物を、自社で運搬したいと考えた場合、廃棄物処理法上の「自社運搬」が可能かどうかを見極める必要があります。しかし実務上は、この自社運搬に関して誤解が多く、知らずに違反してしまうケースも少なくありません。
自社運搬が許される条件
自社運搬とは、「排出事業者自身が、自ら排出した産業廃棄物を自社の車両と従業員で運搬すること」です。これに該当すれば、収集運搬業の許可は不要とされています。
ただし、以下の条件をすべて満たしている必要があります:
- 運搬主体が排出事業者本人(またはその従業員)であること
- 運搬する廃棄物が、その排出事業者が発生させたものであること
- 運搬中の基準(車両表示・書面携帯など)を遵守すること
この条件を外れると「業」とみなされ、無許可営業として罰則対象になります。
下請業者による運搬の落とし穴(例外規定)
「下請業者が軽微な工事で廃棄物を運ぶなら、許可は不要では?」という誤解が多いですが、実際には極めて限定的な例外しか認められていません。
以下の要件すべてを満たす場合のみ、例外的に下請による許可不要の運搬が認められます:
- 工事が500万円以下の小規模工事(ただし新築・増築・解体工事は対象外)
- 運搬する廃棄物の量が1立方メートル以下
- 積替え保管を行わない
- 運搬先が元請業者の施設(または許可を持つ処分業者)で、同一都道府県内または隣接県内
- 請負契約書に運搬の記載があり、その写しを車両に携帯している
このような限定的なケース以外では、原則として下請による運搬は「業」となり、収集運搬業の許可が必要です。
車両表示義務・書面携帯義務・マニフェストの取扱い
自社運搬であっても、次の義務を守らなければ違反になります:
車両表示義務
- 「産業廃棄物収集運搬車」「運搬者名(会社名)」を車体の両側に表示
- 文字の大きさ、見やすさ、位置などにも細かい基準があります
書面携帯義務
- 以下の情報を記載した書類を車内に常備:
- 排出事業者名と住所
- 廃棄物の種類・数量
- 積載日・積載現場・運搬先の情報
- スマートフォン等での電子保存も認められています
マニフェストの適用
- 自社で運び、かつ自社で処分する場合はマニフェスト不要
- 自社で運び、他社で処分する場合はマニフェスト交付が必要(自社が排出事業者として)
つまり「許可がいらない=何もしなくていい」ということではなく、表示義務・携帯義務・マニフェスト義務を含む管理体制が求められます。
このあたりの違いを誤解していると、悪意がなくても違反となり、結果として行政処分や信用失墜につながるおそれがあります。
第5章 違反事例と建設業許可への影響
建設業者が産廃業を兼業するにあたっては、法令や許可内容に違反した場合のリスクも十分に認識しておく必要があります。違反は産廃業だけでなく、建設業許可や事業全体の信頼にも波及しかねないため、注意が必要です。
よくある違反事例(委託基準違反、無許可営業など)
- 無許可営業:許可を得ずに他人の廃棄物を運搬してしまうケース。
- 委託契約書・マニフェスト不備:処理業者との契約書を交わさず運搬したり、マニフェストの交付・保存を怠ったりする事例。
- 積替え保管違反:本来別途許可が必要な積替え保管行為を、許可なく実施してしまう例。
- 虚偽申請:経理的基礎や事務所・車両の使用権限に関して、虚偽の資料を提出してしまうケース。
特に「知らずに違反していた」というパターンが多く、知識不足が原因で処分されることもあります。
行政処分のリスク(事業停止・許可取消)
違反が発覚すると、以下のような行政処分を受けるおそれがあります:
- 業務停止命令:軽微な違反でも一定期間業務を停止されることがあります。
- 許可取消:重大な違反(無許可営業や不法投棄など)や再三の改善命令違反などがあれば、許可自体が取り消されます。
許可の取消しは、産廃業の事業継続が不可能になるだけでなく、他の許可や入札参加資格にも影響します。
建設業許可への波及リスク(欠格事由、入札停止等)
産廃業での違反が、建設業の経営事項審査(経審)や公共工事の入札資格に悪影響を及ぼす可能性があります。
たとえば:
- 許可取消や業務停止が一定期間続くと、建設業許可の更新審査でマイナス評価となる
- 公共工事の入札停止処分を受けるリスク(地方自治体では社会的信用を重視)
- 産廃業の管理体制不備が「善管注意義務違反」等として評価される
兼業を検討する際には、こうした「建設業全体への波及リスク」にまで目を向けることが肝要です。
第6章 兼業のメリットとリスクの天秤
建設業者が産廃収集運搬業の許可を取得して兼業することには、たしかに大きなメリットがありますが、同時に見逃せないリスクも存在します。ここではそのバランスを冷静に見極めるための視点をご紹介します。
コスト削減、柔軟な対応、営業上の強み
- 廃棄物処理コストの削減:委託処理費用や手配コストを抑えられることで、利益率の向上が期待できます。
- 現場対応の柔軟性:自社で運搬できることで、急な廃棄物の発生にも迅速に対応可能。
- 営業力の向上:顧客に「工事+廃棄物処理」を一括で請け負えることが、提案の差別化や信頼獲得につながります。
管理コスト増、法令違反リスク、許可維持の難しさ
- 法令遵守の負担増:車両管理、マニフェスト発行、帳簿作成など、日常的な業務が増加。
- 許可の維持コスト:講習受講、財務状況の安定、設備要件の継続的維持など、コストと労力がかかります。
- 違反時のリスクが高い:許可取消・行政処分にとどまらず、建設業の信用失墜につながる可能性があります。
事業判断のためのチェックポイント
兼業の判断にあたっては、次の視点で慎重に検討することが重要です:
- 現在の廃棄物処理コストと将来的な工事件数
- 対応する廃棄物の種類と運搬設備の必要性
- 自社における管理体制(担当者・帳簿管理・教育体制など)
- 許可取得や維持に必要な初期費用・ランニングコスト
単に「コストが下がりそうだから」という理由だけで判断するのではなく、法令遵守・人的体制・経営的持続性の3点を総合的に評価することが、兼業成功のカギとなります。
まとめ
産廃業兼業は、工事対応力の強化やコスト削減といった大きなメリットがある一方で、法令違反のリスクや管理体制の構築といったハードルもあります。特に建設業者にとっては、事業の信頼性や許可の安定維持といった観点からも、慎重な判断が求められます。
収集運搬業の許可取得には、講習受講・事務所や車両の整備・財務要件・帳簿管理など、多岐にわたる準備と維持管理が必要です。
当事務所では、産業廃棄物処理業に10年間従事してきた行政書士が、建設業と産廃業の両視点から手続きと実務の両面をサポートいたします。
「自社で産廃を運べる体制を整えたい」「違反リスクを回避しつつ、効率化を図りたい」とお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
産業廃棄物に関する手続きで、こんなお悩みはありませんか?
- 初めての許可申請で何から始めていいかわからない…
- 行政の説明が複雑で、自分に当てはまるか不安…
- 元請業者から手続きや登録を求められて困っている…
そんなときは、建設系産業廃棄物業界出身の行政書士が対応する 三澤行政書士事務所にぜひご相談ください。
当事務所は、愛知県を中心に中小企業・個人事業主の建設業者様をサポートしており、 許可申請から更新・変更届、関連する各種制度(例:CCUSや経審など)まで幅広く対応可能です。
▼ お問い合わせはこちらから