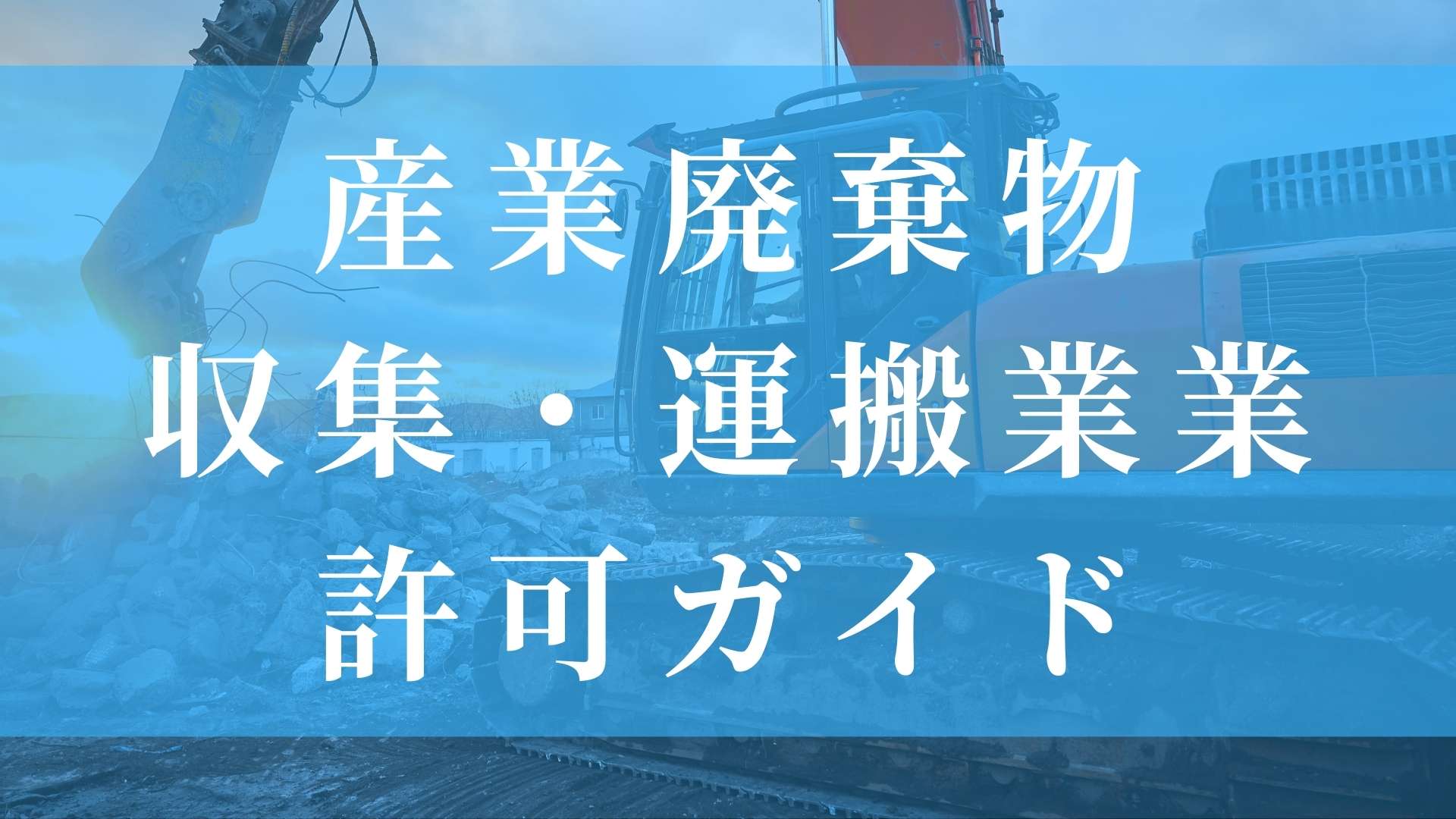こんにちは、行政書士の三澤です!
「産業廃棄物収集運搬業の許可について知りたい」「そろそろ自社でも許可を取るべきかも…」
そんな疑問やお悩みを感じていませんか?
この記事では、
・建設現場で発生する廃材を自社で運びたいと考えている方
・下請業者として元請から産廃運搬を求められる機会が増えてきた方
・許可を取るべきか悩んでいるけど、具体的にどんな準備が必要かイメージが湧かない方
といった建設業者の方向けに、産業廃棄物収集運搬業許可を取得するための「5つの基本要件」について、初めての方でもわかりやすいよう実務の視点で丁寧に解説していきます。
この記事を読むことで、
・許可取得のために満たさなければならない5つの条件がわかる
・自社の状況でどの要件に注意すべきかを判断できる
・書類準備や段取りのポイントを理解できる
ようになります。
「うちでも取得できるの?」「まず何をすればいいの?」と迷われている方の道しるべとなるよう、ポイントを絞ってご紹介します。
それでは、さっそく見ていきましょう!
1. 講習会の修了 ― まずは修了証が必要!
産業廃棄物の収集運搬業を始めるために、まず立ちはだかるのが「講習会の修了」です。これは単なる形式ではなく、許可を取るための必須条件です。
なぜ講習が必要なのか?
産業廃棄物を適正に取り扱うには、法律や運搬のルール、安全対策などの知識が欠かせません。講習を修了していない人が現場で業務を行えば、知らず知らずのうちに違反をしてしまう可能性も。 そのため、法律で「講習を受けていること」が技術的能力の証として定められているのです。
誰が受ければいいのか?
ここが意外と落とし穴になりがちです。 法人の場合は「代表者」か「業務を行う役員」、あるいは「政令で定める使用人(支店長や営業所長など、契約の権限を持つ人)」が対象となります。 個人事業主の場合は、ご本人か、契約権限を持つ従業員が対象です。
→ 行政書士の視点: 実際、「別の担当者が行った方が都合がいいから…」と現場責任者が講習を受けたところ、申請が却下された事例もあります。講習会の対象者は、法的に決められた範囲の人物のみです。受講前に必ず確認しましょう。
いつ・どこで受けられるのか?
講習会は年中どこでも開催されているわけではありません。 定員制のため、希望者が多い時期にはすぐに満席になります。特に年度末や大型連休前などは混みやすいため、受講希望日から逆算して早めの予約が鉄則です。
講習は、公益財団法人「日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)」が全国で実施しており、Webサイトから申込みが可能です。 新規申請の場合は「収集・運搬課程」の新規講習を受講し、試験に合格すると「修了証」が発行されます。この修了証が許可申請の際に必要となります。
2. 経理的基礎 ―「お金」の安定
産業廃棄物収集運搬業は継続的に運営されるべき事業です。そのため、申請時に「経理的基礎があるかどうか」が厳しくチェックされます。
過去3期の決算書や納税証明書が必要な理由
審査の際にチェックされるのは、単なる黒字・赤字ではありません。安定して利益が出ているか、債務超過ではないか、納税が適正に行われているかといった「財務の健全性全体」が見られます。 法人なら直近3期分の貸借対照表・損益計算書・法人税納税証明書など、個人事業主なら確定申告書や所得税の納税証明書などを提出します。
納税証明書は「納税をしている=信頼できる事業者か」の判断材料にもなります。納税額がゼロの場合でも、正しく申告していれば問題視されることはありません。
財務状況が悪くても「改善計画書」で巻き返せる可能性あり
「赤字が続いているから、どうせ無理だろう」とあきらめるのは早計です。実は、財務状況が厳しくても、事業改善計画書や中小企業診断士による経営診断書などを提出することで、将来の見通しが明るいと判断されれば許可が下りることもあります。
このとき求められるのは、数字に裏付けられた現実的な改善プランです。「来年度から黒字化します」ではなく、「このコストを削減し、この契約で売上が増加する予定」というように、具体性がカギになります。
→ 行政書士の視点: 建設業は元請・下請の契約タイミングや現場稼働の季節変動により、決算がぶれる業種です。見せ方次第で「不安定」と判断されることもあれば、「堅実」と受け取られることもあります。
地域によっても判断基準は微妙に異なるため、「この状況で通るか?」と迷う場合は、まず一度ご相談ください。
3. 事業計画 ― 絵に描いた餅ではダメ
事業計画とは、「どんな廃棄物を、どこから、どこへ、どうやって運ぶのか」を具体的に示す書類です。 これは単なる形式ではなく、「その事業が本当に現実的かどうか」を判断するための重要な資料になります。
どんな廃棄物を、どこから、どこへ、どうやって運ぶのかを明確に
例えば、運搬する予定の産業廃棄物の種類(がれき類・廃木材・混合廃棄物など)や性状(液体・粉状・固形)、積込方法や使用車両、運搬先の処分場の情報など、事細かに記載する必要があります。
「ざっくり書いておけばいいだろう」と考えてしまうと、内容の不備を指摘されて再提出になることも。特に建設業者の場合、「どこで発生した廃棄物を」「どういうルートで」「どこに搬入するのか」を、業務の流れに沿って具体的に記載することが求められます。
計画と実態(車両や施設)がズレていないかのチェックが審査で重要
例えば「液体状の廃棄物を運ぶ」と書いてあるのに、準備している車両がダンプだった場合、申請は通りません。
事業計画の内容と、後述する運搬施設の内容(車両・容器・駐車場等)が一貫していることが極めて重要です。 審査する側は、「この会社は本当に計画どおりに運搬できる体制が整っているのか?」を見ています。
→ 行政書士の視点: この「事業計画」は、書き方次第で評価が大きく変わる項目です。 たとえ内容が十分でも、記載方法が曖昧だと「不明瞭」と判断されてしまうことも。逆に、明快かつ整合性のある記述をすれば、審査官にも伝わりやすくなり、結果的にスムーズに許可が下りる可能性が高くなります。
許可申請の中でも、最も「経験とノウハウ」が求められるパートと言えるでしょう。
4. 運搬施設 ― 道具がそろっていなければアウト
どれだけ立派な事業計画を立てても、実際に使う車両や容器が整っていなければ、許可は下りません。 運搬施設の準備は、申請において最も物理的な裏付けが必要な項目です。
廃棄物の種類に適した車両や容器、駐車場の確保
運搬する産業廃棄物の性状(液体・粉体・固体など)に応じて、適した車両や容器を準備しておく必要があります。 たとえば、がれき類を運ぶならダンプ、液体廃棄物なら密閉容器など。
さらに、車両を保管する駐車場も申請時に明示する必要があります。申請車両のすべてが駐車できる広さがあるか、所在地はどこかといった情報も審査対象です。
使用権限の証明(車検証・賃貸契約書など)も重要
単に「車両を使っています」「駐車場があります」と言うだけでは足りません。
審査では、
- 車両の車検証(使用者名が申請者になっているか)
- リース車両の場合は、賃貸契約書などで使用権原を証明
- 駐車場の賃貸借契約書、自己所有の場合は登記事項証明書 などの客観的な証拠を添付する必要があります。
→ 行政書士の視点: 所有していなくても構いませんが、「安定して使える状態であること」を証明しなければなりません。 「友人に借りている」「口約束で置かせてもらっている」では不十分です。書類で裏付けられていない場合、審査ではねられてしまうケースが多くあります。
「使える車両や場所がある」ことと「使えると証明できる」ことはまったく別物です。 申請準備ではこの“証明書類”をしっかり整えることが非常に重要です。
5. 欠格要件 ― “信頼できる事業者”かどうかのチェック
申請者が信頼に足る人物・組織であるかどうかを判断するために設けられているのが「欠格要件」です。 これは、どんなに他の要件を満たしていても、この項目に引っかかってしまえば許可は絶対に下りません。
反社会的勢力との関係や刑事罰歴など、法令順守の姿勢を見られる
例えば、暴力団との関係がある、過去に廃棄物処理法違反で罰金刑を受けた、禁錮刑の執行から5年以内といったケースはすべて欠格要件に該当します。 また、成年被後見人や破産して復権していない場合も対象となります。
「過去の出来事だから」と軽く考えられがちですが、行政は「公共性の高い事業者」としての姿勢を非常に重視しています。
本人だけでなく役員や出資者も対象
チェックされるのは申請者本人だけではありません。 法人の場合、すべての役員(取締役・監査役など)や5%以上の株主・出資者、さらには支店長・営業所長といった「使用人」も対象になります。
このため、「自分には関係ないだろう」と思っていた役員や株主の経歴によって申請が通らないという事態も起こり得ます。
→ 行政書士の視点: この欠格要件に該当していたがために、他の準備がすべて水の泡になってしまった…というケースも実際にあります。 必ず、申請前に関係者全員の経歴や過去の経緯をチェックしておく必要があります。
書類上は、「誓約書」や「登記されていないことの証明書」などを添付することで、非該当であることを証明します。 些細なことでも「これは引っかかるかも?」と思ったら、まずは専門家に相談するのが確実です。
まとめ:許可取得は”準備8割”の世界
ここまで見てきた5つの要件は、いずれも重要なものばかり。 講習会の受講から始まり、経理の健全性、緻密な事業計画、運搬施設の整備、そして欠格要件の確認と、やるべきことは多岐にわたります。
とはいえ、しっかりとポイントを押さえて準備すれば、どの会社でも取得できる可能性は十分にあります。
ただし、初めての方にとっては、「どこから手をつけていいかわからない」「何度も書類を差し戻されてしまう」といった、思わぬ落とし穴も多いのが現実です。
講習の対象者を間違えた、計画と車両の整合性が取れていない、財務の見せ方で損をしている…こうした小さなミスが、全体の許可取得を難しくしてしまいます。
だからこそ、「本業に集中したい」「確実に許可を取りたい」という方には、行政書士に依頼するという選択肢が、結果的に最も合理的です。
産業廃棄物に関する手続きで、こんなお悩みはありませんか?
- 初めての許可申請で何から始めていいかわからない…
- 行政の説明が複雑で、自分に当てはまるか不安…
- 元請業者から手続きや登録を求められて困っている…
そんなときは、建設系産業廃棄物業界出身の行政書士が対応する 三澤行政書士事務所にぜひご相談ください。
当事務所は、愛知県を中心に中小企業・個人事業主の建設業者様をサポートしており、 許可申請から更新・変更届、関連する各種制度(例:CCUSや経審など)まで幅広く対応可能です。
まずはお気軽にご連絡ください。
▼ お問い合わせはこちらから