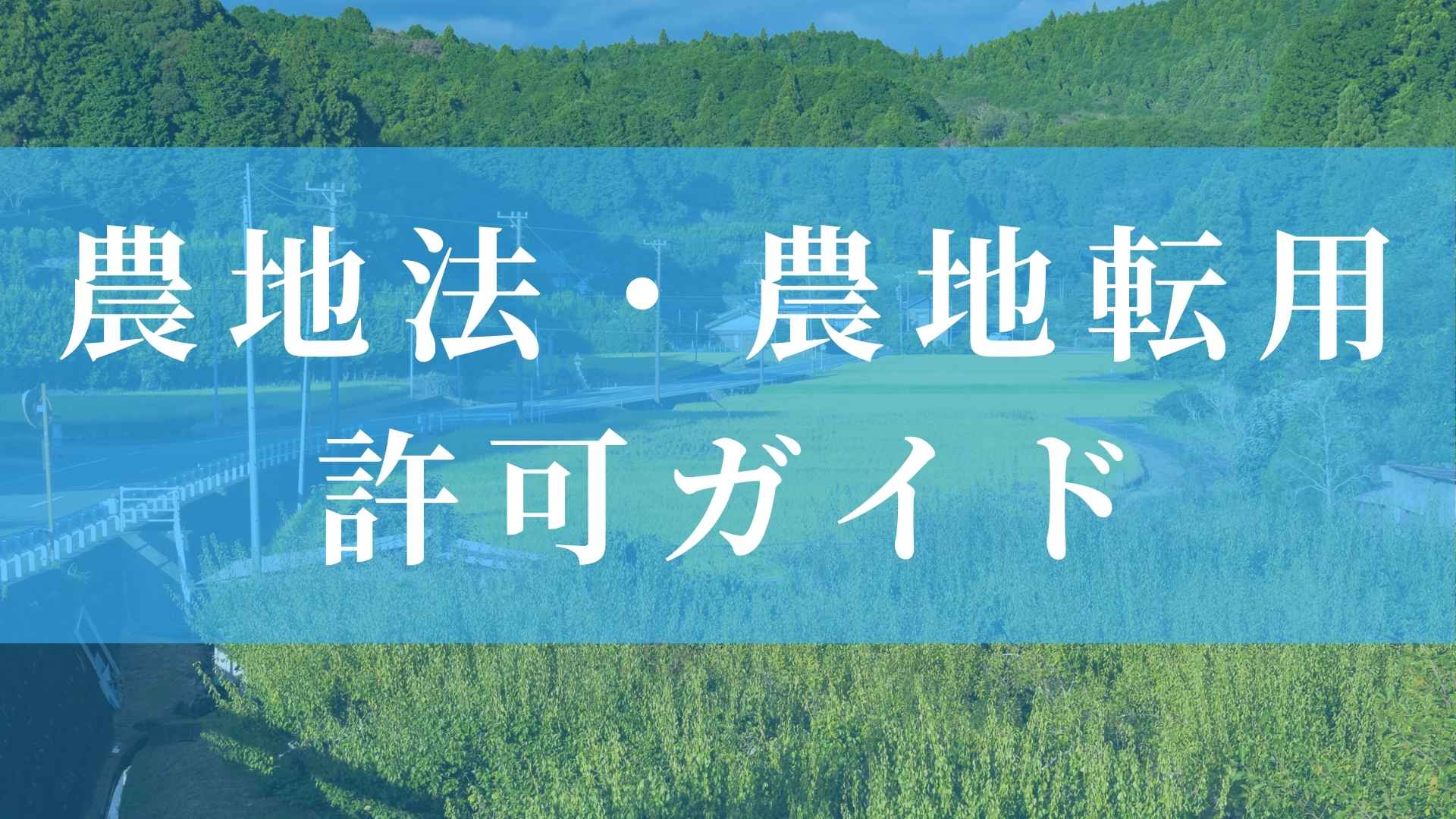こんにちは、行政書士の三澤です!
農地を住宅や店舗、駐車場などに活用したいと考えるとき、最初に立ちはだかるのが「この農地、そもそも転用できるのか?」という問題です。実は、日本の農地は複数の法律によって厳格に守られており、その位置づけや規制内容によって、転用の可否や手続きの難易度が大きく変わります。
特に重要なのが、「農用地区域(通称:青地)」と「農振白地」という区分です。これを見誤ると、せっかく準備した計画が白紙に戻ることにもなりかねません。
この記事では、あなたの農地がどちらの区分にあるのかを見極める方法から、それぞれの区域がもつ意味や特徴、そして農地活用のために必要な手続きの全体像まで、わかりやすく・丁寧に解説します。
1.1. 農地に関わる3つの法律とその関係性
日本の農地制度は、一つの法律だけでは完結しません。農地の位置や性質によって、「どの法律が優先されるか」「どんな手続きが必要か」が決まってくるため、まずはその法制度の“重なり方”を理解することが重要です。
主に関係する3つの法律
| 法律名 | 役割 |
|---|---|
| 都市計画法 | 全国を「市街化区域」と「市街化調整区域」に分けて、土地利用の大枠を決定します。建築や開発がそもそも可能かどうかを左右します。 |
| 農業振興地域の整備に関する法律(通称:農振法) | 「農業振興地域」として農業を保護・振興すべき地域を定め、その中でも特に優良な農地を「農用地区域(青地)」として指定します。 |
| 農地法 | 各農地(1筆ごと)に対して、売買・貸借や転用の可否を個別に判断するための法律です。 |
この3法は、それぞれの役割に応じて「階層構造」のように作用しています。
- 都市計画法によって、その土地が「市街化区域」か「市街化調整区域」かが決まる
- 次に、農振法によって「農業振興地域」「農用地区域(青地)」などの区域が定められる
- 最後に、農地法によって「その農地を売れるか・転用できるか」が判断される
つまり、農地の活用を考える際には、まず上位の都市計画法と農振法の規制をクリアしてから、農地法による個別の許可を得るという流れになります。
この順序を間違えてしまうと、「農地法の許可が下りたのに転用できない」「申請しても受け付けてもらえない」といったトラブルにつながるため、必ず最初に確認しておきましょう。
1.2. 活用できる?できない?最初に立ちはだかる「青地」と「白地」の壁
「この農地、転用して住宅や店舗にできるだろうか?」
そんな疑問を持ったとき、まず確認すべき最初のポイントが、農業振興地域制度における区分、つまり「農用地区域(青地)」か「農用地区域外(白地)」かという分類です。
これは、農業振興地域の整備に関する法律(通称:農振法)に基づき定められるもので、農地の将来的な活用可能性に大きな影響を与える“出発点”になります。
「青地」か「白地」かで何が違うの?
農地がどちらの区域に属しているかによって、以下のような違いが生まれます。
- 農地転用の可否
- 必要な手続きの種類と難易度
- 許可にかかる期間
- 発生する費用や制限内容
たとえば「青地」に指定された農地は、原則として転用できません。もし転用を目指すなら、「農振除外」と呼ばれる高難易度の手続きを経る必要があります。一方で「白地」であれば、農振除外は不要となり、農地法に基づいた転用手続きへと直接進むことができます。
このように、青地・白地の区分は、農地活用の“第一関門”ともいえる重要な分岐点なのです。
本記事では、この「青地」と「白地」の違いを明確にし、読者ご自身の農地がどちらに当てはまるかを調べる方法まで、実務に即した内容でわかりやすく解説していきます。
2. 「農用地区域(青地)」とは?―転用を原則認めない“農地の中の農地”
農地の中でも特に保全の必要性が高いとされる区域が、「農用地区域(通称:青地)」です。この区域に指定された農地は、原則として農業以外の用途への転用が認められません。つまり、住宅や駐車場、資材置き場などへの転用を検討する場合、最初に超えなければならない高いハードルとも言えるのがこの「青地」という存在です。
本章では、農用地区域の法的な定義や指定の目的について、条文に基づいてわかりやすく解説していきます。
2.1. 「農用地区域」の定義と指定の目的
■ 法的な位置づけ(農振法第8条第2項第1号)
農用地区域とは、「農業振興地域の整備に関する法律(農振法)」第8条第2項第1号に基づき、市町村が策定する「農業振興地域整備計画」の中で、農用地等として継続的に利用すべき土地の区域として明示されたエリアを指します。
つまり、地域全体の農業振興を図るうえで「ここは将来にわたって農地として守るべき」と判断された土地が、農用地区域として指定されるのです。
■ 指定の目的 ― 長期的な農地保全と農業振興
農用地区域の主な目的は、優良な農地を中長期的に確保・保全し、農業の持続的な発展を支えることにあります。
特に以下のような土地が指定の対象となります:
- 集団的に存在し、規模が10ヘクタール以上ある農用地
- 区画整理や用排水路整備など、土地改良事業が施行されたエリア
- 農業用施設(畜舎・倉庫など)や、ため池・農道等の関連用地
- 優良農地に隣接する2ヘクタール以上の農業用施設用地
このように、農業生産性の高い土地を農用地区域として保全することで、将来的な食料供給の安定にもつながる仕組みとなっています。
■ なぜ「青地」と呼ばれるのか?
「農用地区域」は、各市町村が作成する「農業振興地域整備計画図」で、青色で塗られて表示されることが一般的です。そこから、実務上では「青地(あおち)」という通称が広まり、定着しています。
この青地に指定されるかどうかで、農地活用の選択肢が大きく変わってきます。次章では、青地農地のメリットとデメリットを具体的に見ていきましょう。
2.2. 青地農地の特徴とは?―保護の裏にある制約とチャンス
農用地区域(青地)に指定された農地は、国や自治体にとって「守るべき農地」として位置づけられており、その分、他の農地と比べて明確なメリットとデメリットがあります。
ここでは、青地農地の実務的な特徴を、「支援される点」と「制限される点」の両面から見ていきましょう。
農業継続に手厚いサポートがある
青地に指定されている農地は、農業振興の中心的な役割を果たすべき土地として、国の政策上でも優先的に支援対象とされています。そのため、以下のような優遇措置を受けやすくなります。
■ 補助金・融資制度の活用がしやすい
- 区画整理(ほ場整備)や農業用施設(用排水路・農道等)の整備
- ビニールハウス等の園芸施設導入 など
これらの農業基盤整備事業では、農用地区域(青地)内の農地であることが補助金や低利融資の要件になることが一般的です。
■ 税制上の優遇も充実
- 固定資産税:宅地等と比べて低い「農地評価」で課税され、税額が大幅に抑えられます。
- 相続税・贈与税:農業後継者による取得に対して、一定の要件を満たせば納税猶予制度が適用されます。
- 所得税・法人税:農用地区域内の農地を譲渡した場合、特別控除が認められるケースもあります。
農地を保有しながら農業を継続する上では、経済的な負担が軽減される仕組みが整っています。
農業以外への利用は原則NG
最大の制約は、農業以外の目的での利用が原則として認められていないことです。
■ 農地転用は原則不可
青地農地では、住宅建築、駐車場、資材置場、太陽光発電設備など、非農業目的での使用(=農地転用)は法律上禁止されています(農振法・農地法の規制)。
■ 転用するには「農振除外」が必須
どうしても転用したい場合は、「農業振興地域整備計画」からその農地を外す「農振除外」の手続きを取る必要があります。
この農振除外は、以下のような厳しい要件(農振法第13条第2項)をすべて満たさなければ認められません:
- 必要性・代替性の不存在
計画している用途(例:住宅建築)が、その場所でなければならず、代わりとなる土地(白地・宅地等)がないこと。 - 農業利用への支障がないこと
除外によって周辺農地の集団性や農作業効率が損なわれないこと。 - 担い手への利用集積への支障がないこと
地域の認定農業者などへの農地の集約を妨げないこと。 - 土地改良施設の機能に影響がないこと
用排水路や農道などの農業インフラに悪影響を与えないこと。 - 土地改良事業から8年が経過していること
ほ場整備等の土地改良が完了した区域である場合、その完了から8年以上が経っていること。
※一部自治体では、地域計画との整合性を加えて「6要件」として説明されることもあります。
これらのうち、特に難しいのが「代替性の不存在」の証明です。
「ほかに土地がないから」「この土地が安かったから」といった主観的な理由は認められず、客観的かつ合理的な裏付けが求められます。
■ 時間もかかる、手間もかかる
農振除外の手続きは年に数回しか申請受付がない自治体も多く、申請から決定まで半年〜1年以上かかるのが一般的です。
青地農地は、農業を続ける人にとってはメリットの多い区域ですが、転用や売却といった活用を考える人にとっては、大きな制限と手間が伴う区域でもあります。
そのため、農地をどう活かすかを考える際には、自身の目的と青地であることの特性が合致しているかを、事前に慎重に見極めることが重要です。
3. 「農振白地(農用地区域外の農地)」とは?―青地ではない“もう一つの農地”
農地が「農業振興地域」に含まれている場合でも、すべてが「農用地区域(青地)」に指定されるわけではありません。
その中で、農用地区域に該当しない農地を、実務上「農振白地(のうしんしろち)」と呼びます。
白地農地は、青地とは異なり、一定の条件下で農地転用の道が開かれているため、住宅建築や事業利用を検討している方にとっては重要な選択肢となり得ます。
3.1. 「農振白地」の定義と背景
■ 法律上の正式名称と位置づけ
「農振白地」は、農業振興地域のうち、農用地区域(青地)には指定されていない農地を指す通称です。
法律上の正式な名称は「農業振興地域内農用地区域外農地」となります。
この名称が示すとおり、農業振興地域の“内部”にあるにもかかわらず、「農用地として重点的に保全すべき」と判断されなかった農地が該当します。
■ なぜ白地に指定されるのか?
農業振興地域内であっても、以下のような理由から青地としての指定を見送られることがあります:
- 周囲に宅地が多く、農地の集団性が低い
- 区画整理(ほ場整備)などの土地改良事業が未実施
- 面積が小さい、形状が不整形で農業利用に不向き など
こうした農地は、農業振興地域に属しながらも、青地ほどの優良性・保全の必要性がないと判断され、「白地」として扱われるのです。
■ 「白地」という呼び名の由来
白地という名称は、「農業振興地域整備計画図」において、農用地区域(青地)に色づけされていない、白く塗られたエリアであることに由来します。
図面上で一目で見分けられるよう、青地=青色、白地=無着色(白)という視覚的区分が実務でも使われています。
青地と白地は、法的な定義や制度上の扱いに明確な差があります。次章では、白地農地が持つ具体的な特徴や、転用可能性について詳しく解説していきます。
3.2. 農振白地は転用できる?―開かれた可能性ともう一つの壁
農振白地(農用地区域外の農地)は、青地とは異なり、農地転用への道が比較的開かれている点が大きな特徴です。
ただし「自由に使える土地」というわけではなく、農地法や都市計画法など、依然として複数の法的規制を受ける点には注意が必要です。
■ 「農振除外」が不要なのが最大のメリット
農振白地は、農用地区域(青地)には指定されていないため、農振法に基づく「農振除外」の手続きは不要です。
これは青地との決定的な違いであり、「農地転用を検討できるかどうか」という観点では、白地農地の方が圧倒的に柔軟です。
■ ただし、農地法の手続きは必須
農振除外が不要であっても、農地を宅地や事業用地にするためには、農地法に基づく「農地転用許可」または「届出」が必要です。
誰が転用するかによって、根拠となる条文が変わります:
- 農地法第4条許可
所有者本人が自分の農地を自ら転用する場合(例:自宅を建てる) - 農地法第5条許可
農地を第三者に売却・賃貸し、その新たな権利者が転用する場合
(例:買主が住宅を建てる、借主が駐車場にするなど)
いずれのケースでも、市町村の農業委員会に対する事前相談が不可欠です。
■ 実は“もう一つの壁”がある ― 都市計画法の区域区分
白地であっても、農地転用がスムーズに進むとは限りません。
その土地が都市計画法におけるどの区域に属しているかによって、手続きの難易度が大きく変わります。
◯ 市街化区域内の白地農地
- 転用の際に「許可」は不要
- 農業委員会への「届出」で足りる(農地法第5条・第4条 届出扱い)
- 手続きも簡素で、1〜2週間程度で完了することが多い
市街化が進められるべき区域のため、建築や開発が基本的に認められています。
◯ 市街化調整区域内の白地農地
- 農地法の「許可」が必要
- 都道府県知事等による厳格な審査を受ける
- 農地の立地条件や事業の確実性、周辺農地への影響など、厳しい審査基準をすべてクリアしなければならない
この区域では、市街化が抑制されているため、転用には慎重な判断が求められます。
■ 「白地=転用できる」とは限らない
まとめると、白地農地は確かに青地よりも転用への道が開かれていますが、それでも以下のような条件を見極める必要があります:
- 農地法による手続き(許可or届出)
- 都市計画法上の区域区分(市街化区域or調整区域)
- その他の法令や条例の制限(例:景観条例や土砂災害特別警戒区域等)
「白地だから安心」というわけではなく、“白地+市街化区域”のように複数条件が重なってはじめて、実質的な転用が可能になるという点を理解しておくことが重要です。
4. 【比較表】「青地」と「白地」の違いを一目で整理!
ここまでで、「農用地区域(青地)」と「農振白地(農用地区域外)」には、
土地の活用において大きな違いがあることをご説明してきました。
この章では、両者の違いを一覧表にまとめ、どのような点で判断や手続きが変わるのかを整理します。
自分の農地がどちらに該当するのかを把握したうえで、どのような活用が可能なのか・どのような規制があるのかを確認する際の参考にしてください。
■ 青地と白地の比較一覧表
| 項目 | 農用地区域(青地) | 農振白地(農用地区域外) |
|---|---|---|
| 転用の可否 | 原則として不可(農振除外が必要) | 転用可能(農振除外は不要) |
| 関連法令と手続き | ①農振法:農振除外が必須 ②農地法:転用許可申請 | 農地法に基づき、転用許可または届出が必要 |
| 都市計画法の影響 | 市街化区域・調整区域いずれも転用不可(原則) | 区域により手続きが異なる(市街化区域なら届出、調整区域なら許可) |
| 主なメリット | ・農業基盤整備(補助金・融資)の対象になりやすい ・税制上の優遇措置(固定資産税・相続税 等) | ・農業以外の活用が可能(住宅・駐車場・事業用地など) |
| 主なデメリット | ・農業以外への転用が極めて困難 ・農振除外には高いハードルと長期間が必要 | ・青地のような補助金や税優遇は受けられない ・転用許可が下りない場合もある |
| 固定資産税の評価 | 「農地評価」により税額が低く抑えられる | 所在地によっては「宅地並み評価」で課税され、税額が高くなる可能性あり |
■ 判断・活用に迷ったら、行政書士への相談を
「青地」か「白地」かで、農地の将来性は大きく異なります。
特に、転用や売買、相続を見据えている方にとっては、この区分を正しく理解しているかどうかが、資産価値や事業計画に直結します。
迷ったときは、必ず行政の窓口や行政書士などの専門家にご相談ください。
5. 自分の農地が「青地」か「白地」かを調べるには?―確実な確認ステップ
農地転用を検討する上で、まず最初に確認すべきなのが「その農地が農用地区域(青地)に指定されているかどうか」です。
この区分によって、転用の可否や手続きの流れが根本的に変わるため、できる限り正確に・公式に確認することが非常に重要です。
5.1. Step 1:最も確実な方法は「市町村役場への問い合わせ」
農地が青地か白地かを正確に知るためには、その農地が所在する市町村の役場に直接確認するのがもっとも信頼性の高い方法です。
担当窓口は自治体によって異なりますが、以下のような名称の部署で対応してくれます:
- 農政課
- 農林水産課
- 産業振興課 など
農用地区域の指定は、各市町村が策定する「農業振興地域整備計画」に基づいて管理されており、地図(農業振興地域整備計画図)と台帳で公式に確認できます。
5.2. Step 2:問い合わせ前に準備しておくべき情報
窓口での照会をスムーズに進めるために、あらかじめ以下の情報を準備しておくことをおすすめします。
■ 必須情報:「地番」
確認に必要なのは、土地の「住所」ではなく、登記上の「地番」です。
■ 地番の確認方法
- 固定資産税の課税明細書
市町村から毎年届く納税通知書に添付。所有地ごとの地番が記載されています。 - 登記事項証明書(登記簿謄本)
法務局で取得可能。地番・地目・面積・所有者情報が確認できます。 - 登記済権利証(登記識別情報通知)
不動産を取得した際に法務局から交付される書類です。
5.3. Step 3:窓口での確認方法
準備した地番を持って、市町村の農業関連窓口を訪れ、以下のように確認を依頼します:
「〇〇市△△町〇〇番の農地が、農用地区域(青地)に指定されているか確認したいのですが。」
担当者が「農業振興地域整備計画図」と台帳を照合し、その土地が青地か白地かを教えてくれます。
5.4. 【参考】インターネットでの事前調査も可能
役場へ行く前に、概ねの目安を掴むためのオンラインツールも存在します。
■ eMAFF農地ナビ(旧:全国農地ナビ)
農林水産省が提供する地図型の情報検索サービスで、全国の農地の位置や一部の農振区分情報が閲覧できます。
- 地図上で対象地を選択すると、青地かどうかを色分け表示してくれる場合があります。
■ ただし、法的な確認には使えない点に注意
- eMAFF農地ナビの情報は法的証明力を持ちません
- 情報が古い可能性があるため、最終的な判断は必ず市町村で公式確認を行う必要があります
■ 効率的な調査の流れ(おすすめ)
- eMAFF農地ナビで大まかな所在地を確認
- 固定資産税明細書や登記簿で「地番」を特定
- 市町村役場で正式に確認し、青地・白地を確定
この3ステップを踏むことで、正確かつ効率的に農地の区分を把握できます。
用語解説:農地関連手続きで頻出するキーワードをやさしく整理
この記事で取り上げた農地関連の制度や手続きは、法律特有の用語が多く、少しとっつきにくく感じるかもしれません。
ここでは、特に重要な専門用語を中心に、制度の背景や法令との関係を交えてわかりやすく解説します。
■ 農振法(のうしんほう)
正式名称は「農業振興地域の整備に関する法律」。
市街化が抑制されている地域などにおいて、農業を将来にわたって安定的に続けていくための地域指定と土地利用の制限を目的とする法律です。
この法律に基づいて、各市町村が「農業振興地域整備計画」を策定し、その中で「農用地区域(青地)」を指定します。
■ 農地法(のうちほう)
農地の売買や貸借、転用などを規制する法律。
農地の確保と保全を通じて、日本の食料供給体制を守ることを目的としています。
農地を農業以外の目的で使用する場合(=農地転用)や、権利移転を伴う場合には、この法律に基づいて許可や届出が必要です。
違反した場合は、工事中止命令や原状回復命令、さらには懲役刑や高額な罰金(法人は最大1億円)といった厳しい罰則もあります。
■ 農地転用(のうちてんよう)
農地(田や畑)を、住宅、駐車場、倉庫、資材置き場、太陽光発電施設など農業以外の目的に使用することを指します。
土地の形状を変えなくても、耕作のために使われていなければ、原則として「転用」に該当します。
例:
- 畑のまま資材置き場に使う → 転用
- 田んぼに砂利を敷いて駐車場にする → 転用
■ 市街化区域(しがいかくいき)
都市計画法に基づき、今後10年以内に優先的・計画的に市街化(=住宅・商業地として開発)を進める区域として定められたエリアです。
この区域内では、農地転用の許可は原則不要で、農業委員会への「届出」のみで転用が可能です。
■ 市街化調整区域(しがいかちょうせいくいき)
都市計画法に基づき、市街化を抑制すべき区域として定められたエリア。
無秩序な開発を防ぎ、農地や自然環境を保全する目的があります。
この区域内では、開発や建築行為は原則として制限され、農地転用には厳格な許可審査が必要です。
■ 農振除外(のうしんじょがい)
農業振興地域整備計画において「農用地区域(青地)」に指定された土地を、例外的に農用地区域から除外するための手続きのこと。
正式には「農用地利用計画の変更申出」といいます。
この除外を認めてもらうためには、農振法第13条第2項に定められた極めて厳格な要件をすべて満たさなければならず、実務上のハードルは非常に高くなっています。
6. まとめ:農地の未来を考えるなら、まず“区分”の確認から
農地を住宅や駐車場に転用したい――そう思ったとき、最初に確認すべきなのは「青地」か「白地」かという区分です。
この違いひとつで、必要な手続き・かかる期間・費用・実現可能性が大きく変わります。
- 青地(農用地区域):農業のために強く保護されている土地。転用には「農振除外」という高いハードルがある
- 白地(農用地区域外):一定の条件のもとで転用の可能性があるが、農地法や都市計画法の規制は残る
農地は大切な資産であると同時に、法律で厳しく守られている「特殊な土地」でもあります。
だからこそ、活用を検討する際には、正確な情報に基づいて慎重に進めることが大切です。
✅ 行政書士による事前相談で、スムーズな農地活用を実現しませんか?
当事務所では、農用地区域の確認から、農振除外・農地転用の申請サポートまで、農地の活用をめぐるすべてのステップを一貫してサポートしています。
- 「自分の農地が転用できるか調べてほしい」
- 「手続きにどれくらいの時間と費用がかかるか知りたい」
- 「市街化区域なのに許可が必要と言われた…」
など、お悩みに応じたご提案が可能です。
まずはお気軽にご相談ください。