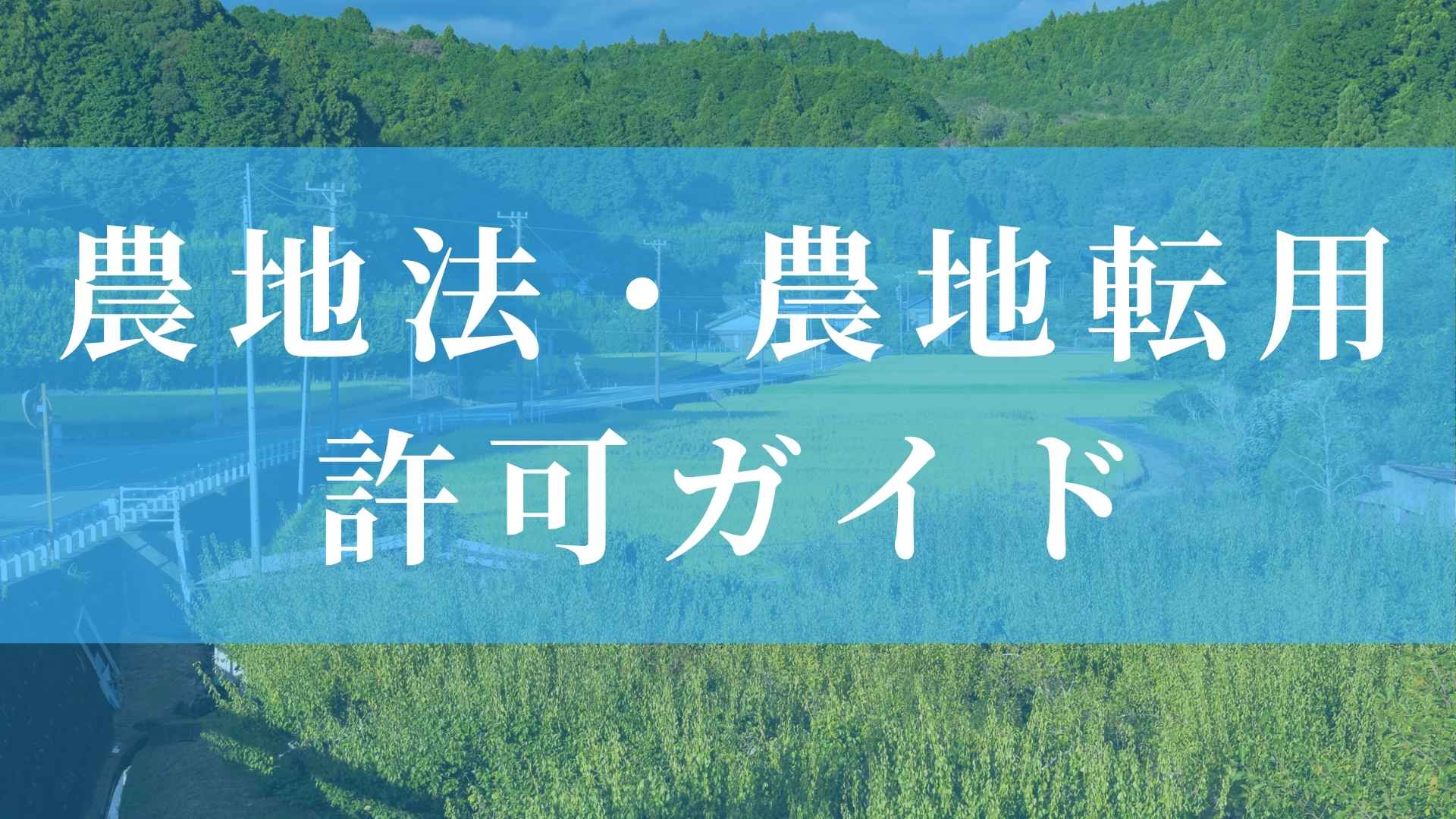こんにちは、行政書士の三澤です!
「相続した畑に家を建てたい」「隣の田んぼを駐車場にしたい」――
このような土地活用を考えたとき、多くの方がまず思い浮かべるのが「農地法」に基づく手続きではないでしょうか。
しかし、ここに思わぬ落とし穴があります。
実は、その土地が「農用地区域」に指定されていると、そもそも農地法の許可申請をすることすらできません。
その前に「農業振興地域の整備に関する法律(農振法)」という、もう一段階上の規制をクリアしなければならないのです。
この「農振法」の存在を知らずに進めてしまったことで、せっかく時間やお金をかけて準備した計画が頓挫してしまう…
そんなケースは決して珍しくありません。
この記事では、農地法と農振法の違い、そして転用にあたって最も重要な「農振除外」の手続きについて、
専門的な観点から、わかりやすく・正確に解説していきます。
「農地転用を考えるすべての方」にとって、必ず知っておいていただきたい内容です。
農地活用の第一歩は「農地法」と「農振法」の役割を知ることから
農地を使いたい――そう思ったとき、立ちはだかるのが二つの法律です。
一つは「農地法」。
これは、個別の農地がきちんと使われているかを監督する“現場の番人”のような法律です。
もう一つが「農業振興地域の整備に関する法律」、いわゆる「農振法」。
こちらは、国や自治体が将来の農業のあるべき姿を描きながら、大きな視点で土地の使い方を計画する“設計図”のような役割を担います。
この2つの法律の役割をきちんと理解しておくことが、土地活用の成功に直結します。
以下、それぞれの特徴を見ていきましょう。
農地法とは?一筆ごとの農地を守る「現場監督」のような法律
農地法(昭和27年法律第229号)は、農業に必要な農地を守り、国民の食料供給を安定させることを目的とした法律です。
この法律の役割は、「農地が農地としてきちんと使われているかどうか」を個別に見守ること。
まさに“一筆ごとの農地”に目を光らせる現場の監督官のような存在です。
農地法では、農地の売買や転用といった具体的な「行為」に対して、3つの許可制度を設けており、
土地の用途変更や所有者の変更には、基本的に市町村の農業委員会の許可が必要になります。
主な規制内容(農地転用の三つの許可)
農地法における許可制度は、以下の3種類に分類されます。
- 3条許可:農地のままの権利移動
農地を農地のまま、売買・賃貸する際に必要です。
例)農家Aさんが、農家Bさんに畑を売る場合。 - 4条許可:所有者自身による転用
自分が所有している農地を、自分で農地以外の用途に使うときに必要です。
例)農家Aさんが、自分の畑に自宅を建てる場合。 - 5条許可:転用を目的とした権利移動
農地を農地以外の用途に転用することを前提として売買・賃貸する際に必要です。
例)Bさんが農家Aさんの畑を購入し、そこに自宅を建てる場合。
これらの許可制度は、「農地のまま使うのか」「転用するのか」「誰が使うのか」によって分けられており、どの許可が必要かを見極めることが、農地活用の出発点となります。
なお、農地法は「現況」で判断されるのが特徴で、登記簿上の地目がたとえ「山林」や「原野」であっても、実際に耕作されていれば“農地”と見なされる点にも注意が必要です。
農振法とは?農業の将来を見据えた「土地利用の設計図」
農業振興地域の整備に関する法律(通称:農振法、昭和44年法律第58号)は、
個々の農地ではなく、地域全体を対象に“農業の将来像”を描くための法律です。
農地法が「いま」の農地利用を管理するのに対して、
農振法は「これからの農業のあり方」を前提に、土地の使い方を長期的に計画します。
法律の目的と全体像
農振法の目的は、日本の食料生産を安定的に支えるため、
将来にわたって農業を継続すべき地域をあらかじめ定め、優良農地を計画的に保全・育成することです。
このために、国・県・市町村が次のような段階で計画を策定します。
- 国(農林水産大臣):
全国的な農地確保の方向性を示す「基本指針」を策定。 - 都道府県知事:
基本指針に基づき、県内における農業推進エリアを定める「農業振興地域整備基本方針」を策定。 - 市町村:
それぞれの地域で実際に土地をどう活用していくかを具体化した「農業振興地域整備計画」を策定。
この「整備計画」の中で、特に重要なのが 「農用地区域」 の指定です。
これは、今後10年以上にわたり農業上の利用を確保すべき土地とされ、
農地転用が原則として認められない“最重要保全エリア”です。
食料安全保障との関係
近年の法改正では、「食料安全保障の観点から必要な農用地等を確保する」ことが
農振法の目的として明記されました。
これは、日本の農業が直面する課題――高齢化、耕作放棄地の増加、食料自給率の低下――
などを受けて、優良農地を戦略的に守る姿勢が一段と強まっていることを示しています。
つまり農振法は、個別の農地取引の話にとどまらず、
地域の農業インフラ全体を支える「土台」として機能している法律なのです。
「農振法」と「農地法」はどう違う?両者の関係を正しく理解しよう
「農地を活用するには農地法の許可が必要」と思っていても、実際にはもう一つ、避けて通れない法律が「農振法」です。
両者はともに“農地を守る法律”であることに違いはありませんが、アプローチの仕方や法的な力関係はまったく異なります。
ここでは、農振法と農地法の役割・立ち位置・適用範囲の違いを明確にしていきます。
これらを理解することは、スムーズな手続きを行う上で非常に重要です。
規制される「エリア」の範囲がまったく違う
まず最初に知っておくべき違いは、「どこに対して規制がかかるのか」という地理的な範囲です。
■ 農地法の規制エリア:日本全国すべての農地が対象
農地法は、全国のすべての「農地」が対象になります。
ここで言う「農地」は、登記簿上の地目に関係なく、実際に耕作されている土地を指します。
たとえば、地目が「山林」や「原野」となっていても、現況で野菜や米を育てていれば、それは農地として扱われ、農地法の規制を受けることになります。
■ 農振法の規制エリア:「農業振興地域」内に限られる
一方、農振法の規制が及ぶのは、都道府県が指定した「農業振興地域」内の土地に限られます。
つまり、対象エリアが限定されており、農業振興地域に含まれていない都市部や山間地の土地などは、
そもそも農振法の規制の対象外です。
この「エリアの違い」は、農地転用の難易度や手続きの要否に直結するため、
計画のスタート時点で必ず確認しておくべきポイントです。
農地法は「個別の農地の行為規制」、
農振法は「地域全体の土地利用計画(ゾーニング)」という性格の違いが、
このエリアの違いにも表れています。
なぜ「農振法」が先に来るのか?〜両法律の優先関係について
農地法と農振法は、どちらも農地を守るための法律ですが、
実務の中では「農振法が農地法よりも優先する」という明確なルールがあります。
この理由は、両法律の性質の違いにあります。
- 農振法は「計画」
地域全体の土地利用を長期的な視点で整備・誘導するもの。
つまり“どの土地をどのように使うか”を決める法律です。 - 農地法は「許可」
個別の土地取引や転用行為について、“それを認めるかどうか”を審査する法律です。
したがって、もしその土地が「農用地区域」に指定されていた場合、
そこは農業を将来にわたって守るべき土地として位置づけられているため、
たとえ農地法の審査に進みたくても、その前に「農振法の壁」を越える必要があるのです。
たとえば、農地法第5条の転用許可を申請しようとしても、
土地が農用地区域に含まれている場合、農業委員会は申請書すら受け取ってくれません。
必ずこう言われるでしょう:
「この土地は農用地区域内ですので、まずは市役所の農政課で農振除外の手続きを済ませてください。」
このように、農振法の規制は、農地法の審査に進む「入口の門番」として機能しているのです。
手続きの正しい順番:まず「農振除外」、その後「農地転用許可」
上記の優先関係を踏まえると、農用地区域に指定されている土地を転用したい場合、
手続きの順番は以下の通り、絶対に守らなければならない流れがあります。
【ステップ1】農振法による「農振除外」の申出
まずは、市町村に対して農用地区域からその土地を外してもらうための手続き、
つまり「農振除外」の申出を行います。
この手続きは、いわば地域のマスタープランを変更してもらう“特別なお願い”であり、
申請時期も限られていて、審査も非常に厳格です。
【ステップ2】農地法による「転用許可申請」
農振除外が正式に認められた後、初めて農業委員会に対して
農地法第4条または第5条の「転用許可申請」を行うことができます。
この順番を無視して、先に農地法の申請をしようとしても、手続きは進みません。
なぜなら、農用地区域はあくまで「原則転用禁止」のエリアだからです。
このように、農地活用の計画を立てる際には、
まずその土地が「農用地区域」に該当するかどうかを確認し、
必要があれば農振除外の可能性を早い段階で見極めることが、成功への第一歩となります。
表1:農地法と農振法の違いがひと目でわかる比較表
| 比較項目 | 農地法 (昭和27年法律第229号) | 農振法(農業振興地域の整備に関する法律) (昭和44年法律第58号) |
|---|---|---|
| 目的 | 農地の権利移動や転用を規制し、 個々の農地を保全することで、 食料の安定供給を確保する | 将来の農業振興のために 地域単位で土地利用を計画し、 優良農地を確保・保全する |
| 法の性格 | 個別の行為に対する「許可制度」 (転用・権利移動の都度審査) | 地域全体の「ゾーニング制度」 (長期的な土地利用の枠組みを計画) |
| 規制対象エリア | 日本全国の農地すべてが対象 | 都道府県が指定する「農業振興地域」 の中に限って適用される |
| 主な規制内容 | ・3条許可(農地のまま権利移動) ・4条許可(自己による転用) ・5条許可(転用目的の権利移動) | ・農用地区域に指定された土地の 原則転用禁止 ・除外には厳しい条件と審査が必要 |
農地活用のカギを握る「農用地区域」と「農振除外」
農地転用を考える上で、避けて通れないのが「農用地区域」の存在です。
この区域に指定されているかどうかで、手続きの難易度や選択肢が大きく変わってきます。
そして、農用地区域に該当する土地を転用したい場合に必要となるのが、
その指定を解除する「農振除外」という重要な手続きです。
まずは、農用地区域とは何か、そして「青地」「白地」との違いについて整理しましょう。
「農業振興地域」「農用地区域(青地)」「白地」──3つの区分の違いを理解しよう
農地がどの区域に属しているかによって、転用の可否や手続き内容が大きく異なります。
以下の3つの区分を押さえることが、最初のステップです。
■ 農業振興地域(農振地域)
都道府県が「将来にわたって農業を振興すべき」と判断したエリアで、その中でさらに土地利用の計画が立てられています。
これは、農振法に基づいて整備される大枠のゾーンであり、市街地や工業地域などは通常含まれません。
■ 農用地区域(通称:青地)
農振地域の中でも、特に農業利用を優先的に守るべき土地が「農用地区域」です。
都市計画図などで青く塗られることが多いため、「青地(あおち)」と呼ばれます。
青地に指定される主な条件は次のとおりです。
- 10ヘクタール以上のまとまった農地
- 公共投資(ほ場整備など)が行われた区域
- 用排水路・農道に隣接する農業インフラが整った土地
この区域に指定された農地は、住宅や駐車場、太陽光発電など農業以外への転用が原則として「一切認められない」非常に厳しい保全対象です。
■ 農用地区域外の区域(通称:白地)
農振地域には含まれているものの、青地には該当しない土地です。
地図上で色が塗られていないことから「白地(しろち)」と呼ばれます。
白地は、青地と比べて規制が緩やかで、転用を希望する場合も農振除外を経る必要はありません。
ただし、「農地法」に基づく許可申請は別途必要である点には注意が必要です。
その土地が「青地」か「白地」のどちらに該当するのかが、手続きの難易度・期間・実現可能性に大きく影響します。
これは、市町村の農政課等担当部署で確認できますので、計画の初期段階で必ずチェックしましょう。
「農振除外」とは?──農用地区域から外すための正式な手続き
「農振除外」とは、正式には「農業振興地域整備計画における農用地区域からの除外」のことを指します。
簡単に言えば、「青地(農用地区域)」に指定されている農地について、
そのゾーニングを外して「白地」扱いに変更してもらうための手続きです。
この除外が認められることで、初めて農地転用の許可申請(農地法4条・5条)に進むことができるようになります。
つまり、農振除外は「転用へのスタートラインに立つための前提条件」なのです。
なぜ農振除外が必要なのか?──“計画優先”の原則を理解する
農振除外が必要となる最大の理由は、農用地区域(青地)に指定された土地は、
法的に「農業利用を将来にわたり確保すべき土地」として保護されているからです。
たとえその土地が何年も耕作されておらず、見た目は雑草だらけの空き地のように見えたとしても、
農業振興地域整備計画図で青地に指定されていれば、それは“法律上の優良農地”として扱われます。
行政機関は、土地の現況ではなく「公的な計画図」に基づいて判断します。
そのため、どんなに転用したい理由があっても、農振除外を経なければ転用の申請(農地法の許可)は一切受け付けられません。
また、農振除外は単なる「申請」ではなく、あくまでも「計画変更の申出」という極めて重い手続きです。
市町村の農政課が定める受付時期・要件・審査プロセスを丁寧にクリアしていく必要があります。
このように、農用地区域にかかる土地を活用したい場合、最初に立ちはだかるのが「農振除外」という高いハードルです。
だからこそ、計画を立てる段階でこの手続きの必要性を見極め、しっかりと準備を整えておくことが成功のカギとなります。
「農振除外」の具体的な手続きとクリアすべき要件とは?
農振除外は、「農業振興地域整備計画」の中で農用地区域(青地)として指定された土地を除外(ゾーニングの変更)してもらうための手続きです。
この除外が認められるかどうかで、転用計画の成否が大きく左右されます。
ただし、農振除外は一般的な許認可申請とは異なり、市町村が策定した公的な計画の変更を求めるという性質を持つ、非常に重い手続きです。
そのため、流れは複雑で期間も長く、かつ厳格な審査が行われます。
農振除外の手続き:一般的な流れ
農振除外の手続きは自治体によって細部が異なるものの、概ね以下のようなステップで進んでいきます。
① 事前相談(農政担当課への訪問)
まずは、市町村の農政担当課に計画の概要を相談します。
この段階で、土地の現況、用途、除外の可能性、必要な添付資料、関係機関との調整事項など、
全体の流れを把握しておくことが極めて重要です。
※ 他法令(開発許可、建築確認など)にかかわる要件の確認も並行して行う必要があります。
② 農振除外の申出(書類提出)
自治体が年に数回設ける「受付期間内」に、正式な申出書と必要書類を提出します。
受付期間は限定的かつ短期間であることが多く、
このタイミングを逃すと申請が半年~1年単位で遅れる場合もあります。
③ 市町村内での審査・関係機関との協議
提出された申出書は、市町村内部で審査され、農業委員会、土地改良区、水利組合など、地域の関係機関との調整が行われます。
この段階で補足資料の提出や説明が求められることもあります。
④ 都道府県との協議
市町村は、除外案を県に提出し、都道府県と協議を行います。
都道府県は広域的な土地利用の視点から、除外の可否を判断します。
⑤ 公告・縦覧・異議申立期間
除外を含む整備計画の変更案は「公告」され、30日間の縦覧期間が設けられます。
関係住民や利害関係者は、その後15日以内に「異議申立て」が可能です。
⑥ 計画変更の決定・通知
異議がなければ、市町村は正式に農業振興地域整備計画を変更し、
申出者に対して「農用地区域からの除外決定通知書」が交付されます。
この通知をもって、初めて次のステップである農地法に基づく転用許可申請へ進むことができます。
このように、農振除外は多段階かつ長期にわたるプロセスです。
行政との綿密なやり取りと、計画全体の戦略的設計が求められる重要な手続きといえるでしょう。
農振除外にかかる期間は?──申出から完了までの目安
農振除外の手続きは、非常に時間がかかるのが特徴です。
提出から結果が出るまでの期間は、概ね6ヶ月〜1年超。
事前相談や必要書類の準備期間を含めれば、計画開始から1年半以上かかるケースもあります。
また、農用地区域からの除外は市町村が年に数回しか受け付けていない場合が多く、
申出のタイミングを逃すと次の受付まで半年待ちということも十分にありえます。
したがって、スケジュールには十分な余裕を持って取り組む必要があります。
農振除外が認められるための「5つの要件」
農振除外は誰でも簡単に通る手続きではありません。
農業振興地域整備計画を変更するという性質上、非常に厳格な審査基準が設けられています。
農振法第13条第2項に基づき、次の「5つの要件」をすべて満たさなければ除外は認められません。
要件① 必要性・非代替性
その土地でなければならない、客観的な理由が必要です。
単に「自分の土地だから」や「他の土地は高いから」という理由は通りません。
- 他の白地や宅地などで代替できないことを証明
- 自己所有地以外も含めて周辺調査が必要
要件② 地域営農への影響が小さいこと(集団性・効率性)
除外によって周辺農地の集団性や作業効率が損なわれないことが求められます。
- 大きな区画の中央だけを除外するようなケースはNG
- 周辺の営農活動との一体性を考慮
要件③ 担い手(認定農業者等)の利用計画を妨げないこと
その土地が将来的に地域の担い手農家に集積される予定がある場合、
それを妨げるような除外は基本的に認められません。
- 担い手が確保されているか、市町村や農業委員会が確認
要件④ 農業用施設(用排水路・農道等)への影響がないこと
水路や農道など、農業インフラの機能を阻害する計画は不可です。
- 水の流れを妨げない
- 公共施設との物理的・機能的な整合性を要確認
要件⑤ 土地改良事業後8年以上経過していること
その土地が国や自治体による土地改良事業(ほ場整備等)の対象地である場合、
事業完了から8年以上が経過していなければ、原則として除外は認められません。
- 年度起算に注意(完了年度の翌年度からカウント)
これら5要件のうちひとつでも欠けると、申出は却下されます。
計画の初期段階から丁寧な確認と根拠の整理が重要です。
どんなケースで農振除外が必要になるのか?──代表的な具体例
以下のようなケースでは、農振除外が必要となる可能性が極めて高くなります。
■ 青地に住宅を建てたい場合(分家住宅・自己住宅など)
- 自宅用の敷地として農地を活用したい場合
- 周辺の白地では代替できないことを証明する必要あり
- 特に「非代替性」の立証が最大のハードルに
■ 工場・倉庫・駐車場などの事業用地として使いたい場合
- 既存事業の敷地拡張など、現地利用に合理性がある場合のみ認められる可能性あり
- 新規事業であれば白地を探すのが原則
■ 太陽光発電設備を設置したい場合(非農業型)
- 青地においては原則として認められません
- 太陽光は代替地が豊富と判断されやすく、非代替性の要件が極めて厳格に判断される
農振除外の申出は、「単なる手続き」ではなく、
「この土地でなければならない理由」を法的・客観的に証明する戦略的プレゼンです。
だからこそ、専門的な判断と丁寧な準備が成功のカギを握ります。
農地の転用には行政書士の力が不可欠です
ここまで見てきたように、「農用地区域(青地)」の農地を転用するには、
- 農振法によるゾーニング(計画)の壁
- 農地法による行為規制の壁
- そして長期かつ厳格な手続きのプロセス
という、三重のハードルを越える必要があります。
特に「農振除外」は、ただ申請書を出せばよいというレベルの話ではなく、
なぜその土地でなければならないのかという根拠を法律と事実に基づいて論理的に構築し、
複数の行政機関を説得していく高度な対応が求められます。
さらに近年、農地制度は食料安全保障の観点から改正が続いており、
今後は除外・転用の審査がますます厳しくなることが予想されます。
このような複雑かつ重たい手続きを、個人で行うのは非常に負担が大きいのが実情です。
行政書士に依頼する4つの大きなメリット
① 時間と手間の大幅な削減
何度も役所に足を運び、書類を収集・作成し、関係機関と調整を行うのは非常に労力がかかります。
行政書士に依頼すれば、これらの工程を一任でき、本業やご家庭に集中できます。
② 許可の可能性を最大化する「戦略的申請」
農振除外が通るかどうかは、立証内容や書類の作り方に大きく左右されます。
行政書士は、審査側の視点をふまえた説得力のある申請書類を構築し、
許可の可能性を最大限に高めるための戦略的支援を行います。
③ 関係機関との調整をスムーズに進行
農政課、農業委員会、土地改良区、県庁など、関係機関との協議・調整が必要不可欠です。
行政書士はその橋渡し役となり、スムーズな進行をサポートします。
④ ワンストップで後続手続きまで対応可能
農振除外が終わっても、農地転用許可申請、開発許可、建築確認など次のステップが続きます。
農地手続きに精通した行政書士であれば、全体の流れを見据えたワンストップ対応が可能です。
農地の転用には、単なる書類作成ではなく、法的知識と現場感覚を兼ね備えた対応が求められます。
大切な資産を無駄にせず、計画を確実に進めるためにも、ぜひ専門家である行政書士にご相談ください。