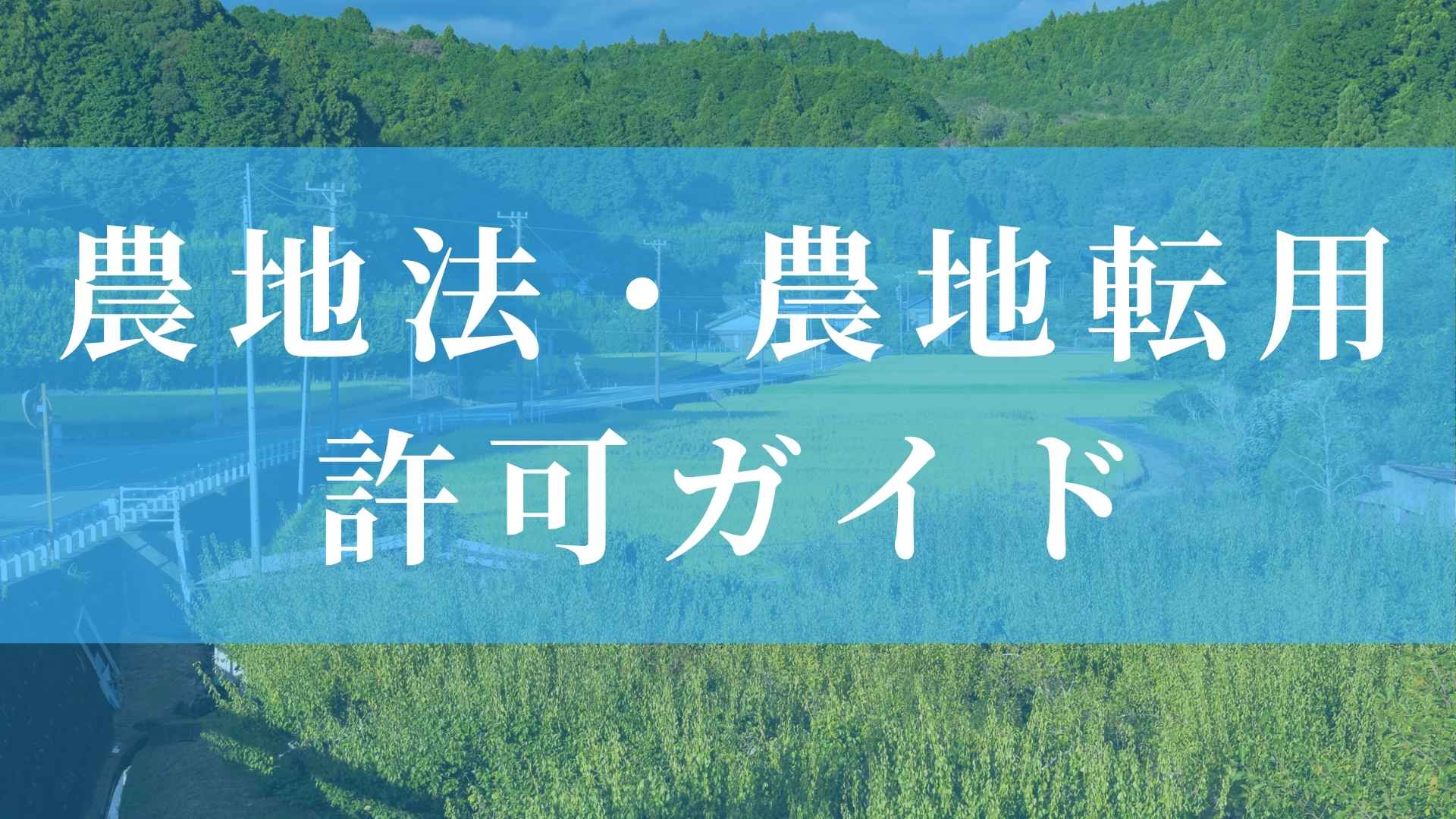こんにちは、行政書士の三澤です!
「所有している農地を宅地や駐車場として活用したい」——そんな計画を立てたとき、多くの方が最初に思い浮かべるのは「農地法に基づく農地転用許可」かもしれません。
しかし、計画の対象地が「農業振興地域」に指定されている場合、農地法の前に立ちはだかるもうひとつの大きな壁が存在します。それが「農業振興地域の整備に関する法律(農振法)」、そしてそこに基づく「農振除外」の制度です。
とくにその農地が「農用地区域」、通称「青地(あおち)」に指定されている場合、事態はさらに複雑になります。青地とは、国や市町村が「将来にわたって農業を守り育てるべき優良な農地」として位置付け、原則として農業以外の用途への転用が認められていない区域です。
この強力な保護を例外的に解除するための唯一の方法が、「農振除外」の手続きです。このプロセスを経なければ、そもそも農地転用の許可申請すら行うことができません。
ところが、多くの方がこの“二段構え”の制度設計を知らずに計画を進め、途中で行き詰まってしまうケースが後を絶ちません。
本記事では、農地転用に精通した行政書士の立場から、「農振除外とは何か」「なぜ1年以上かかる長期戦なのか」「どんな厳しい要件を満たす必要があるのか」といったポイントを、法律と実務の両面から丁寧に解説していきます。
この記事を読み終える頃には、「農振除外」がいかに慎重かつ戦略的に取り組むべき手続きであるかを、きっとご理解いただけるはずです。
1. 「農振法」と「農振除外」とは何か?
農地を転用する計画を立てる際、多くの方がまず意識するのは「農地法」による許可制度です。しかし、その前段階で「農振法(農業振興地域の整備に関する法律)」という、もう一つの重要な制度が存在します。
そして、この農振法に基づいて指定された「農用地区域(青地)」に土地が該当している場合、農地転用の前にまず「農振除外」という手続きをクリアしなければなりません。
ここでは、農振法とはそもそもどのような法律なのか、そして農振除外がどういった位置づけの制度なのかを、農地法との関係も含めて整理していきます。
1.1 農振法とは? 農業を守るための「面」的な区域規制
「農業振興地域の整備に関する法律(農振法)」は、個々の農地の利用を規制する「農地法」とは異なり、地域全体の農業のあり方を守るために作られた法律です。
高度経済成長期に急速な都市開発が進み、貴重な農地が次々と失われたことを受けて制定されたこの法律は、「地域として農業を振興すべきエリア」を面的に指定し、そのエリア内では農業以外の開発行為を厳しく制限します。
つまり、農地法が「点(個別の土地)」に着目しているのに対し、農振法は「面(地域全体)」を対象にしたゾーニング制度です。
このため、たとえ個別の農地で農地転用の意向があっても、まずその土地が属する農業振興地域(特に農用地区域)としての規制をクリアしない限り、農地法に基づく転用許可申請へは進めません。
農振法と農地法は、階層構造として「面→点」の順に審査される仕組みになっていることを、まず押さえておく必要があります。
1.2 農用地区域(青地)とは? 国が重点的に守るべき「一級農地」
「農用地区域(のうようちくいき)」とは、農業振興地域の中でも特に農業利用に適している土地として、市町村が明確に指定するエリアのことです。地図上で青色に塗られることが多いため、一般的に「青地(あおち)」と呼ばれています。
この青地は、単に農地というだけではありません。以下のような特徴を備えた、農業振興にとって極めて重要な土地が対象となります:
- 10ヘクタール以上のまとまりを持つ集団農地
- 土地改良(圃場整備や排水・かんがい設備など)が実施された高機能な農地
- 地域の特産品を支える基盤的な農地
つまり、青地は「国や自治体が将来にわたって農業を守り育てるべき」と判断した、いわば“国宝級”の農地です。
そのため、原則として宅地・駐車場・資材置場・太陽光発電施設といった、農業以外の目的での使用(=転用)は一切認められていません。青地への規制は非常に強く、これを解除するには相当な正当性が必要になります。
1.3 農振除外とは? 転用の第一関門となる「前提手続き」
では、青地に指定された土地は、将来にわたって永遠に転用できないのでしょうか。
実はそうではありません。「やむを得ない事情があり、かつ法律で定められた厳しい条件をすべて満たす場合」に限り、その土地を農用地区域(青地)から除外してもらうための手続きが存在します。それが「農振除外(のうしんじょがい)」です。
農振除外とは、市町村が定めた農業振興地域整備計画を変更し、特定の土地について青地の指定を解除するための行政手続きです。
ここで重要な点は、「農振除外=農地転用許可」ではないということです。
農振除外はあくまで、農地法による転用許可の「前提条件」を整えるためのものであり、除外が認められた時点でようやく農地転用許可のスタートラインに立てる、という位置づけになります。
青地の農地を活用するには、
- 農振除外(=エリア規制の解除)
- 農地転用許可(=用途規制の解除)
という“二段階のハードル”を越える必要があり、特に農振除外の難易度は高く、計画全体の成否を左右する重要なステップとなります。
2. なぜ農振除外は「1年がかりの長期戦」なのか? 申請から決定までの全体像
農振除外の申請手続きは、「申請書を出して数ヶ月で許可が下りる」といった単純なものではありません。実際には、市町村・関係機関・都道府県など複数の主体が関与し、各段階で時間と調整が必要となるため、半年から1年以上かかるのが一般的です。
本章では、申請の流れをステップごとに追いながら、なぜこれほどの長期戦になるのか、その背景と構造をわかりやすく解説します。
Step 1:市町村への事前相談 ― すべての出発点
農振除外の手続きは、いきなり申請書を提出するのではなく、まずは市町村の農政担当課(例:農業振興課や農政課など)への「事前相談」から始まります。
この相談は形式的なものではなく、実質的な第一関門です。
- 計画地が青地に該当するか
- 除外が可能性として検討される区域か
- 自治体独自の基準や運用ルールに適合するか
など、計画そのものの見通しを確認する重要なプロセスです。
また、多くの市町村では「申出の受付期間」が年に数回しか設けられていないため、次回の申請タイミングや事前協議の締切についても、この段階で確認しておく必要があります。
ポイント:
- 受付の“予約”のような意味合いもある
- 計画の実現可能性を行政の視点から初期判断できる
- ローカルルールや事前提出資料の確認もここで行う
この事前相談で否定的な見解が示されれば、その時点で見直しや中止の判断を迫られることもあります。だからこそ、最初の一歩から専門家に相談することが、成功の近道となるのです。
Step 2:申請書の受付 ― 年に数回だけの“限られたチャンス”
農振除外の申出は、農地転用許可申請のように「いつでも提出できる」ものではありません。
多くの市町村では、申出の受付時期が年に数回のみと決められており、それも数日から2週間程度の“極めて短い期間”に限定されているのが一般的です。
たとえば愛知県の場合:
| 市町村名 | 年間受付回数 | 受付期間の特徴 |
|---|---|---|
| 知多市 | 年4回 | 各季節に1回、比較的柔軟だが準備は必須 |
| 大府市 | 年4回 | 各月初15日間。事前相談は前月末までに完了必須 |
| 豊田市 | 年4回 | 月初3日間のみ。提出書類の完成度が求められる |
このように、受付スケジュールは自治体ごとに大きく異なります。加えて、受付停止中の自治体も存在するため、最新の運用状況を事前に確認することが極めて重要です。
受付のタイミングを逃すと…
- 次回の受付まで数ヶ月~半年待ち
- その間に申請書類の内容が古くなり、再提出が必要になることも
- 他法令とのスケジュールがズレて、計画全体の遅延に直結
このように、受付時期を見誤るだけで計画全体に大きな影響が出るため、申請準備は「逆算型」でのスケジュール管理が必須です。
とくに、複数の申請を同時進行で進める場合や、補助金・建築確認などと連動する場合には、申出の受付時期に合わせて全体設計を立てておくことが成功の鍵となります。
Step 3:市町村による内部検討と関係機関との協議 ― 本格的な審査がスタート
申請書が市町村に受理されると、いよいよ本格的な審査段階に入ります。
この段階では、単に提出書類をチェックするだけではなく、さまざまな部署や関係機関との間で横断的な協議が行われます。
関与する主な機関には、以下のようなものがあります:
- 農政担当課(窓口)
- 農業委員会(農地利用の適正性)
- 都市計画課(土地利用計画や用途地域との整合)
- 土地改良区(水利・農業インフラへの影響)
- 建設・開発関連部署(法令適合性)
各機関がそれぞれの視点から計画内容を検討し、農業振興地域や周辺環境への影響の有無を慎重に判断していきます。
この内部調整には数週間から数ヶ月を要することもあり、スムーズな進行には事前の情報整理と資料の正確性が不可欠です。
Step 4:公告縦覧と意見書の受付 ― 地域住民への情報公開と意見収集
内部検討の結果、計画案に問題がなければ、市町村は農業振興地域整備計画の「変更案」を作成し、公告・縦覧手続きに入ります。
この段階では以下のプロセスが行われます:
- 公告・縦覧(30日間)
計画変更案を役所やホームページ等で公開し、誰でも閲覧できる状態にします。 - 意見書受付(縦覧期間終了後15日間)
計画に対して異議のある住民や関係者からの意見を正式に受け付けます。
これは、行政手続法に基づく透明性の確保と、地域住民の声を反映するための極めて重要なステップです。
注意点:
- 隣接農家や地元住民からの異議が出る可能性
- 異議内容によっては手続きが中断・延期されることもある
- 農地法以上に“地元合意”が重視される傾向がある
公告期間中に十分な説明ができるよう、関係者への事前説明や合意形成の働きかけが成功の鍵になります。
Step 5:異議申出への対応 ― 合意形成の最後の壁
公告・縦覧後に提出された異議申出書について、市町村はその内容を精査し、必要に応じて申出人・関係者との調整を行います。
異議が出される主な理由としては:
- 開発による排水や農業インフラへの影響への懸念
- 周辺農地の営農条件の悪化(農薬散布や騒音など)
- 地域全体の土地利用方針との不一致
これらに対して、市町村は技術的・法的に問題がないかを再確認したうえで、申請者に対して追加説明や計画修正を求めることがあります。
また、異議の内容が合理的であり、改善が不可能な場合には申出が却下されるケースもあります。
この段階で求められること:
- 関係者への丁寧な説明と合意形成の努力
- 代替措置(排水路整備など)による影響緩和の提案
- 専門家を通じた調整の主導(行政書士・技術士など)
このプロセスは、計画に対する地域の“納得度”を確保するための最終関門とも言える段階であり、いかに周辺への配慮がなされた設計になっているかが問われます。
Step 6:都道府県への協議・同意 ― 最終判断を委ねる“上位審査”
市町村が計画案を最終的にとりまとめても、それで農振除外が確定するわけではありません。
次のステップでは、都道府県との協議および同意取得という、いわば“上位審査”が行われます。
農振除外は市町村単独では決定できず、法律上、都道府県の同意が不可欠とされています(農振法第13条第3項)。この同意は、単なる形式的な確認ではなく、以下の観点から厳格な検討が行われます:
- 法律や通知に定められた要件を満たしているか
- 都道府県独自の「同意基準」に適合しているか(例:愛知県同意基準)
- 広域的な農業政策との整合性が取れているか
都道府県は、申出地が農地全体に及ぼす影響や、制度の乱用を防ぐ観点から、市町村の判断を一段高い目線で精査します。そのため、都道府県からの指摘を受けて、市町村が再協議や計画修正を求められることもあります。
この段階での調整に時間がかかることも多く、事実上の“最終関門”と言える重要なステップです。
Step 7:決定・通知 ― 「除外完了」の正式なゴール
都道府県の同意が無事得られると、市町村は農業振興地域整備計画を正式に変更し、農用地区域(青地)からの除外が確定します。
その結果は、申出人に対して「農用地区域から除外された旨の通知」として文書で交付されます。これにより、晴れて次のステップである農地転用許可申請へと進むことが可能となります。
ただし、ここまでの一連の手続きには通常:
- 最短でも6ヶ月、長ければ1年以上の期間を要し、
- 各段階での調整や異議対応によって更なる遅延リスクも含まれます。
このステップでの重要ポイント:
- 決定通知書の内容と適用範囲を必ず確認すること(除外の範囲・地番・用途など)
- 転用許可の準備に速やかに移行できるよう、必要書類を整えておくこと
- 開発許可・建築確認など他法令とのスケジュール調整も視野に入れること
この通知が出た時点でようやく「スタートラインに立った」状態であり、計画の実現にはまだ複数の法的ステップが残されています。
だからこそ、農振除外は単なる“書類の手続き”ではなく、戦略的な工程管理が求められる行政プロジェクトだと理解しておくことが大切です。
3. 【最重要】農振除外が認められるための「5つの要件」
農振除外の手続きは、単に申請すれば通るものではありません。むしろ制度の基本スタンスは「原則不許可」であり、ごく限られた例外に対してのみ、厳しい審査を経て“特別に”認められる仕組みになっています。
その基準として農業振興地域の整備に関する法律(農振法)第13条第2項には、次の5つの要件が明記されており、この5項目すべてを同時に満たすことが除外の必須条件です。
要件を一つでも欠けば、その時点で不許可となるため、極めて高いハードルであることを理解しておく必要があります。
3.1 要件1:代替性の不存在 ― 他に適地がないことの合理的説明が必要
この要件は、農振除外を申請するうえで最も重要かつ、審査上もっとも厳しくチェックされる項目です。
簡潔に言えば、
「なぜ、その青地でなければならないのか?」
「ほかに使える土地が本当に存在しないのか?」
という問いに対して、客観的かつ論理的に説明できなければなりません。
行政が確認する「代替地」の範囲
- 申出人が所有する他の土地(青地以外)
- 周辺地域にある白地や市街化区域の土地
- 賃借や購入によって取得可能な土地も含む
つまり「自分の土地だから」「費用を抑えたいから」といった主観的な理由では、代替性の不存在は認められません。
説得力のある事例(代表例):
- 工場の拡張計画
既存工場と隣接する青地でしか効率的な動線が確保できず、生産体制上、他の立地では運用が成立しない。 - 社会福祉施設の設置
利用者の通いやすさやサービスエリア内での配置の妥当性から見て、他に同等の利便性を持つ土地が存在しない。 - 分家住宅の建築
家族の生活基盤(親世帯との近接性など)や地域条例の立地要件をすべて満たす土地が、該当する青地しかない。
このように、代替性の不存在を証明するには、計画の必然性・地理的条件・法規制・周辺環境といった多面的な観点から、資料と論理で組み立てられた説明書類を整える必要があります。
専門家のサポートが必須となる理由:
- 土地利用計画の整合性や関連法令との関係性を分析できる
- 説明書・理由書に説得力ある論理構成を持たせられる
- 客観的資料(地図、交通動線、他法令との関係)を組み合わせた証明力の高い申請書が作成できる
「代替性の不存在」は農振除外の通過可否を分ける最大のポイントであり、ここでの詰めの甘さが手続き全体の失敗につながることも少なくありません。
3.2 要件2:農用地の集団性や利用集積への支障が軽微であること ― 虫食い開発を防ぐ視点
農用地区域(青地)は、単体の農地というよりも、「面」としてのまとまり(=集団性)を重視して指定されています。
この要件は、除外を認めた結果として、その集団性や将来の農地利用の効率性が損なわれないかどうかを審査するものです。
なぜ“集団性”が重要なのか?
- 広大な農地がひとまとまりで維持されていれば、トラクターやコンバインなどの大型機械を効率よく使える
- 農薬の散布や水管理、収穫作業が一体的に行える
- 将来的な土地改良や圃場整備の計画を立てやすい
こうした背景があるため、真ん中の一画だけを除外して宅地や駐車場に転用するような“虫食い状態”は、原則として認められません。
認められやすい例:
- 農用地区域の端に位置し、すでに市街地や宅地が隣接している土地
- 除外によっても、農業機械の動線や水管理にほとんど支障が生じない場合
認められにくい例:
- 周囲を完全に青地に囲まれている、いわば“農地の真ん中”にある土地
- 除外によって農地の分断が生じ、営農効率が大きく低下する恐れがある場合
この要件では、「どこにある土地なのか」「どの方向からどう見ても支障が出ないか」という空間的・地理的な構造理解が極めて重要になります。
3.3 要件3:土地改良施設の機能への支障が軽微であること ― 水路や農道など農業インフラへの影響評価
農業を支える基本インフラである「土地改良施設」は、農振除外の審査においても非常に重要なチェックポイントです。
土地改良施設には以下のようなものが含まれます:
- 用水路・排水路(農業用水の供給・排水)
- 農道(作業車両の通行路)
- 暗渠排水、ため池、揚水機などの設備
これらの機能が、除外による開発計画によって妨げられたり、維持管理が困難になるような場合には、要件不適合と判断される可能性があります。
認められやすい例:
- 小規模な排水路が計画地に通っているが、開発に伴い適切な代替排水路や暗渠が整備される計画がある
- 施設の機能を損なわず、今後も周辺農地への水供給・排水が確保される構造になっている
認められにくい例:
- 周辺農家が共同利用する重要な用水路を分断・廃止してしまう計画
- 地盤改変や造成工事によって、水質が悪化し、下流農地への悪影響が予想されるケース
この要件では、単に「物理的に残す」だけでなく、施設の“機能”が維持されるかどうかが重視されます。見落とされがちですが、排水設計や維持管理計画まで含めた配慮が求められる要件です。
3.4 要件4:地域の農業の効率的・安定的経営への支障が軽微であること ― 地域の“担い手”を守る視点
この要件は、個別の農地の問題にとどまらず、その土地が除外されることで地域全体の農業経営にどのような影響が出るかを問うものです。
とくに重視されるのは、「認定農業者」などの地域の担い手による農業経営です。農地の除外が、彼らの農業計画にマイナスの影響を及ぼす場合には、許可されない可能性が高まります。
判断の観点:
- 除外対象地が、地域の主要な農業者にとって経営上重要な農地となっていないか
- 除外により、耕作面積が減少したり作業効率が低下するおそれがないか
- 地域農業全体のバランスや集積状況に悪影響がないか
認められやすい例:
- 長年放置されていて耕作されていない
- 認定農業者などからも利用希望が出ていない
- 地域農業の担い手層が実質的に関与していない土地
認められにくい例:
- 除外予定地を認定農業者が借りて耕作している
- 除外により、隣接地との一体的な耕作が困難になる
- 農地中間管理機構などが今後の利用を計画している
この要件は、「農業の法人化」「集積と大規模化」が進められている現在の農政方針と密接に関係しており、地域の農業構造そのものを壊すような除外は原則NGです。
3.5 要件5:農業振興地域整備計画の達成に支障がないこと ― 地域農業の将来ビジョンとの整合性
この要件では、申出地が個別に見て問題がなかったとしても、それが市町村が描く農業振興地域整備計画(いわば“農業の未来図”)に悪影響を与えないかが判断されます。
農業振興地域整備計画とは、市町村が策定する中長期的な農地活用の基本方針であり、
- 圃場整備の実施エリア
- 農業基盤整備の優先順位
- 農産物加工施設や直売所などの整備予定地
といった将来構想が盛り込まれています。
そのため、たとえ個別の除外に合理性があっても、将来の基盤整備と矛盾してしまう場合には許可されないことがあります。
認められにくい例:
- 市町村が将来、集中的な圃場整備を予定している区域にある
- 農地集積や農業施設整備など、将来の重点施策地と重複している
- 除外により、整備計画の連続性が断たれてしまう可能性がある
チェックすべきポイント:
- 該当地が農業振興地域整備計画書の中でどのように位置づけられているか
- 「除外を認めることで、周辺計画全体が成立しなくなる」リスクがないか
- 計画と矛盾しないよう、開発の配置や規模が調整可能か
この要件は、市町村の政策判断とも密接に関係するため、市町村の担当部署と早い段階で丁寧に調整を行うことが重要です。
4. 農振除外を安易に考えてはいけない理由と、行政書士の専門的支援の重要性
ここまで見てきたとおり、農振除外の手続きは一見すると「申請して待てば結果が出る」というシンプルなものに見えるかもしれません。しかし実際には、
- 年に数回しかない申出受付のタイミング
- 半年〜1年以上に及ぶ審査期間
- すべてを同時に満たす必要のある5つの法定要件
といった多くのハードルがあり、非常に高難度で戦略性の問われる行政手続きであることがわかります。
しかも、審査の中でとくに重視される「代替性の不存在」については、法令や行政実務の深い理解を前提に、客観的資料と論理構成によって説明責任を果たす必要があるため、一般の方が独力で取り組むには限界があります。
なぜ専門家のサポートが不可欠なのか?
農振除外を成功に導くには、以下のような複合的な支援が求められます:
- 戦略的判断と初期見立て
経験に基づいた実現可能性の判断と、要件をどうクリアするかの方針立て - 膨大な書類の整理と作成
登記簿・公図・土地利用計画図・事業計画書などを正確に揃え、審査の意図に合った形で提出 - 行政との交渉と調整
市町村や都道府県との協議を、専門用語を用いて円滑に進め、照会や修正要求にも即応できる体制を整える - 関連手続きとの連携
農振除外の完了後には、農地転用許可、開発許可、建築確認、登記手続きなどが連動します。行政書士は、他士業(土地家屋調査士や司法書士など)とのネットワークを活かし、これらを一貫してサポートできます。
費用は“コスト”ではなく、“成功への投資”
農振除外手続きに関する行政書士の報酬相場は、おおよそ25万円~とされます(※案件の難易度や内容により変動あり)。
これは、半年〜1年以上にわたる手続きの伴走と、申請成功率を大幅に高めるための専門知識と実務経験に基づいた「投資」であるとお考えください。
まとめ:
農振除外を「ちょっと申請してみよう」と軽く考えると、時間・労力・費用のすべてを失う結果となる可能性があります。
だからこそ、計画の初期段階から専門家に相談することが、もっとも合理的で確実な選択肢なのです。