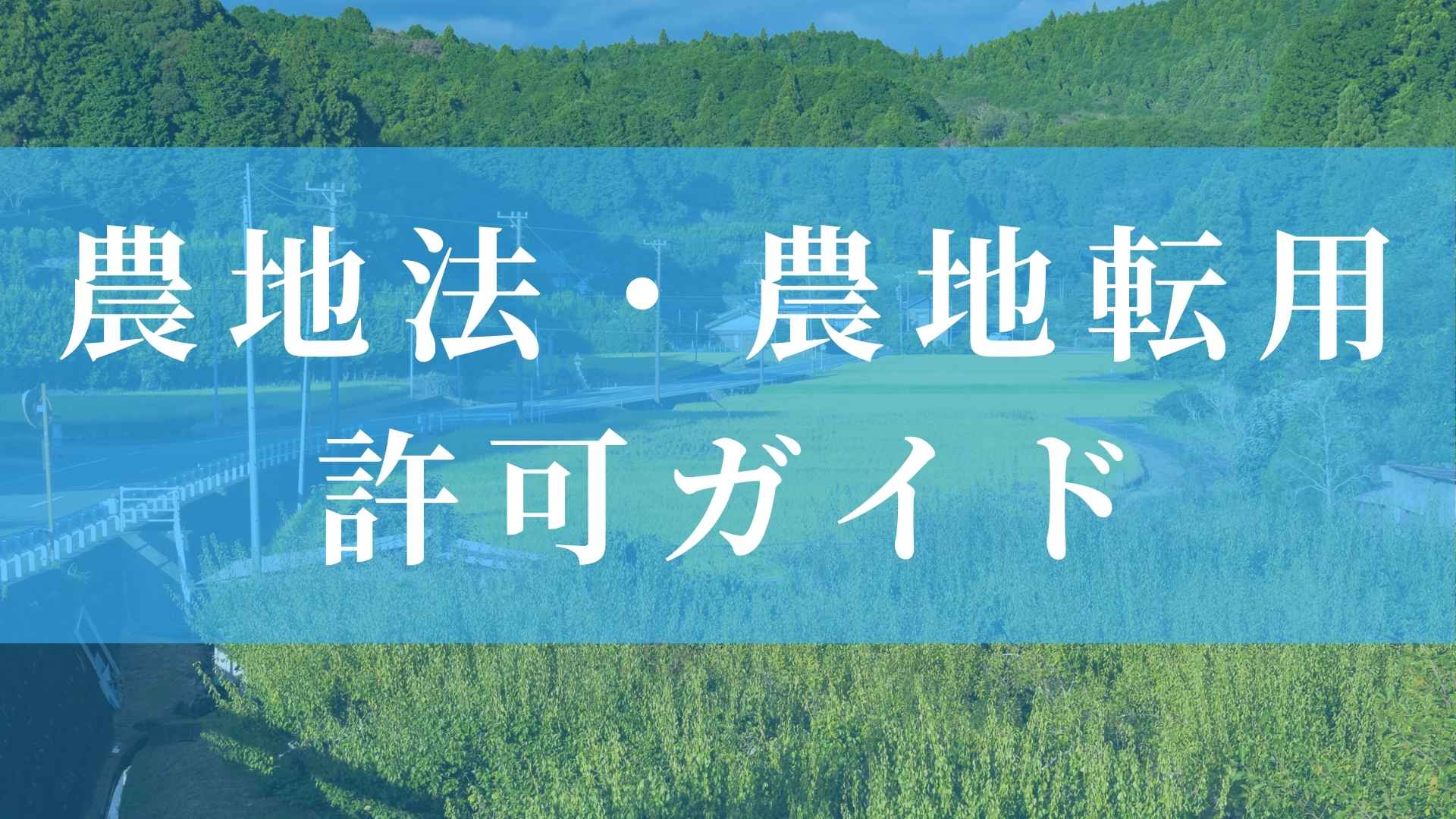こんにちは、行政書士の三澤です!
日本の農地法は、「農地は耕す人が持つべきもの」という『耕作者主義』を基本にしています。これは、農地が投資や投機の対象になってしまうのを防ぎ、安定した食料供給を守るための重要な理念です。
そのため、法人が農地を「所有」するには原則として厳しい制限があります。しかし、近年の農業現場では、担い手不足や高齢化が深刻化しており、経営の効率化や規模拡大、新規参入を進める必要性が高まっています。こうした背景のもと、一定の条件を満たした法人には例外的に農地の所有が認められる制度が用意されました。
それが、農地法に基づく「農地所有適格法人」という制度です。
この記事では、農業参入を検討している企業や、法人化を目指す農業者の方が、この制度を正確に理解し、実務上の判断に活かすことができるよう、次のような視点から解説を行います。
この記事でわかること
- 「農地所有適格法人」とは何か?(定義と法的な位置づけ)
- 制度の背景と名称変更の理由(旧:農業生産法人との違い)
- 資格を得るために満たすべき4つの要件
- 制度を利用するメリットと注意点
- 設立から許可取得までの手続きの流れ
- 要件を満たせなくなった場合のリスクと対応
本記事は、農地法および関連法令に基づき、行政書士としての実務的な視点も交えて解説します。制度の正確な理解と事前の準備が、安定した農業経営への第一歩となります。
農地所有適格法人の基礎知識
農地所有適格法人とは?〜「会社の種類」ではなく「法的な資格」です
まず最初に押さえておくべき重要なポイントは、「農地所有適格法人」は株式会社や合同会社といった法人格そのものを指す言葉ではない、ということです。
これは、既存の法人(株式会社・合同会社・農事組合法人など)が、農地法で定められた一定の要件をすべて満たしたときに得られる「資格」または「ステータス」を指します。
この定義は、農地法第2条第3項に明記されており、法人が農地を所有することを許されるための法的根拠となっています。
【ポイント】設立=農地所有適格法人ではない
「農地所有適格法人を設立したい」と相談を受ける場面では、しばしば「農地所有適格法人」という名前の特殊な法人格を登記するイメージを持たれていることがありますが、それは誤解です。
実際の手続きは次の2段階で構成されています。
- 通常の法人(非公開会社など)を設立する
農地所有適格法人の要件を満たす内容で、株式会社や合同会社などの法人を設立します。 - 農業委員会に農地取得の許可申請を行う
その法人が農地を売買・贈与などで取得するため、農地法第3条に基づく許可を申請し、審査を受けます。
この許可が下りて初めて、その法人は「農地所有適格法人」として認定され、農地の所有が可能になります。
【継続的な要件維持が必要】
農地所有適格法人のステータスは、農地を所有し続ける限り、4つの法的要件を常に満たし続けることが求められます。つまり、一度資格を得たから終わり、ではなく、継続的な体制整備と管理が必要なのです。
この「資格」であるという本質を理解していないと、法人化のプロセスや、農業委員会との許可手続きで思わぬトラブルを招く可能性があります。初動の段階で正しい理解と戦略的な設計が求められる制度です。
「農業生産法人」から「農地所有適格法人」へ――名称変更に込められた政策的な狙い
2016年4月1日に施行された農地法の改正により、それまで使われていた「農業生産法人」という名称は、「農地所有適格法人」へと変更されました。
一見すると単なる呼び名の変更に見えるかもしれませんが、これは単なる言葉の置き換えではなく、農業政策の方向転換を象徴する重要な変更でした。
【旧名称の問題点:生産重視の印象】
「農業生産法人」という呼び方は、その名のとおり「農産物の生産」に焦点がある印象を与えていました。しかし、近年の農業は「作って終わり」ではありません。
農業経営の現場では、一次産業(生産)に加えて、二次産業(加工)、三次産業(販売・サービス)を一体的に展開する「6次産業化」が主流になりつつあります。
【新名称の意味:農地所有の適格性に着目】
そこで導入された新名称「農地所有適格法人」は、法人が農地を所有するにあたって法的な適格性を備えているかという点に焦点を当てています。
この変更とともに、法人の「主たる事業」が農業であれば、関連事業(加工・販売・農家レストラン等)による売上も事業要件の判断に含められるようになり、要件が柔軟化されました。
つまり、「生産活動だけではなく、農業に関連する幅広いビジネスモデルも認めましょう」という姿勢が制度上に反映されたのです。
【アクセルとブレーキの絶妙なバランス】
ただし、制度の根幹にある「耕作者主義」の理念は変わっていません。
たとえば、
- 法人の支配権は農業者にあること(議決権要件)
- 役員の過半数が農業に常時従事していること(役員要件)
といった基本的な要件は厳格に維持されています。
この制度は、「農業の多様化・近代化を推進する」というアクセルと、「農地を守るための規制を維持する」というブレーキの両方を同時に機能させる――まさに政策的なバランスの妙といえるでしょう。
農地所有適格法人となるために必要な4つの要件(農地法第2条第3項)
法人が「農地所有適格法人」として認められるためには、農地法第2条第3項に定められた4つの要件をすべて、かつ継続的に満たす必要があります。
この要件は、一つでも欠ければ資格喪失となる可能性がある非常に重要な基準であり、単なる取得時のチェック項目ではなく、農地を所有し続ける限り守り続けるべき「条件」です。
以下の表は、それぞれの要件の概要と法的根拠をまとめたものです。
| 要件名 | 内容の概要 | 判断基準・条件 | 根拠条文 |
|---|---|---|---|
| 法人形態要件 | 一定の法人形態であること | 株式譲渡制限付き株式会社、持分会社、農事組合法人 | 農地法第2条第3項本文 |
| 事業要件 | 主たる事業が農業であること | 農業関連売上が総売上の過半数(50%超) | 同条第1号 |
| 議決権要件 | 農業関係者が実質的に経営を支配していること | 総議決権の過半数(1/2超)を農業関係者が保有 | 同条第2号 |
| 役員要件 | 経営陣が農業に深く関与していること | 過半数の役員が常時従事+1名以上が実際の農作業従事者 | 同条第3号および第4号 |
この4つの要件は、単独ではなく総合的に連動しており、農地の投機的利用を防ぎつつ、持続可能で安定した農業経営を実現することを目的としています。
農地所有適格法人になれる法人の形|法人形態要件
農地所有適格法人として認められるには、その法人の「形」が農地法で定められた種類である必要があります。これが「法人形態要件」と呼ばれるものです。
農地法第2条第3項本文により、以下の法人形態に限定されています。
- 農事組合法人
- 株式会社(※株式譲渡制限付きに限る)
- 持分会社(合同会社・合資会社・合名会社)
特に株式会社の場合、「譲渡制限付き株式」であることが必須です。つまり、株式を他人に譲る際には会社の承認が必要である旨を、定款に定める必要があります(非公開会社)。
これは、農業に無関係な第三者が自由に株式を取得し、経営に影響を与えるリスクを防ぐための仕組みです。この要件があることで、次に解説する「議決権要件」の実効性も確保されます。
主たる事業は「農業」であること|事業要件
農地所有適格法人は、「主な事業が農業であること」が求められます。これが「事業要件」と呼ばれるもので、農地法第2条第3項第1号に明記されています。
✅ 判定基準
以下のいずれかの方法で、売上構成から主たる事業を判定します。
- 既存法人の場合:
直近3年間の売上実績に基づき、農業関連売上が総売上の過半数(50%超)を占めること。 - 新設法人の場合:
設立から3年間の営農計画(売上見込み)に基づいて判断されます。
✅ 「農業関連売上」とは?
農地法施行規則により、農業そのものだけでなく、次のような「関連事業」も農業売上に含めてよいとされています。
- 自社で生産した農産物の加工・製造・販売(例:自家製トマトでトマトジュースを作って販売)
- 農産物の貯蔵・運搬・販売
- 農業に必要な資材の製造・販売
- 農家レストラン・農家民宿など、農業と地域観光を融合させた事業
これは、6次産業化(生産×加工×販売)を推進する政策的な配慮によるもので、単なる農作業にとどまらない幅広いビジネス展開が認められています。
この「事業要件」を満たすためには、単に農業を行っているだけではなく、売上構成のバランス管理が必要です。特に複数事業を展開する法人では、計画段階から要件を意識した設計が重要になります。
経営の実権は農業関係者に|議決権要件
農地所有適格法人が農地を所有するには、その経営の実質的なコントロールが農業関係者にあることが必要です。これが「議決権要件」と呼ばれるもので、農地法第2条第3項第2号に規定されています。
✅ 要件の内容
農業関係者が法人の総議決権の過半数(1/2超)を保有していなければなりません。
これは、法人の意思決定が農業と無関係な第三者によって左右されることを防ぐための、極めて重要な制限です。たとえば、農業に興味を持つ企業や投資家が出資者となることは可能ですが、彼らの持つ議決権は過半数未満に抑える必要があります。
✅ 「農業関係者」とは?
法律上、「農業関係者」と認められるのは以下のような者に限られます。
| 区分 | 内容の概要 |
|---|---|
| 農地提供者 | 法人に農地を売却または賃貸した個人 |
| 常時従事者 | 法人の農業に年間150日以上従事している構成員(役員・従業員など) |
| 農作業委託者 | 自らの農地の管理を法人に委託している個人(例:高齢農家) |
| 農地中間管理機構 | 農地バンクを通じて農地を法人に貸し付けている機関 |
| 公的機関・農協等 | 地方公共団体、農業協同組合(JA)、農協連合会など |
このように「農業関係者」としてカウントできる構成員は限られており、単に出資しただけの個人や企業は該当しない点に注意が必要です。
✅ なぜこの要件が重要なのか?
議決権要件は、「誰が法人を動かしているのか」を法的に明確にするための仕組みです。名義上は農業法人でも、経営の実態が全く別の分野の出資者に握られていては、農地の本来の目的利用が損なわれるおそれがあります。
そのためこの要件は、制度の根幹である「耕作者主義」を法人にも徹底させる役割を担っているのです。
経営陣は農業の現場を理解しているか|役員要件
農地所有適格法人として認められるには、法人の役員が単なる名義上の経営者ではなく、農業の現場に実質的に関与していることが求められます。これが「役員要件」と呼ばれるもので、農地法第2条第3項第3号および第4号に規定されています。
この要件は、次の2つの条件を同時に満たす必要があります。
✅ 要件①:役員の過半数が「常時従事者」であること(第3号)
まず、法人の役員の過半数が、その法人の構成員(出資者など)であり、かつ農業に常時従事している者である必要があります。
用語メモ「常時従事」
年間150日以上、その法人の農業に関わる業務に従事していることを意味します。
- この「従事」には、圃場での作業だけでなく、経営計画の立案、販路の開拓、資材の調達、労務管理など、農業経営に不可欠な業務全般が含まれます。
この規定により、経営陣が農業から完全に遊離してしまうことを防ぎ、現場とのつながりを保つことが求められています。
✅ 要件②:役員等のうち1名以上が「農作業」に従事していること(第4号)
さらに、役員または法人の主要な使用人(農場長など)のうち、少なくとも1名は、年間60日以上、実際の農作業(フィールドワーク)に従事している必要があります。
この「農作業」は、耕起・播種・収穫などの現場作業そのものを意味し、経営的な業務とは明確に区別されます。
✅ なぜ2段階の要件があるのか?
このように、役員要件は「150日の常時従事」と「60日の農作業従事」という二重構造になっています。
- 経営者が農業の実態を理解したうえで戦略やマネジメントを行う。
- 同時に、少なくとも一人は実際に土に触れて農作業を行っている。
この制度設計により、たとえば「農業経験のある現場責任者」と「経営に強い代表者」が役割分担をしながら、法人全体としてバランスの取れた運営ができるよう配慮されています。
この役員要件は、農地法の理念である「耕作者主義」を法人経営の中にも浸透させるための重要な基盤となっています。
農地所有適格法人になることで得られる利点と生じる義務
農地所有適格法人としての資格を取得することは、法人にとって大きな転機となります。ここでは、その制度を活用することによって得られるメリット(利点)と、同時に負うことになるデメリット(義務やリスク)を整理して比較します。
これは、農業に本格的に参入する企業や、個人農業者が法人化を検討する際に、戦略的な意思決定を行う上で非常に重要なポイントです。
農地所有適格法人になることの主なメリット
✅ 1. 農地を「所有」できる安定性と資産価値
最大の利点は、法人が農地を「所有」できる点です。これにより次のような安定性が得られます。
- 契約更新のリスクがないため、長期的な投資(果樹園・ビニールハウス等)を安心して行える。
- 農地を法人の資産として計上でき、担保価値も認められる。
✅ 2. 社会的信用力の向上と資金調達の円滑化
法人格を持ち、農地所有適格法人として認定されていることで、以下のような信用が得られます。
- 金融機関や行政機関からの評価が向上し、補助金や融資制度の活用がしやすくなる。
- 地域との協働や取引先との信頼関係構築にもつながる。
✅ 3. 経営の近代化とガバナンスの強化
法人化によって個人の家計と事業資金が明確に分かれ、次のような効果があります。
- 財務管理・帳簿管理が正確になり、税務・会計の透明性が向上。
- 経営分析や戦略立案がしやすくなり、組織的な意思決定が可能に。
✅ 4. スムーズな事業承継が可能に
個人経営では相続のたびに農地の所有者変更が必要ですが、法人の場合は以下のような承継が可能です。
- 株式の譲渡により経営権を引き継げる。
- 農地所有に関する許可等の再取得が不要で、後継者問題への備えになる。
農地所有適格法人であることの主なデメリットと義務
⚠️ 1. 要件を「継続的に」満たす義務
農地所有適格法人の4要件(法人形態・事業・議決権・役員)は、一度満たせば終わりではなく、農地を所有し続ける限り維持しなければなりません。
- 売上構成や株主構成の変化
- 役員の交代や人事異動
といった変動にも対応し、適格性を保ち続ける必要があります。
⚠️ 2. 年次報告義務と罰則規定(農地法第6条・第68条)
毎事業年度終了後3か月以内に、農業委員会へ「農地所有適格法人報告書」を提出する義務があります。
- 虚偽報告・報告遅延には、30万円以下の過料が科される可能性あり(農地法第68条)。
⚠️ 3. 設立・維持にかかるコストと手間
法人の設立・運営には、以下のような負担がかかります。
- 会計帳簿の整備と税務申告の実施
- 定款変更・役員変更時の登記手続き
- 専門家への依頼や顧問契約に伴うコスト
⚠️ 4. 「借りる」という選択肢もある
実は、一般法人が農地を「賃借」して農業を行う道もあり、その場合は農地所有適格法人の要件を満たす必要はありません(農地法第3条の許可は必要)。
つまり、事業目的や経営戦略に応じて、
- 「農地を所有して長期安定を重視する」
- 「借地によって柔軟性を重視する」
という選択肢を比較検討することが重要です。
このように、農地所有適格法人はメリットの大きい制度である一方、重い法的責任と継続的な管理義務を伴います。慎重な準備と制度理解のもと、戦略的な判断が求められます。
農地所有適格法人となるための道筋 ― 設立から農地取得許可までの流れ
農地所有適格法人として農地を「所有」するには、単に法人を設立するだけでは不十分です。法人設立から農地法第3条の許可取得まで、段階的なプロセスを経る必要があります。
特に重要なのは、農業委員会との事前協議を軽視せず、初期段階から行政と連携を取りながら進めることです。
以下に、資格取得までの一般的な流れを5つのステップで整理します。
✅ ステップ1:事業計画の策定と農業委員会との事前協議
まず、農地の取得や法人設立の前に、営農計画書を作成し、農地所在地を管轄する農業委員会との事前相談を行います。
この段階で、以下のポイントについて行政側とすり合わせを行います。
- 法人の構成(株主や役員)が4要件を満たすかどうか
- 営農計画の現実性や地域との整合性
- 必要書類や今後の手続きの確認
事前協議は申請の可否を左右する重要なステップであり、安易に省略すべきではありません。
✅ ステップ2:法人の設立(定款設計と登記)
事前協議で前向きな見通しが得られたら、要件に適合した内容で法人を設立します。
- 株式会社の場合は、株式譲渡制限(非公開会社)の定款規定を必ず設ける必要があります。
- 合同会社や農事組合法人の場合も、それぞれの法的形式に応じた設計が求められます。
法人設立後は、登記簿謄本や定款の写しなど、後の許可申請に必要な書類を準備します。
✅ ステップ3:農地法第3条許可申請
法人が農地を取得するためには、農地法第3条の許可が必要です。
農業委員会へ以下の書類を添えて申請します。
- 営農計画書
- 定款、登記簿謄本、株主名簿
- 4つの要件を満たしていることを示す資料(議決権構成、役員の従事状況など)
この申請手続きが、事実上の「農地所有適格法人」としての適格性審査の場となります。
✅ ステップ4:許可の取得と農地の登記
審査の結果、農業委員会が適格性を認めれば、農地法第3条に基づく許可が下ります。
- 許可証の交付を受けてから、農地の売買・贈与契約を締結し、所有権移転登記を行います。
- この登記が完了した時点で、初めて法人は正式に「農地所有適格法人」となります。
✅ ステップ5:適格法人としての運用と報告義務の開始
農地の取得後は、以下のような継続的な義務が発生します。
- 毎年、農地所有適格法人報告書を提出(農地法第6条)
- 要件の維持(構成員・売上比率・役員体制等)
- 法人内部の変更があった場合の都度対応(定款変更、登記変更など)
この一連のプロセスを正しく踏むことで、法的に安定した農地所有が可能になります。反対に、手順を誤ると無効な登記・許可取り消しといった重大なリスクに直面することになります。
そのため、計画段階から行政との協議を大切にし、必要に応じて専門家の支援を受けながら進めることが、確実な資格取得への近道です。
要件を満たせなくなった場合 ― 資格喪失とその結末
農地所有適格法人のステータスは、取得すれば永続的に維持されるものではありません。農地法第2条第3項に定められた4つの要件のいずれかを満たせなくなった場合、その法人は「農地所有適格法人」としての資格を喪失します。
ここでは、資格を失った場合にどのような措置が取られるのか、段階ごとの流れを確認します。
要件未達時の対応①|資格の喪失と是正勧告(農地法第6条第2項)
農業委員会は、法人から毎年提出される「農地所有適格法人報告書」に基づいて、各要件の充足状況をチェックしています。
そして、以下のような状態が確認された場合は、法人に対して是正勧告を行うことができます。
- 農業関連売上が総売上の50%を下回った
- 株主構成が変化し、農業関係者の議決権割合が1/2以下になった
- 常時従事役員が過半数を下回った など
これは、農地法第6条第2項に基づく措置であり、法人が「要件を満たさなくなった」または「そのおそれがある」と判断された場合に、農業委員会が改善を促すための第一段階の警告として発出します。
勧告を受けた法人は、構成員の見直しや事業内容の再編といった具体的な対応を行い、要件の充足を図る必要があります。
要件未達時の対応②|農地の処分義務と最終的な国の買収(農地法第7条)
是正勧告にもかかわらず、法人が要件を回復できなかった場合には、より深刻な措置が講じられます。
✅ 農地の処分義務
農地法第7条に基づき、要件を欠いた法人は、すべての農地および採草放牧地を速やかに処分(売却等)しなければなりません。
- 処分にあたっては、農業委員会が譲渡先のあっせんなどを行います。
- ただし、法人が自発的に処分しない場合は、さらに厳しい措置が取られます。
✅ 最終措置:国による強制買収
法人が農地を処分しないまま放置した場合、農地法第7条により、国による強制的な買収が行われる可能性があります。
これは、農地法の根本理念である「耕作者主義」を守るための最後の手段であり、制度に違反した法人に対する法的制裁の意味合いを持ちます。
このように、農地所有適格法人制度は「取るのも維持するのも容易ではない」仕組みであり、その資格には継続的な法令遵守と組織体制の整備が不可欠です。
一時的な経営悪化などへの配慮はあるものの、改善の努力を怠れば、最終的には農地の所有権を剥奪されるという厳格な制度設計となっています。
まとめ
農地所有適格法人制度は、法人が農地を「所有」することを法的に認める、農地法上で唯一の制度です。
この制度を活用することで、農地を自社資産として保有でき、安定的かつ長期的な農業経営が可能になります。さらに、法人化による経営の近代化、事業承継の円滑化、金融機関や自治体からの信用力向上といった多くのメリットも得られます。
一方で、この制度の利用には、農地法第2条第3項で定められた4つの厳格な要件を継続的に満たすという、高いコンプライアンス体制が求められます。
- 会社の形態や定款の内容
- 売上構成や事業の実態
- 出資比率や議決権の構成
- 役員の農業従事状況
これらを常に適法に保ち続けなければ、資格喪失や農地の強制処分といった重大なリスクが発生します。
✅ 行政書士と連携することが成功への近道
農地所有適格法人の設立と運用には、法令理解・行政手続・経営設計の3つを横断する総合的な知識と経験が必要です。
特に、以下のような局面では行政書士などの専門家に相談することが、制度の適正な活用とリスク回避につながります。
- 設立前の事業構想段階での要件適合性の検討
- 株主構成・役員構成などの法的整理
- 農業委員会との事前協議、申請書類の作成
- 設立後の報告義務対応や体制の見直し支援
農業参入や法人化を考えるすべての方へ。
制度を正しく理解し、実情に合った活用方法を検討することが、長く続く経営の第一歩となります。