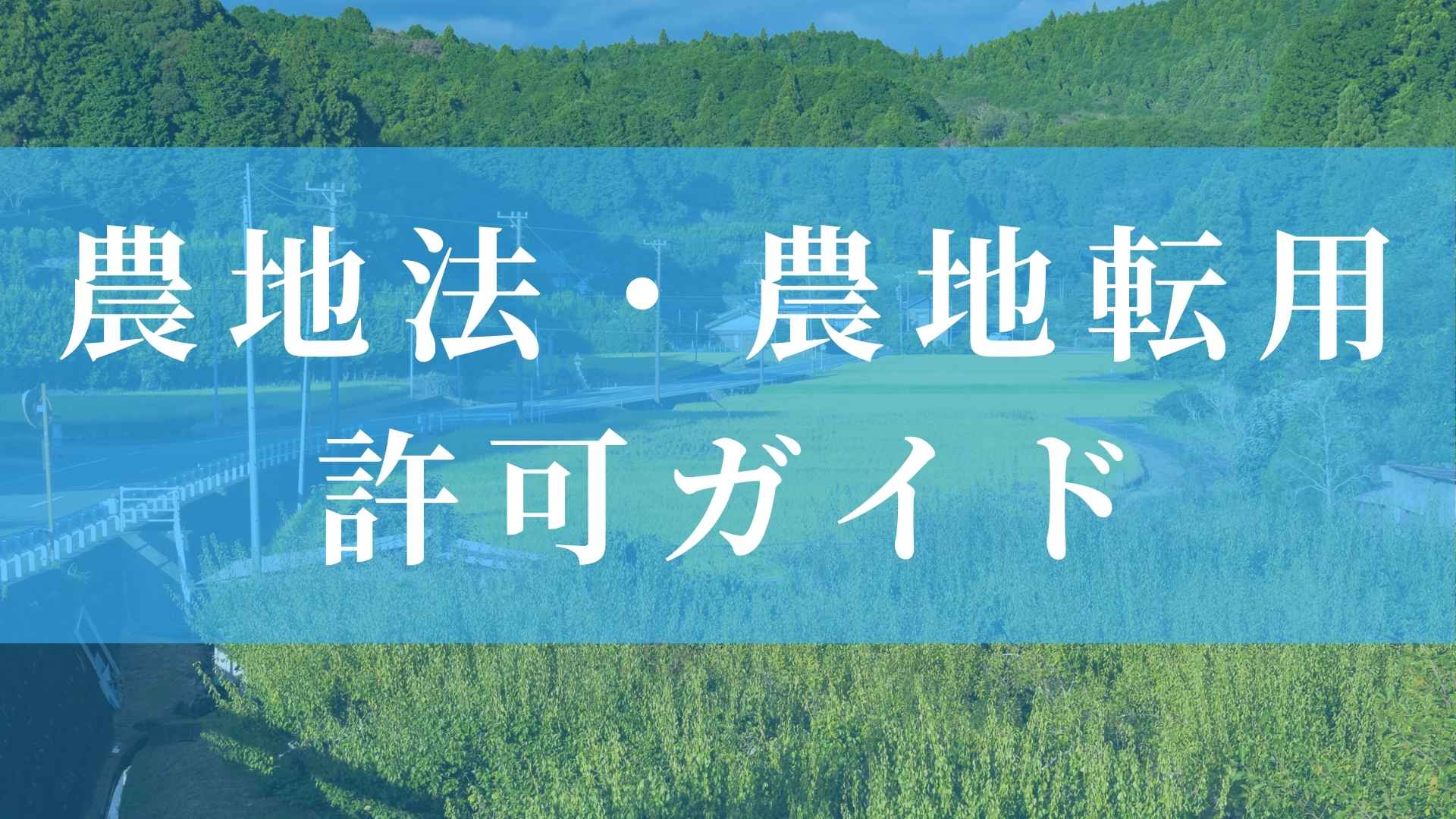こんにちは、行政書士の三澤です!
ご自宅やご実家に、市街地にある畑や田んぼ、あるいは家庭菜園の土地はありませんか?
「使い道がない」「固定資産税がかかるだけ」と感じて、放置されている方も多いかもしれません。
ですがその土地、実は大きなポテンシャルを秘めた「資産」かもしれません。
住宅を建てたり、駐車場・店舗として活用したり、売却したりすることで、価値を現実のものに変えることができます。
こうした活用を可能にするために必要なのが、「農地転用」という法的手続きです。
農地転用とは、その名の通り、農地を農地以外の用途(宅地・駐車場・資材置場など)で利用できるようにするための申請手続きのこと。これは、農地法という法律に基づいて厳格に管理されています。
そして、農地転用には大きく分けて2種類のルートがあります。
- 許可申請(市街化調整区域などで必要な、審査の厳しい手続き)
- 届出(市街化区域で認められる、比較的シンプルな手続き)
この記事では、市街化区域に農地をお持ちの方向けに、比較的手軽な「農地転用届出」について、行政書士の視点からわかりやすく解説していきます。
「許可との違いって何?」「手続きはどこに出せばいいの?」「どんな点に注意すべき?」といった疑問を、丁寧に解きほぐしながらお伝えします。
専門的な制度ではありますが、ポイントさえ押さえれば、農地は大きな可能性を秘めた資産となり得ます。
本記事が、あなたの土地活用の第一歩となれば幸いです。
第1章:なぜ市街化区域の農地は「届出」で済むのか?
1.1 農地法に基づく「届出」制度の仕組みとその目的
農地を宅地や駐車場など、農地以外の用途に転用する場合、通常は農地法に基づき「許可申請」が必要になります。
しかし、市街化区域にある農地については、例外的に「届出」だけで手続きが完了する制度が設けられています。これが、農地転用の「届出」制度です。
この制度の根拠は農地法に明確に定められており、手続きの種類によって適用条文が異なります:
- 自分の農地を自分で転用する(自己転用)場合:農地法第4条第1項第7号
- 他人に売却や賃貸したうえで転用する場合:農地法第5条第1項第6号
この「届出」制度の目的は、許可申請のように計画の妥当性を審査するものではなく、市街化区域内にある農地が今後転用されるという「事実」を、行政(主に市町村の農業委員会)が把握することにあります。
具体的には、
- 書類の形式が整っているか
- 対象地が確かに市街化区域にあるか
といった形式的なチェックが行われるだけであり、転用の内容そのものに対する審査は行われません。
つまり、「届出」とは、計画の可否を問うための手続きではなく、「転用します」という意思表示と報告を法的に整えるための手続きなのです。
1.2 なぜ「届出」で済むのか? そのカギを握るのは都市計画法
「市街化区域にある農地なら、なぜ許可ではなく届出だけでいいのか?」
この素朴な疑問に答えるには、農地法だけでなく、都市計画法というもう一つの重要な法律を理解する必要があります。
都市計画法では、日本全国の土地を大きく次の2つに区分しています:
- 市街化区域(しがいかくいき)
すでに市街地となっているか、今後10年以内に重点的に開発していくことが定められたエリアです。いわば「積極的にまちづくりを進める区域」です。 - 市街化調整区域(しがいかちょうせいくいき)
逆に、市街化を抑制し、農地や自然を保全していくエリア。原則として住宅や店舗などの建築・開発行為は制限されます。
この都市計画法の区域区分が、農地転用手続きの性質を大きく左右します。
国や自治体は、市街化区域については「ここはまちにしていく場所」と明確に位置づけており、その方針に基づいて都市インフラの整備や土地利用が進められます。
したがって、この区域にある農地について、農地法があまりに厳しい規制をかけてしまうと、国全体の土地政策と矛盾が生じてしまいます。
そのため、市街化区域では、農地法の規制が都市計画法の方針に配慮して一部緩和されているのです。
農地転用を妨げるのではなく、「届出」だけで円滑に転用できるようにしているのは、こうした法体系の整理の結果にほかなりません。
つまり、市街化区域で届出だけで済む理由は、単に手続きが簡略化されているからではなく、
「都市づくりの一環として、農地転用を促進する必要がある」という政策的背景があるからなのです。
この関係性を理解すれば、農地法と都市計画法という2つの制度がどのようにバランスを取って運用されているか、その全体像が見えてきます。
第2章:「届出」と「許可」はここが違う!農地転用における7つの重要な違い
農地転用「届出」と「許可」の違いを徹底比較
農地を転用する際、どの手続きを選ぶべきかは、その土地が属する区域によって異なります。
転用手続きには、大きく分けて以下の2種類があります:
- 「届出」制度:市街化区域内に限って認められる、比較的簡易な手続き
- 「許可申請」制度:市街化調整区域などで必要となる、厳格な審査付きの手続き
一見似たように見える「届出」と「許可」ですが、実際には目的も流れも難易度も大きく異なる手続きです。
以下の比較表で、それぞれの違いを整理しましょう。
| 比較項目 | 農地転用「届出」 | 農地転用「許可」 |
|---|---|---|
| 1. 対象区域 | 市街化区域 | 市街化調整区域など |
| 2. 手続き先 | 農業委員会(市町村) | 都道府県知事または指定市町村長(農業委員会経由) |
| 3. 手続きの性質 | 形式的審査(記載や添付書類の確認) | 実質的審査(計画内容の妥当性も評価) |
| 4. 審査基準 | 区域と書類の整合性のみ | 立地基準・一般基準による厳格な判断 |
| 5. 処理期間の目安 | 約1~2週間 | 約1ヶ月半~(案件により数ヶ月かかることも) |
| 6. 必要書類 | 比較的少ない(登記簿・公図など) | 多い(事業計画書・資金計画・排水計画など) |
| 7. 専門家の関与 | 自力も可能だが、確実性重視なら行政書士推奨 | 専門知識が必須。行政書士の関与がほぼ前提 |
1. 対象区域の違い
最大の違いは「その土地がどの区域にあるか」です。
市街化区域にある農地なら「届出」で済みますが、それ以外の区域(とくに市街化調整区域)では、原則として「許可」が必要です。
2. 手続き先の違い
「届出」は、農地のある市町村の農業委員会に直接書類を提出し、その場で完結します。
一方「許可」の場合は、農業委員会が意見を付して上位の行政庁(都道府県知事や政令市長など)に申請を送付し、そこで審査・判断されます。
3. 手続きの難易度
「届出」はあくまで形式的な審査であり、記載内容や添付書類が整っていれば基本的に受理されます。
しかし「許可」は、実質的な審査が入ります。計画の内容・妥当性・実行可能性などが厳しくチェックされるため、難易度は格段に高くなります。
4. 審査基準の違い
「届出」は、土地が市街化区域内であることと、書類の体裁が整っているかどうかが主な審査基準です。
「許可」では以下の2つの基準を満たす必要があります:
- 立地基準:優良農地の保護を目的とし、原則として第1種農地などの転用は不可
- 一般基準:資金調達・他法令の許認可・周辺農地への影響などを総合的に審査
5. 標準的な処理期間
「届出」は比較的スピーディーに処理され、通常1~2週間で「受理通知書」が交付されます。
一方「許可」は最低でも1ヶ月半程度、場合によってはさらに長期間かかることもあります。
6. 必要書類のボリューム
「届出」で求められるのは、登記事項証明書・公図・案内図など、比較的シンプルな書類です。
「許可」ではこれに加えて、事業計画書・資金計画・技術図面など多くの資料が必要になり、準備にも時間と労力がかかります。
7. 専門家の必要性
「届出」はある程度自力でも可能ですが、正確性や確実性を求めるなら行政書士に相談するのが安心です。
「許可」については、法的・実務的な難易度が非常に高いため、行政書士など専門家の関与が事実上不可欠と言えるでしょう。
「届出と許可、どう違うの?」という疑問は、農地転用の現場ではよく聞かれるテーマです。
この章を通じて、それぞれの制度の位置づけと違いをしっかり把握しておきましょう。
第3章:農地転用「届出」手続きの5ステップ
Step 1:最初にやるべきは「事前確認」と「相談」
農地転用の届出手続きで、いきなり書類を準備し始めるのは避けましょう。
まずやるべきは、その土地のある市町村の農業委員会へ事前相談に行くことです。
このステップを飛ばすと、あとで手戻りが発生し、余計な手間や時間がかかる可能性があります。
とくに確認すべきポイントは次のとおりです:
✅ 土地が「市街化区域」にあるかの再確認
届出制度が使えるのは、あくまで市街化区域内の農地に限られます。地番を伝えて、区域内かどうかを確実にチェックしてもらいましょう。
✅ 自治体独自の様式や必要書類の確認
市町村ごとに届出書の書式や添付書類、提出部数などに細かい違いがあります。ホームページで事前に調べるだけでなく、窓口で確認するのが確実です。
✅ 「土地改良区」の区域内かどうかの確認
一部の農地は「土地改良区」に含まれており、別途手続きや確認が必要になる場合があります。見落とされがちなので要注意です。
この事前相談を丁寧に行うことで、その後の書類作成や手続きがスムーズになります。
また、地域の実情や担当者の方針など、ネットでは得られない“生の情報”を得られるのも大きなメリットです。
農地転用届出の成功は、この最初の一歩にかかっていると言っても過言ではありません。
Step 2:必要書類をそろえて準備を整えよう
事前相談で必要書類が確認できたら、いよいよ収集と作成の段階に入ります。
「届出」で必要となる書類は、比較的シンプルですが、自治体によって微妙に異なるため、必ず確認しましょう。
主な必要書類は以下のとおりです:
- 農地転用届出書
市町村役場や公式ウェブサイトから入手できます。
※「第4条届出(自己転用)」と「第5条届出(売買・賃貸等を伴う転用)」で様式が異なります。 - 登記事項証明書(登記簿謄本)
法務局で取得。発行から3ヶ月以内のものが求められることが一般的です。 - 公図の写し
対象地の位置や範囲を示す地図。こちらも法務局で取得します。 - 案内図・位置図
住宅地図のコピー等で、対象地の場所に目印を付けたもの。 - 委任状
行政書士など代理人が手続きを行う場合に必要です。
書類が1枚足りないだけで受付不可となることもありますので、確実に揃えてから提出しましょう。
Step 3:農業委員会に届出書を提出する
必要書類がすべて揃ったら、いよいよ提出です。
提出先は、農地がある市町村の農業委員会事務局です。
届出の種類によって提出者が異なります:
- 第4条届出(自己転用)
⇒ 土地の所有者本人が提出 - 第5条届出(売買・賃貸等)
⇒ 現在の所有者(譲渡人・貸主)と、新たな利用者(譲受人・借主)の連名で提出が必要
記入漏れや添付書類の不備があると受理されないため、提出前に再度チェックしておくことが大切です。
Step 4:「受理通知書」の交付で法的手続きが成立
無事に書類が受理されると、農業委員会から「受理通知書」が交付されます。
これは「農地転用届出が正式に受け付けられた」ことを証明する重要な書類です。
交付までの期間は自治体によって異なりますが、通常は1~2週間程度が目安です。
この受理通知書が手元に届けば、農地法上の手続きは一区切りとなります。
ただし、ここで終わりではありません。次のステップが非常に重要です。
Step 5:【最重要】地目変更登記を忘れずに!
「受理通知書をもらったから、もう終わり」――そう考えてしまう方も多いのですが、実はここからが本当の最終ステップです。
地目変更登記を行わなければ、土地の用途が登記簿上は依然として「畑」や「田」のままです。
農地転用後、土地が実際に目的どおり(宅地・駐車場等)に利用できる状態になったら、
1ヶ月以内に法務局へ「地目変更登記」の申請を行う必要があります(不動産登記法の定めによる義務)。
そして、この登記申請は、土地家屋調査士の独占業務です。
行政書士では行えませんので、調査士との連携が欠かせません。
▼ このステップを怠るとどうなる?
- 地目が現況と合っていないため、売買や融資で支障が出る
- 法的義務違反として、過料の対象になる可能性がある
したがって、農地転用手続きは「行政書士による届出」と「土地家屋調査士による登記申請」のダブル連携が重要なのです。
この5つのステップを正しく踏めば、市街化区域の農地転用はスムーズに進みます。
次章では、実務で特に注意すべきポイントをさらに詳しく解説します。
第4章:【重要】農地転用「届出」で失敗しないために知っておくべき4つの注意点
注意点①:市街化区域でも「届出できない農地」がある
「市街化区域にあれば、届出で転用できる」──そう思っていませんか?
実は、市街化区域であっても、すべての農地が届出の対象になるわけではありません。
とくに注意すべきなのが、「生産緑地」に指定されている農地です。
🔍 生産緑地とは?
生産緑地とは、市街化区域内において、以下のような役割を果たす重要な農地です。
- 良好な都市環境の維持
- 災害時の避難スペースや緑地の確保
- 食料生産機能の保全
これらの目的から、「生産緑地法」に基づき、農地として長期にわたり保全すべき土地として市町村が指定しています。
✅ 生産緑地に指定されるとどうなる?
- 原則として、宅地や駐車場への転用はできません。
- 建物の建築や売却も制限されます。
- 税制面では優遇されるものの、農地としての維持管理が義務付けられます。
したがって、たとえ市街化区域にある農地でも、生産緑地に指定されていれば、「農地転用届出」では転用できないということになります。
❗ 指定解除には条件あり
生産緑地の指定を解除するには、以下のような厳格な条件を満たす必要があります:
- 所有者が高齢や病気などの理由で、農業を継続できなくなった場合
- 市町村に対して買い取り申し出を行い、一定期間内に対応がなかった場合
このプロセスを経なければ、届出も許可申請も受理されません。
📝 まずは「指定の有無」を必ず確認!
農地転用を検討される際は、その土地が生産緑地に指定されていないかどうかを、必ず市町村の農業委員会や都市計画課で確認してください。
「市街化区域だから大丈夫だろう」という思い込みは、大きな誤算につながります。
注意点②:無断で転用したらどうなる?— 違反転用の重大リスク
「届出は簡単そうだし、とりあえず先に工事を始めちゃおう」──
そんな考えは絶対に避けなければなりません。
農地転用の「届出」は、「受理通知書」が交付されて初めて法的に成立します。
つまり、それ以前に造成工事や駐車場運営などを始めてしまうと、「無断転用(違反転用)」という違法行為に該当します。
❌ 無断転用が発覚するとどうなる?
農地法に基づき、以下のような厳しい措置が科される可能性があります:
- 原状回復命令
工事の中止命令だけでなく、元の農地の状態に戻すことを行政から命じられます。 - 罰則規定
違反が悪質な場合には、次のような刑事罰が適用されることもあります: - 個人:3年以下の懲役 または 300万円以下の罰金
- 法人:1億円以下の罰金
「届出だから軽い手続き」と油断すると、取り返しのつかない損害を被る可能性があります。
工事・利用の開始は、必ず「受理通知書の交付後」に行うことが鉄則です。
注意点③:添付書類の「有効期限」や「正確性」に注意
農地転用の届出に添付する書類は、形式的な審査の対象となります。
つまり、記載漏れや期限切れの書類があると、それだけで不受理となる可能性があります。
✅ よくあるミス例
- 登記事項証明書(登記簿謄本)の有効期限切れ
多くの自治体では、「発行から3ヶ月以内」の書類を求めています。 - 相続登記が未了のまま
土地の所有者が亡くなっている場合、まずは相続登記を済ませなければ、届出は受理されません。
書類の正確性・最新性の確認は、ご自身で行う場合も、専門家に依頼する場合も、基本中の基本です。
注意点④:市町村によって「手続きの中身」が違う!?
農地法による基本的なルールは全国共通ですが、
実務上は、市町村ごとに運用方法が異なるケースが少なくありません。
🏙 よくある「ローカルルール」の違い
- 届出書の様式が独自のもの
- 添付書類に追加項目がある
- 提出部数や押印の要否に差がある
たとえば、A市では不要な書類が、B市では必須──というケースは珍しくありません。
📌 対応策は?
- Step1で紹介した「事前相談」を丁寧に行うこと
- 地域に精通した行政書士に依頼すること
地域の行政慣行や窓口対応を熟知している専門家に依頼することで、
こうした“地味だけど重要な違い”にスムーズに対応でき、手続きが確実・迅速に進みます。
まとめ:農地転用は行政書士とともに確実な手続きを
ここまで、市街化区域にある農地の「届出」制度について、
その制度の背景・具体的な手続き・注意点に至るまで、網羅的に解説してきました。
✅ 本記事のまとめ
- 市街化区域にある農地は、比較的簡易な「届出」手続きによって転用が可能です。
- ただし、「簡単=任意」ではありません。届出は法律で定められた義務的手続きです。
- 「生産緑地」など例外となるケースや、地目変更登記といった見落とされがちな後続手続きにも注意が必要です。
農地転用は、長年活用されていなかった土地に新たな価値を与える機会となります。
住宅建築・駐車場経営・事業活用・売却など、将来にわたる可能性が広がる一方で、
農地法を中心とする法的ルールに従った慎重な対応が求められる分野でもあります。
💡 行政書士の活用で、安心と確実性を
農地転用の届出は、ご自身でも可能ですが、
- 書類の正確性
- 自治体ごとのローカルルールへの対応
- 地目変更登記への引継ぎ(※土地家屋調査士との連携)
といった実務上のポイントを考慮すると、行政書士によるサポートを活用することが非常に効果的です。
我々行政書士は、
- 届出書類の作成
- 窓口対応の代行
- 土地家屋調査士との連携によるワンストップ支援
を通じて、皆さまの大切な土地の価値を、安心・確実に活用するお手伝いをしています。