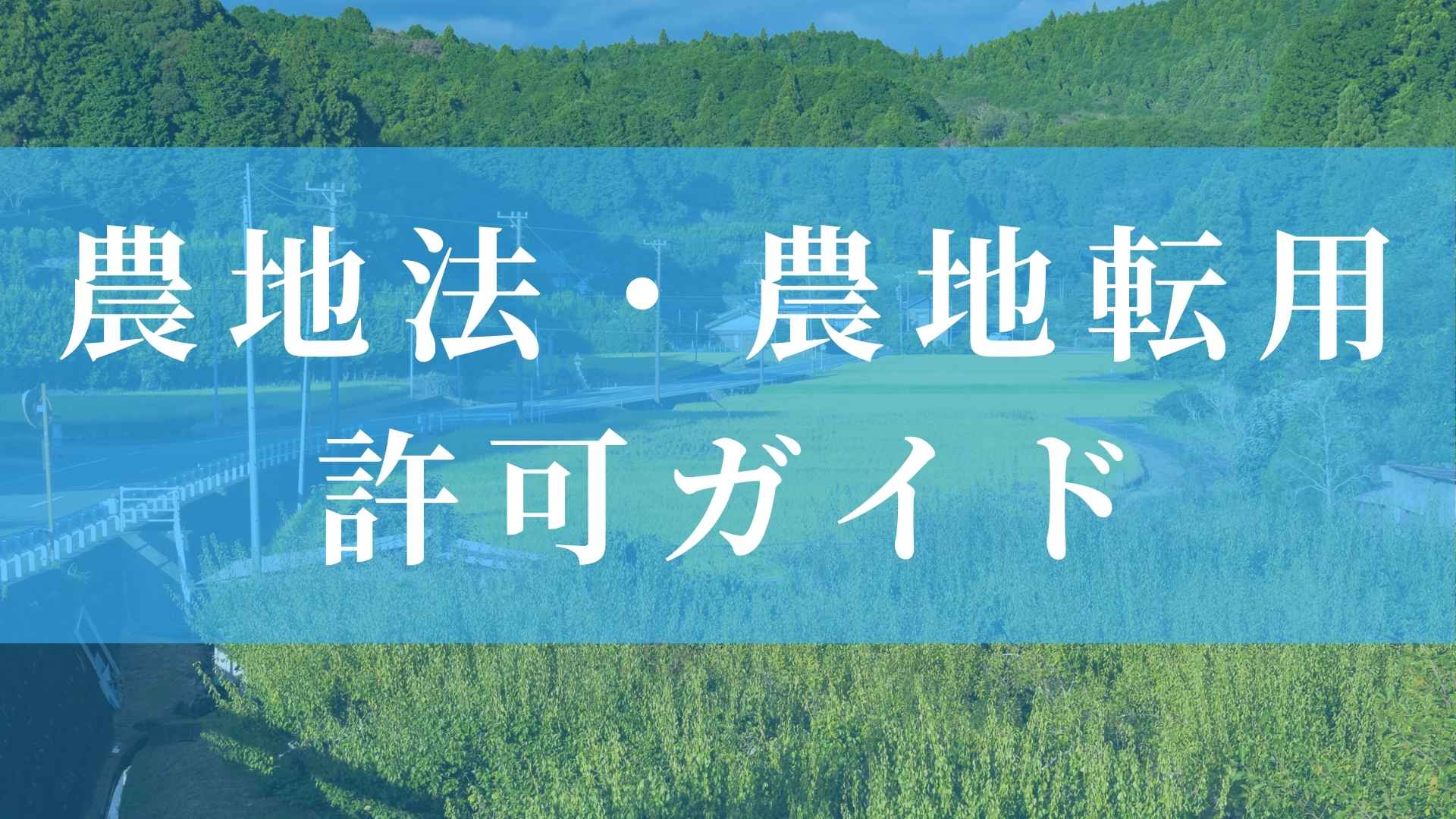こんにちは、行政書士の三澤です!
「親から田んぼを相続したけれど、自分では使い道がなくて困っている」
「今は使っていない畑に、自宅を建てたい」
「空いた農地を駐車場や資材置場にして、有効活用したい」
こんなお悩みやご希望をお持ちではないでしょうか?
せっかく所有している土地なのに、建物を建てたり貸し出したりといった活用ができず、もどかしい思いをされている方は少なくありません。
その理由の多くは、土地が「農地」として登記・登録されており、「農地法」という法律によって、用途が厳しく制限されていることにあります。
ですが――農地だからといって、活用をあきらめる必要はありません。
もちろんすべてが可能なわけではありませんが、条件を満たしている土地で適切な手続きを行えば、その農地を宅地や駐車場、店舗や太陽光発電用地といった“使える土地”に生まれ変わらせることが可能です。
そのカギとなるのが、「農地転用(のうちてんよう)」という制度です。
本記事では、行政書士として多数の農地転用手続きを実務で扱ってきた経験をもとに、はじめての方にもわかりやすく、
- 農地転用の基本的な考え方
- 手続きの流れ
- かかる費用や期間
などを丁寧に解説していきます。
読み終える頃には、ご自身の土地の可能性が見え、次の一歩を安心して踏み出せるはずです。
そもそも農地転用ってなに?──ひとことで言うと・・・
まずは、答えをシンプルに知りたい方のために、結論からお伝えします。
農地転用とは、「農地を、農地以外の目的で使うための法的な手続き」のことです。
たとえば、田んぼや畑を――
- 自宅を建てるための宅地にしたい
- 月極駐車場として使いたい
- 資材置場や店舗、工場にしたい
- 太陽光発電の用地として活用したい
といったように、農業以外の目的で使いたい場合には、たとえ土地の見た目が変わらなくても、農地転用の手続きが必ず必要です。
では、なぜそんな手続きが必要なのか?
それは、日本にとって農地がとても貴重であり、国の食料を安定的に確保するために保護されているからです。
実際、日本の食料自給率はカロリーベースで約38%と、先進国の中でもかなり低い水準です。
誰もが自由に農地を宅地や駐車場に変えられるようになってしまえば、将来、食べ物を安定して得ることがますます難しくなってしまいます。
そのため、国は「農地法」という法律で農地を守りつつ、
一方で「活用したい」という土地所有者の権利とのバランスを取るしくみとして、農地転用制度を設けているのです。
農地転用とはいわば、単なる申請ではなく、こうした社会全体の利益と個人の活用希望をつなぐ“対話のルール”でもあるのです。
どうして自由に使えないの?──農地転用が必要な理由とは
「自分の土地なんだから、好きなように使わせてほしい」
そう思うのは、土地を所有していればごく自然な感覚です。
ですが、農地は“個人の財産”であると同時に、“社会全体の食料を支える大切な資源”でもあります。
そのため、農地の使い方には「農地法」という法律によって厳格なルールが設けられており、勝手に宅地や駐車場に変えることはできません。
この法律の目的は、限られた農地を守り、日本の食料生産を安定させること。
無秩序な転用を防ぎ、将来世代にも農業の土台を残していくことが重視されているのです。
無断転用には厳しい罰則が
「見つからなければ大丈夫だろう」と思って勝手に転用してしまうと、重大な法令違反となり、次のような厳しい処分が科されます。
- 工事の中止命令・原状回復命令
→ 建物や構造物をすべて撤去し、元の農地に戻すよう命じられます(費用は自己負担)。 - 刑事罰の対象に
→ 命令に従わなければ、個人で「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」、法人であれば「1億円以下の罰金」となります。
さらに、農業委員会はドローンなどを活用して定期的にパトロールを行っており、近隣住民からの通報や土地売却時の調査でも違反が発覚するケースが少なくありません。
許可を後から取るのは、ほぼ不可能
違反が発覚した後で「事後的に許可を取ればいい」と思う方もいらっしゃいますが、現実にはほとんどの場合、追認的な許可は認められません。
法令に則った正規の手続きを踏むことが、
- トラブルを防ぐ
- 時間とお金のロスを避ける
- 将来も安心して土地を使える
という意味でも、最も確実で安全な道なのです。
農地転用の基本を押さえよう──「農地法3条・4条・5条」の違いをやさしく解説
農地転用の手続きを考えるうえで、絶対に知っておきたいのが
農地法の3つの条文――第3条・第4条・第5条の違いです。
法律というと難しく聞こえるかもしれませんが、
それぞれの条文は「誰が、何のために、どう使うか」という視点で整理すれば、とてもシンプルに理解できます。
以下に3つの条文の違いを表にまとめました。
| 条文 | どういう手続き? | 誰が申請する? | 土地の用途は? | 具体例 |
|---|---|---|---|---|
| 第3条 | 農地を農地のまま売買・貸す | 譲る人(売主)と受け取る人(買主) | 農地のまま使う | Aさんの畑を、農業を続けるBさんが買う。 |
| 第4条 | 自分の農地を自分で転用 | 土地の所有者本人 | 農地 → 宅地などに変える | 自分の畑に、自宅や駐車場をつくる。 |
| 第5条 | 農地を他人に売って転用する | 譲る人と受け取る人(共同申請) | 農地 → 宅地などに変える | Aさんの畑を、住宅を建てたいBさんが購入する。 |
それぞれのポイントをやさしく解説
◉ 第3条:「農地のまま別の人へ譲り渡す」場合の手続き
- 目的:農業を続ける人に、農地を売ったり貸したりするための許可
- ポイント:使い道は“農地のまま”。転用ではないが、農地に関わる重要な申請
- 実務の注意点:農業を継続する意思や計画が問われる(営農計画や労働力の有無など)
◉ 第4条:「自分の農地を、自分が所有者のまま転用」する場合の手続き
- 目的:畑を宅地にして、自宅や資材置場に使いたいときなど
- ポイント:所有者は変わらない。用途だけが農地→非農地へ
- 実務の注意点:計画の具体性や資金の裏付けが求められる(特に事業目的の転用時)
◉ 第5条:「農地を他人に譲り、さらに転用もする」場合の手続き
- 目的:第三者が農地を取得して、家や店舗、太陽光発電所などをつくるとき
- ポイント:3条と4条の“合わせ技”であり、最も一般的な転用ケース
- 実務の注意点:「親の農地に子どもが家を建てる」というケースでも、親子間の名義変更があればこの5条になります
これらの違いを理解しておくと、スムーズな申請準備ができるだけでなく、
誤った条文で手続きを進めてしまうリスクを防ぐことができます。
迷ったときは、どの条文が当てはまるかを専門家に確認するのが安心です。
農地転用できるかどうかは“場所”で決まる──まずは立地条件をチェック!
農地を転用できるかどうかは、「どんな計画か?」よりも、
「その農地が、どこにあるか?」が最も重要な判断ポイントです。
つまり、どれだけ立派な計画でも、立地によっては最初から転用が認められないケースもあるということです。
ここでは、農地転用の可否を大きく左右する「2つの立地チェックポイント」を解説します。
チェック①:都市計画上のエリア分け ― 「市街化区域」か「市街化調整区域」か
まずは、あなたの農地が都市計画法上でどのエリアにあるのかを確認しましょう。
ここが、農地転用の「難易度」を大きく左右する第一関門です。
■ 市街化区域(しがいかくいき)
- どんなエリア?
→ すでに街として整備されているか、今後10年以内に市街化を進めるとされている地域。 - 転用のしやすさ:★★★★★(最も易しい)
→ 原則として許可不要で、農業委員会への届出のみでOK。 - 期間の目安
→ 書類に不備がなければ、1〜2週間程度で完了することも。
■ 市街化調整区域(しがいかちょうせいくいき)
- どんなエリア?
→ 開発を抑えて自然や農地を守るべき地域。新たな建築は原則NG。 - 転用のしやすさ:★☆☆☆☆(かなり厳しい)
→ 都道府県知事(または市町村長)の許可が必要。厳しい審査が行われます。 - 期間の目安
→ 申請から許可まで、2〜3ヶ月以上かかるのが一般的。
✅ エリアの確認は、市町村の都市計画課や各市町村のホームページ等で調べることができます。
チェック②:農地のランク ―「農地区分」によって許可の難易度が変わる
とくに「市街化調整区域」にある農地は、その農地区分(等級)によって、転用の可否がほぼ決まります。
| 区分 | 通称 | 転用の難易度 | 特徴とポイント |
|---|---|---|---|
| 農用地区域内農地 | 青地 | ★☆☆☆☆(原則NG) | 農地の“保護区”。除外申請から必要。 |
| 甲種農地 | ― | ★☆☆☆☆(原則NG) | 大規模で優良な農地。公共事業以外NG。 |
| 第1種農地 | ― | ★★☆☆☆(原則NG) | 比較的良好な農地。例外を除きNG。 |
| 第2種農地 | ― | ★★★☆☆(条件付き) | 周辺状況によっては許可の可能性あり。 |
| 第3種農地 | ― | ★★★★★(許可されやすい) | 市街地化が進んでいる農地。原則として許可。 |
✅ 同じ「農地」でも、区分によって天と地ほどの違いがあります。
行政書士などの専門家に相談すれば、あなたの土地がどの区分に該当するかを早期に確認できます。
✅ 立地次第で結果が変わる
農地転用ができるかどうかは、
どうしたいかよりも、どんな立地にあるかです。
まずは、あなたの土地の
- 都市計画エリア(市街化区域 or 調整区域)
- 農地区分(第○種農地など)
を確認することから始めましょう。
不安な方は、地元で農地転用を扱う行政書士事務所などに相談すると、無駄なく進められます。
農地転用って何から始めればいい?──申請から許可までの7ステップ
農地転用は、「申請書を出せば終わり」ではありません。
実際には、事前相談から書類作成・審査・許可まで、いくつかの段階を踏んで進んでいきます。
ここでは、市街化調整区域での“許可申請”の場合を前提に、標準的な流れを7つのステップに分けて解説します。
ステップ①|事前相談(農業委員会・行政書士)
まずは、農地がある市町村の農業委員会へ相談に行きましょう。
この時点で、行政書士にも相談しておくとスムーズです。
- 立地条件(農地区分・都市計画)
- 関連法令(開発許可、農振除外など)
- 申請の可否や進め方
といった点を確認します。
✅ 農地転用を扱う行政書士事務所なら、ここで将来的なリスクや最適な申請時期も見極めてくれます。
ステップ②|必要書類の収集
転用申請には、多くの書類が必要です。
書類の一例:
- 申請書(様式あり)
- 登記事項証明書、公図
- 位置図・案内図
- 土地利用計画図・建物の図面
- 事業計画書(目的・内容)
- 資金計画資料(残高証明や融資証明など)
- 関係者の同意書(隣地所有者、水利組合など)
✅ 書類が揃っていないと、受付すらしてもらえない自治体もあります。
ステップ③|申請書類の作成・提出
集めた資料をもとに、法律に則った形で正式な申請書を作成します。
行政書士が代理作成し、申請者名義で農業委員会に提出します。
⏰ 多くの市町村では「毎月○日締切」という受付期限が決まっており、
1日遅れると審査が翌月にずれ込みます。
ステップ④|農業委員会による審査・現地調査・総会
農業委員会の職員が、書類審査と現地確認を行い、
その後「総会(毎月1回)」で審議されます。
- 転用計画の妥当性
- 周辺農地への影響
- 排水や土砂流出対策の有無 などが審査されます。
ステップ⑤|都道府県知事(または市町村長)への進達
農業委員会が「許可すべき」と判断した案件については、
意見書を添えて、都道府県知事(または移譲された市町村長)に送付されます。
ステップ⑥|許可 or 不許可の決定
都道府県の担当部局で最終審査が行われ、
すべての条件をクリアしていれば正式に許可が下ります。
✅ 法的な条件を満たしていても、説明不足や図面の不備で差し戻されるケースもあります。
ステップ⑦|許可証の交付 → 転用スタート!
無事に許可が下りたら、「農地転用許可証」が交付されます。
この許可証が交付されてはじめて、工事や土地利用の変更が可能になります。
スムーズな手続きのカギは“準備と専門知識”
農地転用は、役所との折衝・多岐にわたる書類対応・スケジュール管理が重要です。
慣れていないと、思わぬところで手続きがストップすることも。
「何から始めるべきか」迷ったら、まずは行政書士に相談するのが一番の近道です。
気になる費用と期間の目安──農地転用にかかるお金と時間を事前に把握!
「農地転用って、結局いくらかかるの?」
「どのくらい時間がかかるの?」
こうした疑問は、多くの方が最初に抱えるポイントです。
ここでは、農地転用の実務経験に基づいた費用と期間の現実的な目安をお伝えします。
🔹 費用の内訳と目安
農地転用にかかる費用は、主に次の2つに分かれます。
① 専門家への報酬(行政書士費用)
| 手続きの種類 | 費用の目安 | 特徴・補足 |
|---|---|---|
| 届出(市街化区域) | 約5万円~ | 書類作成のみで済むため比較的安価 |
| 許可申請(調整区域) | 約15万円~ | 難易度や面積、関係手続きの有無で変動 |
✅ 農振除外や開発許可などの追加手続きがあると、さらに費用がかかる場合があります。
② 実費(役所・登記などに支払う費用)
| 項目 | 費用の目安 | 補足内容 |
|---|---|---|
| 各種証明書類の取得費用 | 数千円〜1万円程度 | 登記事項証明書、公図、住民票など |
| 地目変更の登記報酬 | 約5万円~ | 土地家屋調査士へ依頼する場合 |
| 登録免許税 | 通常は不要 | ※所有権移転などがある場合は別途必要 |
| その他 | 事案による | 測量費・土地改良区への決済金など |
✅ 「家を建てる」など実際の造成工事費(整地・擁壁など)は別途かかり、数十万〜数百万円になることもあります。
🔹 手続きにかかる期間の目安
手続きの種類によって、かかる期間も大きく異なります。
■ 市街化区域での「届出」の場合
- 農業委員会への提出から1〜2週間程度
- 書類の準備も含めれば、全体で1ヶ月前後で完了するケースが多いです。
■ 市街化調整区域での「許可申請」の場合
- 農業委員会の総会(毎月1回)→ 都道府県知事等の審査
- 標準的には、2〜3ヶ月程度が目安です。
⏳ 注意:農振除外などの事前手続きが必要な場合、半年〜1年以上かかることもあります。
✅ 金額も時間も「条件次第」
農地転用にかかる費用と期間は、
- 土地の場所(市街化区域 or 調整区域)
- 転用の目的や規模
- 必要となる関係手続きの数
によって大きく変わってきます。
「このくらいかかるだろう」と自己判断するのではなく、早めに行政書士へ相談し、事前に見積もりとスケジュールを立てることが成功のカギです。
よくあるご質問とその答え──農地転用で皆さまから寄せられる疑問にお答えします
農地転用を検討される方から、よくいただくご質問とその回答をQ&A形式でまとめました。
「自分も同じことで悩んでいた!」という内容がきっと見つかるはずです。
❓ 相続した農地でも、すぐに転用できますか?
A:いいえ、いくつかの前提条件を満たす必要があります。
相続登記が未了でも申請は可能ですが、
- 相続人全員による「遺産分割協議書」がまとまっていること
- 農業委員会へ相続届(農地法第3条の3)を10ヶ月以内に提出していること
などが求められます。
スムーズに進めるためには、先に相続登記を済ませておくのが理想的です。
❓ 家庭菜園にしたい場合も、農地転用の手続きは必要ですか?
A:小規模な家庭菜園なら、通常は不要です。
ご自宅の庭の一部で行う程度の「家庭菜園」であれば、農地法の対象とはされません。
❓ 太陽光発電パネルを設置するには、転用が必要ですか?
A:はい、農地転用の手続きが必要です。
- 恒久的に使う場合:雑種地などへ地目変更する「恒久転用」が必要
- 営農を続ける場合:営農型太陽光発電(ソーラーシェアリング)として「一時転用」が必要
一時転用では、定期的な更新や営農の継続が条件になります。
❓ どんな場合に「転用許可が下りない」のでしょうか?
A:主に次のようなケースで不許可となることがあります。
- 立地に問題がある(青地や第1種農地など原則転用不可の土地)
- 計画の具体性に欠ける(資金計画が曖昧、書類不備など)
- 周辺農地に悪影響が出るおそれがある(排水先が確保されていない、土砂流出の懸念など)
事前の立地確認と計画の精度が、許可取得の大きなカギを握ります。
❓ 手続きは自分でもできますか?
A:可能ですが、現実的には専門家に依頼するのが安心です。
農地転用は、農地法に加え都市計画法や農振法など複数の法律が絡む複雑な手続きです。
また、書類作成や役所とのやり取りに慣れていないと、思わぬミスで大幅に時間をロスすることも。
✅ 申請締切(月1回)を逃すと、1ヶ月単位でスケジュールが後ろ倒しになります。
✅ 行政書士に依頼すれば、確実性・スピード・安心感の面で大きなメリットがあります。
✅ ご不明な点はお気軽にご相談ください!
本記事で解消しきれない疑問がある場合は、お気軽にお問い合わせください。
三澤行政書士事務所は愛知県知多半島(知多郡、半田市、常滑市、東海市、知多市、大府市)を中心に、農地転用を取り扱う行政書士事務所です。
まとめ:農地転用で失敗しないために──最初の一歩は専門家への相談から
ここまで、農地転用についての基本知識から手続きの流れ、費用、よくある疑問までを解説してきました。
最後に、重要なポイントをもう一度整理しておきましょう。
✅ 農地転用のポイントまとめ
- 農地転用とは:農地を住宅や駐車場など「農業以外の目的」で使うための法的手続き
- 手続きの要否は立地で決まる:市街化区域なら届出、市街化調整区域なら許可が必要
- 許可が下りるかは“農地区分”次第:立地条件により、転用の可否がほぼ決まる
- 無断転用は厳禁:違反には高額な罰金や原状回復命令などのリスクがある
- 正しい手続きを踏むことが、最も安全で確実な近道
✅ 自分で手続きできる?→ 現実はなかなか大変です
法律や制度に詳しくない状態で、自分ひとりで手続きを進めるのはハードルが高く、
- 書類の不備で申請が通らない
- 審査が遅れて計画がずれ込む
- そもそも申請方法を間違えている
といったトラブルも少なくありません。
💡 農地転用案件は、早い段階で専門家の関与が成否を左右します。
✅ 行政書士に相談すれば、時間・コスト・安心感が手に入る
行政書士は、農地転用に関する書類作成や申請代行だけでなく、
- 計画の実現可能性の診断
- 関係法令の確認
- 各役所とのやり取り代行
など、全体のプロセスをサポートできます。
🌱「この土地、どうにか活かしたい」──その想い、私たちが全力で支えます
- 「相続したけど使い道がない」
- 「建てたい家があるけど進め方がわからない」
- 「いくらかかるかだけでも知りたい」
そんなお悩みをお持ちの方は、まずはお気軽にご相談ください。
当事務所では、これまで多くの複雑な農地転用をサポートしてきました。
あなたの土地の可能性を、安心・確実にカタチにするお手伝いをいたします。