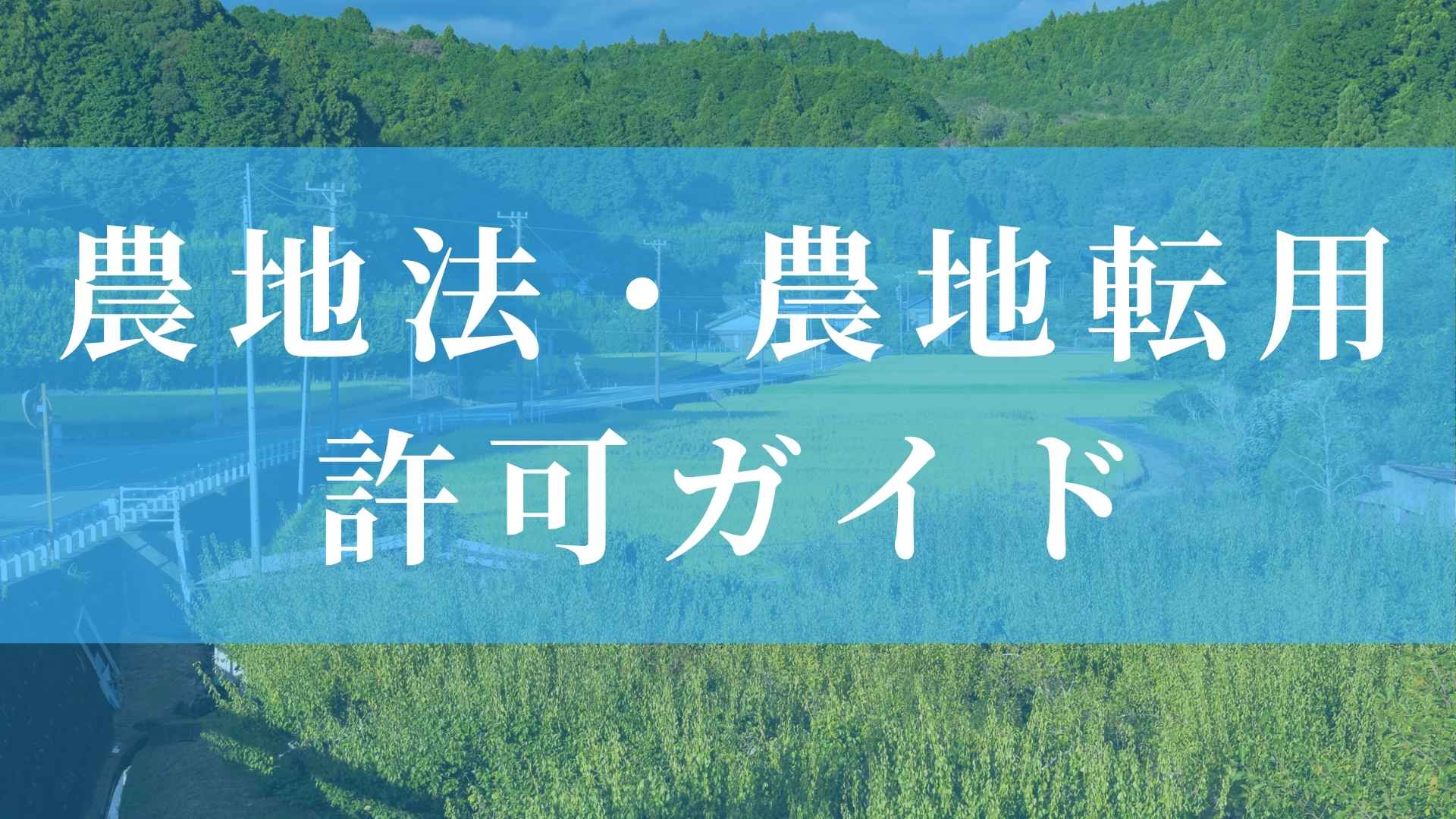こんにちは、行政書士の三澤です!
「親の畑を相続したけど、家を建ててもいいの?」「使っていない農地を誰かに貸したいけど、どうしたらいいんだろう?」
そんなふうに農地の活用を考え始めたとき、必ずと言っていいほど出てくるのが「農地法3条・4条・5条」という言葉です。でも、数字だけが並んでいて、何がどう違うのか…正直よく分からない、という方も多いのではないでしょうか。
ご安心ください。この記事では、行政書士が専門家の視点から、農地法3条・4条・5条の違いを図解でやさしく解説します。
結論からお伝えすると、この3つの条文の違いは、たった2つのポイントに集約されます。
- 「人が変わるかどうか」
- 「土地の使い方が変わるかどうか」
これだけで判断できるんです。
✅ 農地法3条:農地のまま、持ち主(または使う人)が変わる
✅ 農地法4条:持ち主はそのまま、農地の使い方を変える(例:宅地に)
✅ 農地法5条:農地を売ったり貸したりして、かつ使い方も変える(両方変わる)
この3パターンさえ押さえれば、「うちはどの条文にあてはまるのか?」という疑問が、すぐにクリアになります。
それでは早速、図を使って、3条・4条・5条の関係性を一緒に見ていきましょう。
農地法3条・4条・5条の違いと関係性
言葉だけの説明ではイメージしづらい…そんな方のために、まずは図を使って全体像を確認しましょう。
この図では、「人が変わるのか?」「土地の用途が変わるのか?」という2つの視点で、農地法3条・4条・5条の関係性を整理しています。
- 3条:農地のまま、名義(所有者や利用者)が変わる
- 4条:所有者は変わらず、農地の用途(目的)を変える
- 5条:名義も用途も両方変わる
つまり、5条は3条と4条の要素が合わさった複合パターンなのです。
ポイントは以下の2点です。
✅ 「権利の移動(人が変わる)」=3条・5条に該当
✅ 「用途の変更(農地以外に変える)」=4条・5条に該当
5条が「人も変わり、土地の用途も変わる」ケースだと押さえると、3条・4条との違いが自然と見えてきます。
【比較表で整理】農地法3条・4条・5条のちがいをまとめて確認!
図で全体像がつかめたら、次はそれぞれの条文を具体的に比較してみましょう。
農地法3条・4条・5条は、「どんな目的で」「誰が関わり」「誰に許可をもらうのか」によって手続きが分かれます。以下の表で、その違いが一目でわかります。
| 項目 | 農地法第3条 | 農地法第4条 | 農地法第5条 |
|---|---|---|---|
| 目的 | 権利の移動(人が変わる) | 転用(使い方が変わる) | 転用を目的とした権利の移動(両方変わる) |
| キャッチフレーズ | 農地のまま、人が変わる | 人は同じ、土地が変わる | 人も土地も、両方変わる |
| 当事者 | 売主・貸主 ↔ 買主・借主 | 所有者のみ | 売主・貸主 ↔ 買主・借主 |
| 許可権者 | 農業委員会 | 都道府県知事(または指定市町村) | 都道府県知事(または指定市町村) |
| 具体例 | 農家Aが新規就農者Bに畑を売る | Aさんが自分の畑に家を建てる | BさんがAさんから畑を買って宅地にする |
| 無許可の場合 | 契約が無効になる | 原状回復命令の対象になる | 契約が無効+原状回復命令の対象になる |
このように、それぞれの条文は「目的」と「関係者」によって明確に分かれています。
特に注目すべきは、許可を出す行政機関の違いと、無許可で行った場合のリスクです。
なかでも5条は、最も厳しいリスクが伴うため、慎重な対応が求められます。
農地法3条・4条・5条の内容を具体例つきで解説
ここからは、それぞれの条文について、もう少し踏み込んで見ていきましょう。
実際のケースに照らして解説するので、「自分のケースはどれに当てはまるのか?」を判断するヒントになるはずです。
🟢 農地法第3条とは?
=農地のまま、名義(権利)が変わるケース
目的: 農地の売買・贈与・賃貸借などで、所有者や使用者を変更する場合に適用されます。ただし、土地の使い方は「農地のまま」です。
許可権者: 農地がある市町村の農業委員会
具体例:
リタイアする農家のAさんが、新規就農希望者Bさんに畑を売却し、Bさんがそのまま農業を続ける場合。
✅ 補足:2023年の法改正ポイント
以前は「下限面積要件(例:50アール以上)」が必要でしたが、2023年4月の改正により廃止されました。
今は、面積の大小にかかわらず、以下の要件を満たせば許可が得られます:
- 取得した農地をすべて効率的に活用すること(全部効率利用要件)
- 必要な農作業に常時従事すること
- 周辺農地の利用を妨げないこと
🟡 農地法第4条とは?
=持ち主は同じで、農地の使い方を変えるケース(自己転用)
目的: 所有している農地を、宅地・駐車場・資材置場などに用途変更(転用)する場合。
許可権者: 原則として都道府県知事(または指定市町村長)
具体例:
親から相続した畑を所有するAさんが、その一部を整地して、自宅を建てる場合。
✅ 専門的なポイント
- 第4条は「農地」のみが対象
- 採草放牧地の自己転用には適用されません(3条・5条は農地+採草放牧地を対象)
🟠 農地法第5条とは?
=農地を売ったり貸したりし、かつ用途も変えるケース(人も土地も変わる)
目的: 転用を目的とした売買・貸借などによる権利移動。
実務では最も多く見られるパターンです。
許可権者: 原則として都道府県知事(または指定市町村長)
具体例:
サラリーマンのBさんが、農家のAさんから農地を購入し、自宅を建てるケース。
または、不動産会社が農地を買って分譲住宅を建てるケースも該当します。
🔺 よくある誤解:「親の農地に子どもが家を建てる」は何条?
これも典型的な質問です。
「親名義の農地に、子どもが家を建てたい」というケースは、第5条に該当します。
たとえ親子間であっても、法律上は別人格。使用権の移転(使用貸借や贈与)+転用が発生するためです。
➡ ポイント:親族間でも、”人が変わる+使い方が変わる”なら第5条
【ケース別チェック】あなたのケースは農地法3条・4条・5条のどれ?
ここまでで、農地法の3つの条文(3条・4条・5条)の違いはある程度つかめたと思います。
でも「自分のケースがどれに当てはまるのか?」となると、やっぱり迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。
そんなときは、以下のQ&Aで判断してみてください。
身近な事例をもとに、どの条文に該当するかをわかりやすく整理しています。
❓ Q1. 農業を始めるために、地主さんから畑を買いたい
▶️ 答え:農地法第3条
- 土地はそのまま「農地」として使う
- 所有者が変わる(権利移動が発生)
- → だから「第3条許可」が必要です
❓ Q2. 相続した畑に、自分の家を建てたい(所有者は自分)
▶️ 答え:農地法第4条
- 所有者は変わらない
- でも使い方を「農地 → 宅地」に変える(転用)
- → だから「第4条許可」が必要です
❓ Q3. 自分の畑を不動産会社に売り、会社が宅地にして分譲予定
▶️ 答え:農地法第5条
- 所有者が変わる(売却)
- 土地の使い方も変わる(宅地化)
- → だから「第5条許可」が必要です
❓ Q4. 父の畑を借りて、自分(息子)がそこに家を建てたい
▶️ 答え:農地法第5条
- 所有権は父のままでも、「使用権」があなたに移る(使用貸借による権利移動)
- さらに使い方も変わる(転用)
- → 「人も使い方も変わる」ため、親子間でも第5条の対象になります
💡 まとめポイント:
| 条件 | 当てはまる条文 |
|---|---|
| 人が変わる(売買・貸借など) | 3条または5条 |
| 土地の使い方が変わる(宅地・駐車場などへ) | 4条または5条 |
| 両方変わる場合 | 5条一択 |
ちょっとした違いでも、該当条文が変わることがあります。
迷ったときは、手続きの前に行政書士へご相談ください。
申請前に必ず確認したい3つの実務ポイント
条文の違いがわかっても、「じゃあ実際にどう動けばいいのか?」という段階でつまずく方も少なくありません。
ここでは、農地に関する申請を進めるうえで、特に大事な3つのポイントを実務の視点からご紹介します。
これを知っているかどうかで、手続きのスムーズさや成功率が大きく変わります。
✅ ① 上位法令の確認:農地法の前に“チェックすべき法律”がある!
多くの方が見落としがちなのが、「農地法に進む前に、そもそも転用できる土地かどうか」の確認です。
農地は、都市計画法や農振法といったより上位の法律の規制を受けている場合があります。
■ 都市計画法:土地の区域区分を確認する
- 市街化区域なら → 転用は基本的に“届出”でOK(許可不要)
- 市街化調整区域なら → 原則転用NG。開発許可や例外基準が必要で、非常にハードルが高い
■ 農振法(農業振興地域の整備に関する法律):青地かどうかを確認
- 青地(農用地区域)の場合 → 転用は原則不可
- 転用には「農振除外」が必要だが、年に数回の受付+高い要件が課され、1年以上かかることも
✅ ② 申請窓口の誤解に注意:許可は知事、でも提出先は市町村
4条・5条の許可権者は都道府県知事ですが、申請書の提出先は市町村の農業委員会です。
農業委員会は、現地調査や意見書の作成を行い、知事に進達します。この農業委員会の判断が、事実上の可否を左右するため、最初の相談段階からしっかり丁寧に説明することが重要です。
✅ ③ 無許可転用のリスク:バレなきゃ大丈夫…は通用しません!
許可を得ずに転用を進めた場合(違反転用)、以下のような重いペナルティがあります。
- 個人の場合: 3年以下の懲役 または 300万円以下の罰金
- 法人の場合: 最大1億円以下の罰金
さらに、「原状回復命令」により建物の撤去や土地の復元を命じられる可能性もあります。
費用的にも精神的にも、取り返しのつかない状況になる前に、必ず正規の手続きを踏みましょう。
📌 まとめ:
申請に進む前に、以下の3点を必ず確認してください。
- 都市計画法・農振法などの上位法令による制限
- 申請の実務窓口(農業委員会)との事前相談の重要性
- 無許可で進めた場合の重大なリスク
ちょっとした確認漏れが、大きなトラブルにつながる分野だからこそ、事前準備がすべてです。
【まとめ】農地手続きの第一歩は「条文の理解」と「事前確認」から
この記事では、農地法の3条・4条・5条について、それぞれの違いや判断ポイント、実務上の注意点を詳しく解説してきました。
ポイントを振り返っておきましょう。
- 農地法3条: 農地のまま、人が変わる(権利の移動)
- 農地法4条: 人は同じで、土地の使い方が変わる(転用)
- 農地法5条: 人も土地の使い方も変わる(転用目的の権利移動)
そして何より大切なのは、「自分の土地がそもそも転用できる場所かどうか」=都市計画法や農振法の規制確認を、最初の段階で行うことです。
🌾 農地に関する手続きで、こんなお悩みありませんか?
- 相続した畑を活用したいけど、何から始めればいいかわからない
- 住宅や倉庫を建てたいが、転用できる土地なのか判断がつかない
- 無許可で動いてしまいそうで不安…後からトラブルになるのは避けたい
そんなときは、農地手続きに詳しい行政書士にご相談ください。
現地の状況や今後の活用計画に応じて、適切な手続きとスケジュールをご提案いたします。
▼ お問い合わせはこちらから