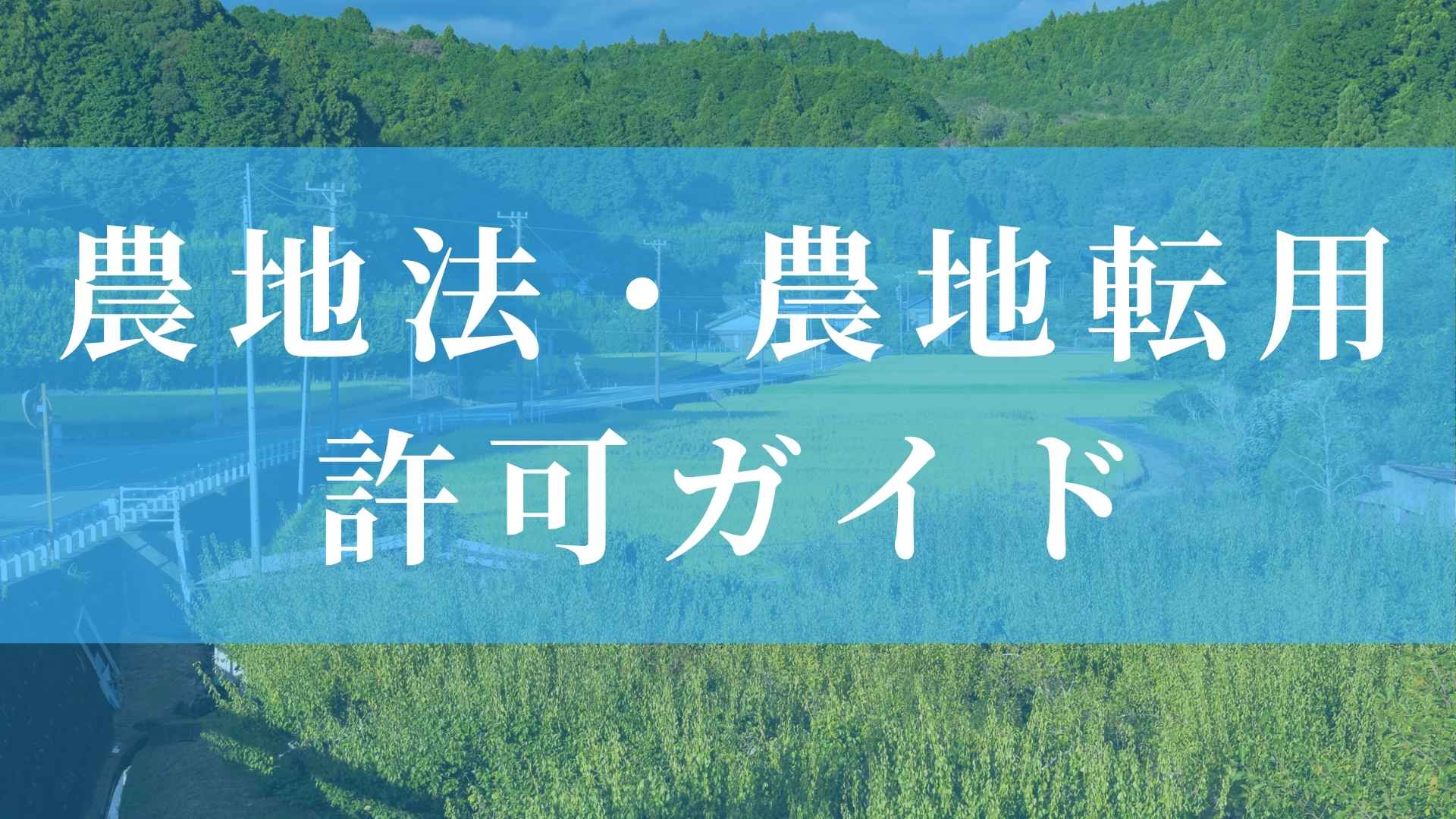こんにちは、行政書士の三澤です!
「親から相続した畑を、農業を始めたいという知人に売りたい」
「新規就農のために、近所の農家さんから田んぼを借りたい」
このような“農地の売買や貸し借り”を考えたときに、必ず立ちはだかるのが「農地法」という法律です。
中でも、農地を農地のまま使い続けながら、他人に譲る・貸すといったケースでは、「農地法第3条の許可」という手続きが欠かせません。
とはいえ、「農地法って何?」「なぜ“許可”が必要なの?」「自分の土地なのに自由にできないの?」と疑問に思われる方も多いはず。
この記事では、農地の売買や貸し借りを検討している方に向けて、
農地法第3条の許可がどういう制度なのか、どんなときに必要で、どんな準備が必要なのかを、行政手続きの専門家の視点からわかりやすく解説していきます。
「農地手続きでトラブルにならないために」「安心して農業をスタートするために」――
まずはこのページで、農地法第3条の基本をしっかり押さえておきましょう。
なぜ必要?農地を譲るときの「第3条許可」って何のため?
農地法第3条は、ひと言で言えば
「農地を農地として使い続けること」を前提に、その権利を移動させるときのルールを定めたものです。
具体的には、農地や採草放牧地を、耕作目的で誰かに売ったり貸したりするときには、
その土地がある市町村の農業委員会の許可を受ける必要があると定められています。
用語メモ
「採草放牧地」とは…
家畜のエサになる草を刈ったり、放牧に使ったりする土地のこと。
農地ではありませんが、農地法上は農地とほぼ同じように扱われます。
では、自分の土地を誰に譲ろうと勝手じゃないの?――
そう感じる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし農地は、単なる「個人の財産」ではなく、日本の食料を支える貴重な資源として守られるべきものなのです。
農地法第1条では、農地を「国民の限られた資源」「地域の大切な資産」と位置づけています。
この理念に基づき、第3条の許可制度には、次のような役割が託されています。
農地法第3条許可制度の3つの目的
- 安定した食料供給を守るため
良質な農地が乱開発や放置によって失われるのを防ぐ。 - 優良な農地を活かすため
農業を本気でやる人に、効率的に土地を使ってもらう。 - 投機や転売目的を防ぐため
実際に耕す気もないのに、値上がりを期待して農地を買うような行為を防止する。
つまり農地法第3条の許可制度は、単なる役所の手続きではなく、
農業の未来と地域社会を守るための「セーフティネット」とも言える仕組みなのです。
【迷ったらここ!】農地法3条・4条・5条の違いをかんたん整理
農地の手続きを考えるとき、よく登場するのが「農地法第3条・第4条・第5条」。
数字は似ていますが、それぞれ対象となるケースや手続き内容がまったく異なるので、
最初にしっかり整理しておくことが大切です。
まず押さえるべきポイントはこれ!
| 条文 | 何が変わる? | 土地の使い道 | 誰が許可する? | 具体例 |
|---|---|---|---|---|
| 第3条 | 人が変わる(権利の移動) | 農地のまま | 農業委員会 | 農家Aさんが、就農希望者Bさんに農地を売る |
| 第4条 | 土地の用途が変わる(転用) | 農地 → 宅地など | 都道府県知事等 | Aさんが自分の畑に自宅を建てる |
| 第5条 | 人も用途も変わる | 農地 → 宅地など | 都道府県知事等 | CさんがAさんから農地を買って家を建てる |
各条文の意味と特徴
✅ 第3条(農地のまま譲渡・貸借)
- 目的:農地を引き続き農地として活用すること
- 許可先:農業委員会
- ポイント:農地の権利が移動するだけで、使い道はそのまま
✅ 第4条(自己所有の農地を転用)
- 目的:農地を宅地や駐車場など、別の用途に変える
- 許可先:原則として都道府県知事など
- ポイント:人は変わらないが、土地の用途が変わる
✅ 第5条(転用目的の権利移動)
- 目的:他人に農地を渡し、さらにその土地を別用途に転用
- 許可先:原則として都道府県知事など
- ポイント:「3条+4条」がセットになったような手続き
なぜ第3条は「農業委員会」、4条・5条は「都道府県知事」?
この違いには、法の考え方が反映されています。
- 第3条:農地を農地として残すことが前提なので、地域の実情に詳しい「農業委員会」が判断
- 第4条・5条:農地が消えてしまう(転用)ため、より広い視点から土地利用を判断できる「都道府県知事等」が許可を行う
つまり、「農地を守る手続き」と「農地を転用する手続き」では、扱いの重みが違うというわけです。
迷ったときは、「人が変わる? 土地の使い道が変わる?」という視点で整理すると、どの条文が該当するのかが自然と見えてきます。
許可が必要なとき・不要なとき ~よくあるケースをチェック~
「農地法第3条の許可って、どんなときに必要なの?」
実際のご相談でも、ここが一番混乱しやすいポイントです。
この章では、許可が必要なケース・不要なケースを、わかりやすく整理していきます。
✅ 許可が【必要】なケース
農地を耕作目的で譲ったり借りたりする契約(=法律行為)をするときは、原則すべて「許可が必要」です。
具体的な例
- 売買:農地をお金を払って買う
- 贈与:無償で農地を譲る(例:親から子へ)
- 賃貸借:農地を家賃(賃料)を払って借りる
- 使用貸借:無償で農地を借りる(例:親戚間で「自由に使っていいよ」と貸す)
- その他:地上権・永小作権・質権など、農地を使って利益を得る権利設定
ケース
- 引退する農家Aさんが、若手のBさんに田んぼを売却する
- 実家の畑を、弟に無償で貸す(使用貸借)
- 農業法人が、遊休農地を地主から年間契約で借りる
❌ 許可が【不要】なケース
一方、当事者の意思に基づかず自動的に権利が移る場合や、
国が特例として認めている場合には、許可は不要です。
具体的な例
- 相続・遺産分割:被相続人が亡くなり、農地の権利が法定相続人に移るとき
- 法人の合併・分割、時効取得:会社間の統合や時効による取得など
- 農業経営基盤強化促進法による貸借:
市町村が策定した「農用地利用集積計画」に基づく農地の貸し借り
注意ポイント!
- 遺言で相続人以外に譲る「特定遺贈」の場合は、許可が必要になるので注意が必要です。
【超重要】許可は不要でも「届出義務」があるケースに注意!
特に多い誤解がこちらです。
「相続だから許可はいらないよね?じゃあ、何もしなくていいよね?」
→ いいえ、それは誤解です!
相続などで農地を取得した場合でも、
農業委員会への「届出(農地法第3条の3)」が法律上義務とされています。
この届出は、取得を知った日から10ヶ月以内に提出しなければなりません。
届出のポイント
- 登記とは別手続き:登記をしても、届出をしないと義務違反になります
- 罰則あり:虚偽の届出や未届出は、10万円以下の過料の対象になります
許可が下りるかどうかはここで決まる!農地法第3条の4つの審査ポイント
農地法第3条の許可を受けるには、
申請者が「本当に農地をきちんと耕してくれる人かどうか」が重要な判断基準になります。
農業委員会は次の4つの要件(許可基準)をもとに、厳しく審査を行います。
✅ 要件①:全部効率利用要件
→ 持っている農地を全部、有効に使えているか?
この要件は、もっとも重視される審査ポイントです。
- 今回取得する農地だけでなく、すでに所有・借入している農地も含めて、
すべてを効率よく使えているかが問われます。 - 「農地を持っているだけ」「雑草が茂っている放置地」がある場合、許可はまず下りません。
審査で見られるポイント
- 農機具や設備:トラクターや田植え機などが揃っているか、リースの予定があるか
- 労働力:本人や家族の人数・労働時間は十分か。人手不足なら外部雇用の計画があるか
- 技術や経験:作付予定の作物について、経験や研修歴があるか(新規就農者は特に重要)
用語メモ
「世帯員等」とは、同じ家に住んでいて生計を共にしている親族なども含みます。
✅ 要件②:農作業常時従事要件
- 農業を本業レベルで継続できるか?
農地を取得する人やその家族が、
年間150日以上を目安に農作業に従事していることが求められます。
これは、いわゆる「趣味レベル」や「資産保有目的」で農地を持つ人を排除するための要件です。
法人の場合はさらに厳格に
- 農地所有適格法人(旧:農業生産法人)でないと農地を取得できません。
- 役員の過半数が農業に常時従事している必要があります。
一部緩和されるケースも
- 「農地を借りる(賃貸・使用貸借)」だけなら、
将来の返還も可能なため、要件が一部緩和されることがあります。
✅ 要件③:下限面積要件【※2023年に廃止】
→ 最低面積のルールは、すでに撤廃されています
以前は「都府県では合計50a(5000㎡)以上」などの下限がありましたが、
2023年4月1日の法改正で廃止されました。
廃止されたとはいえ…
- 審査が甘くなったわけではありません。
- 小さな農地でも「しっかり活用できる具体的な計画」がなければ、許可は下りません。
- 営農計画書の中身がこれまで以上に重視されます。
✅ 要件④:周辺農地への影響要件
→ 地域の農業に迷惑をかけないか?
農業は一人で完結するものではなく、
水利・病害虫防除・大型機械の通行など、地域との協調が不可欠です。
よくあるNG例
- 地元の用水路を勝手にふさいでしまう
- 減農薬エリアで一人だけ農薬を大量使用
- 集団営農地の中で、機械の進入路を遮る土地の取得 など
農業委員会はこうした点もチェックして、地域全体の農業が損なわれないかを判断します。
✅ 許可を取るには「リアルな営農計画」がカギ!
形式的な条件よりも、「本当に農業をやっていけるかどうか」が問われる時代です。
農地を取得したい方は、現実的で説得力のある営農計画書の準備が何より重要です。
農地法第3条の申請手続きと期間 ~スムーズに進めるための流れを解説~
農地法第3条の許可申請は、「思い立ってすぐできるもの」ではありません。
提出書類の準備や事前相談、審査のスケジュールなどを踏まえて、余裕をもって計画的に進めることが成功のカギです。
ここでは、申請から許可が下りるまでの全体の流れと目安となる期間をわかりやすく解説します。
✅ 許可までの6ステップ
ステップ①|事前相談(農業委員会)
まず最初に行うべきは、市町村の農業委員会への事前相談です。
申請予定の農地の所在地を管轄する農業委員会に連絡し、以下を確認しましょう。
- 許可の見込みがあるか
- 地域独自のルールや慣習があるか
- 具体的にどんな書類が必要か
👉 このステップを丁寧に行うことで、後の手続きがスムーズになります。
ステップ②|申請書類の作成・収集
農業委員会で確認した内容をもとに、申請書や営農計画書などを作成し、
法務局・役所などから必要な添付書類(登記簿謄本、公図、住民票など)を集めます。
ステップ③|申請書の提出
必要書類がすべて揃ったら、農業委員会に申請します。
ここで重要なのが「締切日」!
多くの農業委員会では、毎月1回の申請締切日があり、
それを過ぎると審査が翌月に持ち越しになるため、1ヶ月以上遅れることもあります。
ステップ④|農業委員会の審査・現地調査
提出された申請書類に基づいて、
農業委員会の担当者が「4つの許可要件」を満たしているかを審査します。
同時に、現地調査も行われ、農地の管理状況や周辺環境が確認されます。
ステップ⑤|農業委員会総会での審議・決定
毎月1回程度開催される農業委員会の総会で、
申請内容が正式に審議され、「許可」または「不許可」が決まります。
ステップ⑥|許可書の交付
許可が下りると、後日「許可書」が交付されます。
この許可書をもとに、法務局で所有権移転登記や賃借権の設定などの手続きが可能になります。
🕒 標準的な処理期間の目安は?
書類に不備がなく順調に進んだ場合、
申請締切日から約1ヶ月後に許可が下りるのが一般的です。
たとえば、「毎月1日締切」の自治体であれば、
その月の下旬には許可が下りるというスケジュールになります。
- 書類に不備があると、確認や差し戻しで大幅に遅れることがあります。
- 年度末や繁忙期は、申請件数が多くなるため処理が遅れることもあります。
✅ 余裕をもった準備が成功のコツ!
- まずは農業委員会へ事前相談
- 締切日を意識して書類を早めに揃える
- 書類は“完璧な状態”で提出する
こうした基本を守るだけでも、申請の通過率はぐっと上がります。
許可申請に必要な書類一覧 ~漏れなく揃えてスムーズ申請を~
農地法第3条の申請には、多くの書類が必要です。
書類に不備があると手続きがストップしたり、審査が1ヶ月以上遅れたりすることもあります。
ここでは、許可申請時に必要となる主な書類と取得先を一覧でご紹介します。
📌 注意:自治体によって必要書類・様式が異なる場合があります。
申請前に、必ず管轄の農業委員会へ確認しましょう!
✅ 申請書類一覧(一般例)
| 提出者 | 書類名 | 内容・取得先 |
|---|---|---|
| 共通 | 農地法第3条許可申請書 | 農業委員会窓口または市町村HPで入手。譲渡人・譲受人の署名・押印が必要 |
| 共通 | 登記事項証明書(登記簿謄本) | 法務局で取得。発行後3ヶ月以内のもの |
| 共通 | 公図の写し | 法務局で取得 |
| 共通 | 位置図・案内図 | 地図コピー等で対象地が特定できるもの(住宅地図など) |
✅ 譲受人(借りる・買う側)が準備する書類
| 書類名 | 内容・取得先 |
|---|---|
| 営農計画書 | 作付内容・労働力・農機・販売計画などを記載。審査のカギになる重要書類 |
| 住民票の写し | 市区町村役場で取得 |
| 耕作証明書 | 市外の農地をすでに所有・賃借している場合、その地の農業委員会で発行 |
| 定款または寄附行為の写し | 法人の場合。原本証明が必要なことも |
| 法人の登記事項証明書 | 法人の場合に必要。法務局で取得 |
✅ 譲渡人(貸す・売る側)が準備する書類
| 書類名 | 内容・取得先 |
|---|---|
| 住民票の写し | 登記簿上の住所と現住所が異なる場合に必要。市区町村役場で取得 |
✅ その他(該当する場合のみ)
| 書類名 | 内容 |
|---|---|
| 土地改良区の意見書 | 農地が土地改良区内にある場合、別途手続きが必要 |
| 水利権関係の書類 | 水路や用水利用の調整が必要な場合 |
| 委任状 | 行政書士などに手続きを委任する場合に必要 |
チェックリストを使って事前確認を!
申請書類は一つでも抜けると、申請を受け付けてもらえないことがあります。
不安な場合は、農業委員会の職員に「事前チェック」をお願いするのも効果的です。
👉 各書類の準備と取得には時間がかかることもあるため、早めの行動をおすすめします。
無許可で農地を売ったり貸したりするとどうなる? ~知らないでは済まされない重大リスク~
「面倒だからとりあえず契約してしまおう…」
「親戚同士だし、役所に届けなくても大丈夫でしょ?」
そんな軽い気持ちで農地の取引をしてしまうと、重大なトラブルや法的リスクを招くことになります。
農地法第3条の許可を得ずに売買や貸借を行った場合、契約自体が“なかったこと”になるほか、刑事罰の対象になる可能性もあるのです。
❌許可なし契約は「無効」です!
農地法第3条の許可を受けていない取引は、
法律上「無効(=はじめから効力がない)」とされます。
無効になるとどうなる?
- 売買代金を支払っても、所有権は移らない
- 登記もできない
- 買主は法的には何の権利もないまま土地を使っている状態に
- 売主から「返せ」と言われれば、応じるしかない
- 最悪の場合、民事トラブルに発展し訴訟へ
用語メモ「無効」
無効とは「取消」と違い、最初から契約が成立していなかったことになる厳しい扱いです。
⚠ 無許可取引には「刑事罰」もあります
農地法に違反した場合、
農地法第64条に基づき、以下のような刑事罰が科される可能性があります。
- 3年以下の懲役
- 300万円以下の罰金
さらに、違反を知りながら契約を進めた行政書士などの関係者にも、場合によっては責任が問われる可能性があります。
✅ 「知らなかった」では済まされません
農地法は、農地を守るために厳格なルールを設けています。
そのルールを無視して手続きを飛ばせば、
当事者同士の信頼も失い、法的にも極めて危険な状態に陥ります。
「正式な許可を取ってから契約を交わす」
――これは、農地を扱うすべての人が守るべき基本ルールです。
不安なときは、必ず専門家に相談しましょう。
まとめ:農地の手続き、迷ったら行政書士に相談を
ここまでご覧いただきありがとうございます。
農地法第3条の許可について、手続きの流れや注意点、許可基準などを解説してきました。
この記事のポイントを改めて振り返りましょう。
✅ 農地法第3条の許可は「絶対に必要」です
- 農地を農地のまま売ったり貸したりする場合は、必ず農業委員会の許可が必要です。
- 許可を得ずに契約すると、その契約は無効扱いになり、トラブルや罰則の原因になります。
✅ 許可を取るには「現実的な営農計画」がカギ
- 審査では、「ちゃんと農業を続けられる人かどうか」が問われます。
- 特に営農計画書の内容は、審査の合否を左右する重要なポイントです。
✅ 相続でも「届出」が必要です
- 相続など許可がいらないケースでも、届出義務(第3条の3)があります。
- 届出を怠ると、過料(最大10万円)の対象になるため注意が必要です。
✨ 農地手続きは、行政書士にお任せください!
農地法の手続きは、
単に書類を出すだけではなく、専門知識と実務経験が求められる複雑な業務です。
当事務所では、こうした農地に関する申請を多数サポートしてきた実績があります。
初回相談は無料ですので、「うちのケースはどうなんだろう?」という段階でも、お気軽にご相談ください。
📌 行政書士に依頼する4つのメリット
- 申請をスピーディーに進められる
書類の作成から提出まで一括サポート。不備によるやり直しを防ぎます。 - 審査に通りやすい書類を作成
営農計画書や必要書類を、審査基準に沿って整えます。 - 行政とのやり取りもすべて代行
農業委員会との事前相談・交渉・説明もお任せください。 - 他士業と連携したトータルサポート
登記が必要なら司法書士、測量が必要なら土地家屋調査士と連携し、まとめて対応します。
📞 お問い合わせ・ご相談はこちら
農地の売買や貸借、新規就農、相続した農地の活用など――
どうぞお一人で悩まず、まずは行政書士にお話しください。
あなたの大切な土地と未来の農業を、確かな手続きで守ります。