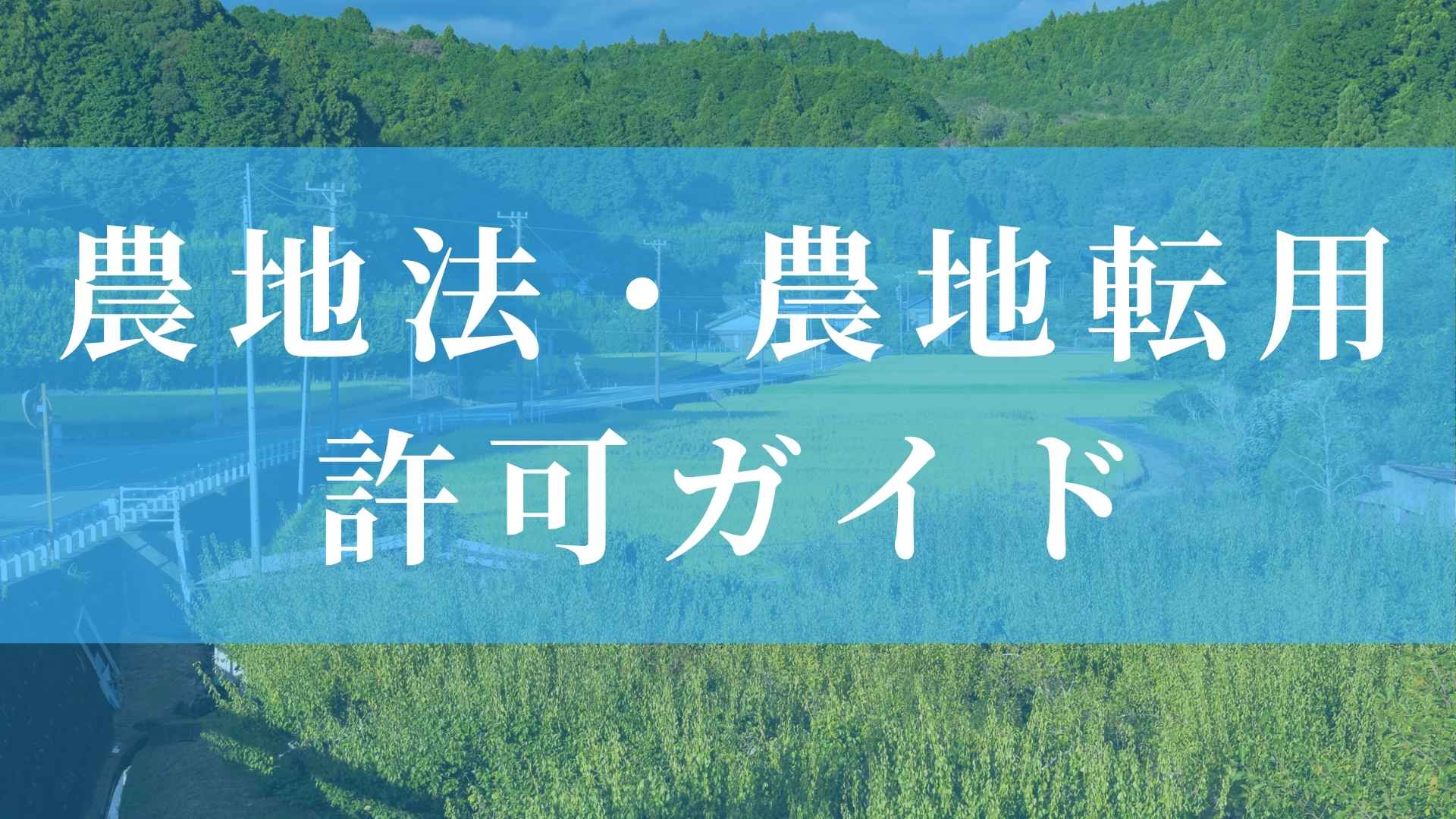こんにちは、行政書士の三澤です!
今、日本の農業は大きな転換点を迎えています。
高齢化と深刻な後継者不足によって、農業の担い手が急速に減少し、耕作放棄地の増加が社会全体の課題となっています。
たとえば、農林水産省の統計によると、2020年時点で基幹的農業従事者(主に農業を本業とする人)の約70%が65歳以上を占めており、49歳以下はわずか11%にすぎません。
さらに、農業経営体の約7割が後継者を確保できていないというデータもあり、現場の実情は極めて深刻です。
こうした背景を受けて、2023年4月1日に施行されたのが、今回の農地法改正です。
その最大のポイントが、「下限面積要件の廃止」です。
これは、これまで新たに農業を始めようとする人にとって、大きなハードルとなっていた「最低限必要な農地面積」の条件を撤廃するもの。
この法改正によって、より柔軟で多様な形での農業参入が可能となり、遊休農地の有効活用や、新しい担い手の確保に向けて、大きな期待が寄せられています。
この記事でわかること
- 改正前の「下限面積要件」とは何だったのか
- 2023年の改正で何が変わったのか
- 改正によって可能になる新たな農業の形
- そして、要件廃止後も引き続き注意すべき法律上のポイント
といった点を、できる限りわかりやすく、かつ正確に解説していきます。
これから農業にチャレンジしたい方、小規模な農地を取得したいと考えている方にとって、本記事が確かな判断材料となることを願っています。
「下限面積要件」とは何か|改正前の制度を正しく理解する
今回の法改正の本質を理解するためには、まず廃止された「下限面積要件」がどのような制度だったのかを押さえておく必要があります。
「下限面積要件」とは、農地法第3条に基づき、農地を耕作目的で取得(売買・賃貸借等)する際に必要な許可要件のひとつです。
具体的には、農地の権利を取得した後の農地経営面積の合計が、一定以上でなければならないというものでした。
基準は次の通りです:
- 都府県:原則50アール(5,000㎡)以上
- 北海道:原則2ヘクタール(20,000㎡)以上
ただし、各市町村の農業委員会は、地域の実情に応じて「別段の面積(緩和基準)」を設定することも可能でした。
とはいえ、「一定規模以上の農業経営体を育成する」という政策的な意図に基づく原則は、全国共通で適用されていました。
制度の目的と、時代の変化による副作用
この要件の背景には、かつての農業政策における「効率的で安定した農業経営体の育成」という目的がありました。
零細経営の乱立を防ぎ、ある程度の規模をもつ農業者に農地を集約させることで、生産性の向上を図るという考え方です。
しかし時代が進み、担い手不足が深刻化する中で、この制度はむしろ「新たな農業の担い手」の参入を妨げる障壁になっていきました。
たとえば、以下のような方々にとって「下限面積要件」は高すぎるハードルとなっていたのです:
- 小規模から始めたい新規就農者
資金・人手・設備が限られている段階で、50アール以上の農地確保は現実的ではありません。 - 「半農半X」型のライフスタイル志向の方
本業や地域活動と両立させながら農業を行いたい方にとって、大面積の経営は不向きでした。 - 定年帰農者やUターン・Iターン希望者
「まずは小さな畑で自分なりの農業を始めたい」という想いが、面積要件によって断念に追い込まれていました。 - 企業の試験的な農業参入
研究開発や地域貢献として小規模に農業を始めたい法人も、面積要件がネックとなっていました。
このように、かつては農業の効率化を目的とした制度が、現代においては新たな担い手の参入を阻む「参入障壁」となってしまっていたのです。
これが、後述する法改正の重要な背景となっています。
2023年農地法改正の核心|「下限面積要件」の撤廃とその意義
2023年4月1日に施行された農地法改正は、日本の農業政策における重要な転換点です。
その中でも、もっとも大きなインパクトをもたらしたのが、「下限面積要件」の完全撤廃です。
この改正は単なる制度変更ではなく、日本の農業の未来に向けた本格的な構造転換の一環として実施されたものであり、非常に重要な意味を持っています。
下限面積要件の完全撤廃|農地法第3条の大きな変化
まず結論から申し上げると、2023年4月1日より、農地法第3条の許可要件として定められていた「下限面積要件」は完全に廃止されました。
この法改正は、
「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)」
に基づいて行われたものであり、農地法の一部改正にとどまらず、日本の農業経営全体を見直す包括的な取り組みの一環として位置づけられています。
これにより、面積による参入制限は撤廃され、農地取得の門戸が大きく開かれたのです。
なぜ下限面積要件は廃止されたのか?|政策転換の背景と目的
農林水産省がこの改正に込めた目的は非常に明快です。
「経営規模の大小を問わず、意欲ある多様な人材の新規参入を促し、遊休農地の発生を防ぎながら、農地の有効活用を図る」
これは、日本の農業政策が根本的に方向転換したことを意味しています。
従来の政策は、「下限面積要件」というフィルターを設けて、「一定規模以上の農業者=本格的な担い手」を選別する方式(ゲートキーピング型)でした。
しかし、その結果として、担い手そのものが不足し、農地が使われずに放置されるという深刻な事態を招いてしまいました。
今回の改正では、「意欲がある人を排除しない」という発想に転換。
参入のハードルを下げ、多様な人材の農業参入を後押しする「ファシリテーション(促進)」型の政策へと大きく舵を切ったのです。
さらにこの改正は、「規制緩和」で終わるものではありません。
- 市町村による「地域計画」の策定が義務化され
- 農地中間管理機構(通称:農地バンク)の機能が強化される
といった施策と組み合わされ、「参入しやすくする」だけでなく、「参入後の農業経営が持続可能となる地域体制づくり」を同時に進める、戦略的な構造改革となっています。
つまり、下限面積要件の廃止は、単なる参入規制の撤廃ではなく、
「多様な担い手が農業に参加し、地域農業の未来を担う存在として活躍できる仕組み」を実現するための第一歩なのです。
「下限面積要件」の撤廃がもたらす現実的な変化と可能性
下限面積要件の廃止によって、農地取得に関する大きなハードルが取り除かれました。
これにより、従来は農地法の要件により参入が難しかった多くの人々に、新たなチャンスが生まれています。
ここでは、今回の法改正によって実際にどのような変化が起きるのか、3つの観点から具体的に解説します。
小規模農地の取得が「現実的な選択肢」に
これまで農地を取得するには、原則として都府県で50アール以上、北海道で2ヘクタール以上の農地を確保する必要がありました。
この面積基準は、資金・人手・経験の乏しい新規参入者にとって、極めて大きな障壁でした。
しかし今回の改正により、たとえば10アール(1,000㎡)といった小規模な農地でも、農業委員会の許可を得て正当に取得することが可能になりました。
- 週末農業として趣味の延長で始めたい方
- 特定の野菜やハーブを小規模に栽培し直販したい方
- 家族と協力して小さな自給的農園を運営したい方
こうした方々にとって、農業への一歩がグッと身近なものになります。
「半農半X」という多様なライフスタイルが現実に
「半農半X」とは、小規模な農業(半農)と、自分の得意分野・仕事・活動(X)を組み合わせて暮らすという、柔軟なライフスタイルの提案です。
たとえば:
- リモートワーカーが週の一部を畑作業に充てる
- 伝統工芸家が自ら育てた植物で染色素材を確保する
- 主婦が家庭菜園レベルの農業を発展させ、地域販売に挑戦する
このように、「生計の一部としての農業」や「生活の質を高める農業」が現実的な選択肢になります。
下限面積要件の廃止は、こうした多様な暮らし方を制度面で支える、大きな転機といえるでしょう。
担い手不足の打開へ|個人・法人を問わず新規参入が加速
今回の改正は、農業を取り巻く深刻な担い手不足に対する強い危機感から行われたものでもあります。
今後は個人・法人を問わず、さまざまな形での参入が想定されます。
個人のケース
- 定年後にUターン・Iターンして農業を始めたい高齢者
- 自然豊かな土地で家族と暮らしながら、農業に挑戦したい若年層
- 都市部から地方へ移住し、地域と関わる仕事として農業を選びたい方
こうしたニーズに応える柔軟な制度環境が整ってきました。
法人のケース
企業にとっても、小規模農地の取得がしやすくなったことで、以下のような新たな活用が可能になります:
- 食品メーカーや種苗会社による試験農場の運営(研究開発・実証実験)
- 社員の福利厚生や地域貢献を目的とした社内農園(CSR施策)
- 異業種企業によるスマート農業や高付加価値型農業への新規参入
こうした法人の柔軟な参入は、農地の有効活用を進めるだけでなく、地域経済や雇用への波及効果も期待できます。
このように、下限面積要件の撤廃は、農業参入の“現実的な可能性”を大きく広げる法改正です。
それは単なる制度緩和ではなく、「農業の未来を開くための土台づくり」と言えるでしょう。
行政書士が解説|要件廃止でも変わらない大事なポイントとは?
「下限面積要件が廃止された」と聞くと、「これでもう自由に農地が買える」と誤解してしまう方もいるかもしれません。
しかし、行政書士として強調したいのは、農地取得に関する法的なハードルがすべて取り払われたわけではないということです。
農地法は、「農地は耕作者自身が耕作するべきもの」とする耕作者主義を基本理念としています。
この理念は、今回の法改正によってもまったく変わっていません。
つまり、農地を取得するには依然として農業委員会の許可が必要であり、その許可を得るためには複数の要件をクリアする必要があります。
下限面積要件は廃止されましたが、それ以外の要件は引き続き審査対象であり、むしろ重視される傾向にあります。
ここでは、現在も残っている主な許可要件と、実務上注意すべき点を解説します。
農地法第3条の許可審査で重視される主要な要件とは?
下限面積要件は廃止されましたが、農地法第3条の許可申請においては、今も複数の重要な審査基準が存在します。
むしろ面積という形式的基準がなくなった今、農業を実際に行う意志と計画の実質性がより厳しく問われるようになったと言えます。
ここでは、現在も適用されている主な要件と、行政書士としての実務的な確認ポイントを解説します。
| 要件 | 概要 | 実務上の確認ポイント(行政書士視点) |
|---|---|---|
| ① 全部効率利用要件 | 申請者が取得予定の農地だけでなく、すでに所有・借入している全農地についても、効率的に耕作・利用すること。 | 作成する営農計画書が具体的かつ現実的かが鍵。作付け品目・時期・販売方法などが詳細に記載されているか。実行可能性の裏付け(機械・労力・資金)も重要。抽象的な内容では「形式的申請」と判断される恐れがある。 |
| ② 農作業常時従事要件 | 申請者本人または世帯員が、年間150日以上を目安に農作業に従事すること。 | 現在の職業や生活スタイルから見て、農作業日数を確保できるかを検討。パートタイム農業や小面積で150日に満たない場合でも、繁忙期の集中従事など、実態に即した説明が求められる。 |
| ③ 地域との調和要件 | 新たに始める農業経営が、地域の農業活動や周辺農地との調和を損なわないこと。 | 水利組合、農道・用水路の利用状況、近隣の営農活動(集落営農・有機栽培など)との関係性を確認。地元の慣習やルールに配慮した計画であるかが問われる。 |
| ④ 農地所有適格法人要件(法人のみ) | 法人が農地を「所有」する場合、農地法で定められた厳格な法人要件を満たす必要がある。 | 主たる事業が農業であること、役員の過半数が農業従事者であることなど、法人形態・役員構成・定款の記載内容などを細かくチェック。なお、「賃借」での取得であれば、一般法人でも可能。 |
これらの要件を正しく理解し、事前に計画・証拠書類・地域対応を整えることが、農地取得をスムーズに進める鍵となります。
特に営農計画の具体性と、地域との関係性(地域計画や水利権など)に対する配慮は、審査の通過率に大きく影響する重要ポイントです。
行政書士としては、これらの要件を総合的に見ながら、「法的に整合性があり、現実的で、地域にも受け入れられる計画」を構築する支援を行います。
地域計画という“見えないハードル”|制度理解のカギを握るポイント
農地法の改正により下限面積要件は廃止されましたが、実務上の新たな判断基準として、「地域計画」との整合性が極めて重要になっています。
この地域計画こそが、ある意味で「新たなハードル」となり得る点を見落としてはいけません。
地域計画とは?
地域計画とは、市町村が地域内の農業者や農業委員会・農地中間管理機構などと協議のうえで策定する、農地利用の将来像を描いた公式な計画です。
具体的には、
- どの農地を誰が利用していくのか
- どのような営農形態(大規模・集落営農・有機農業など)を想定しているか
- どのエリアを農地バンク(農地中間管理機構)に集約していくか
といった「農地の未来図」が明記されます。
この地域計画は、法的に市町村に策定が義務付けられており(農業経営基盤強化促進法の改正による)、今後の農地法第3条許可審査において、重要な判断材料として活用されることが明言されています。
地域計画と整合しない申請は不許可の可能性も
たとえ申請者の営農計画が真摯で実現可能性の高いものであったとしても、
地域計画に照らして「調和を乱す」と判断されれば、許可が下りないケースもあります。
例:想定されるケース
- 申請者:小規模なオーガニック農園を始めたい個人
- 対象農地:地域計画では「大規模稲作法人への集約エリア」として位置付けられている
この場合、個人の農業意欲や営農計画の内容にかかわらず、「地域全体の農地集約戦略を妨げる」として不許可となるリスクが生じます。
なぜ地域計画が重視されるのか?
背景にあるのは、限られた農地資源を地域単位でどう活かすかという“農業政策の現場主義”への転換です。
個々の申請内容だけでなく、その地域全体の農業戦略との整合性が問われる時代に入ったのです。
行政書士の支援が力を発揮する場面
この「地域計画との整合性」の確認と対策は、農業者にとってハードルが高く、情報の非対称性も大きな課題です。
そこで、行政書士が果たす役割は次のように広がります:
- 地域計画の内容を調査・読み解く
- 対象農地の位置づけを確認
- 必要に応じて農業委員会・市町村と事前協議
- 地域方針に沿った申請戦略の構築
これらの対応を通じて、地域との衝突を回避しながら、許可が得られる現実的なルートを見出すことが可能になります。
地域計画は、行政文書であるがゆえに「表立って拒否されることはないが、審査の中で強く作用する」―そんな“見えざる要件”とも言える存在です。
だからこそ、制度の裏にあるロジックを読み解き、申請者の意欲と地域の戦略とを橋渡しする専門家の存在が、ますます重要になっています。
下限面積要件の廃止は“自由化”ではなく“戦略転換”
2023年の農地法改正により、「下限面積要件」が完全に廃止されました。
これは、これまで農業参入を目指す人々の前に立ちはだかっていた“面積の壁”を取り払い、
多様なライフスタイルや事業モデルに対応した柔軟な農業参入を後押しするものです。
特に以下のような方にとって、大きなチャンスとなる制度改正と言えるでしょう:
- 小規模から農業を始めたい新規就農者
- 都市部から移住して半農半Xを実践したい方
- 企業として農業に試験的に参入したい法人や団体
ただし、面積要件がなくなったからといって、農地が“誰でも自由に買える”ようになったわけではない点には十分注意が必要です。
審査の軸は、これまでの「形式的な要件(面積)」から、
「営農計画の具体性・実現可能性」や「地域農業との調和」といった“中身”重視へとシフトしました。
特に、地域の農業ビジョンを示す「地域計画」との整合性は、今後の審査における最大の焦点になる可能性が高い項目です。
そのため、農地の取得を目指すにあたっては、
- 自分の営農計画が法的に適合しているか
- 地域の計画や農業委員会の方針と矛盾しないか
- 必要な資料や根拠をどう整えるか
といったポイントを、戦略的に整理・準備しておくことが不可欠です。
私たち行政書士は、単なる申請代行者ではありません。
農地取得に向けた法的・実務的な伴走者として、以下のようなサポートを提供しています:
- 計画段階での事前相談・地域調査
- 農業委員会との交渉・打合せ支援
- 許可取得のための営農計画書・必要書類の作成
- 地域計画との整合性をふまえた申請戦略の構築
制度改正によって開かれた新たなチャンスを、確かな一歩につなげるために、どうぞお気軽にご相談ください。
農地取得の成功には、情熱だけでなく、法令理解と地域戦略が欠かせません。
あなたの農業への夢が、地域の未来を支える力となるよう、私たちが全力でサポートいたします。