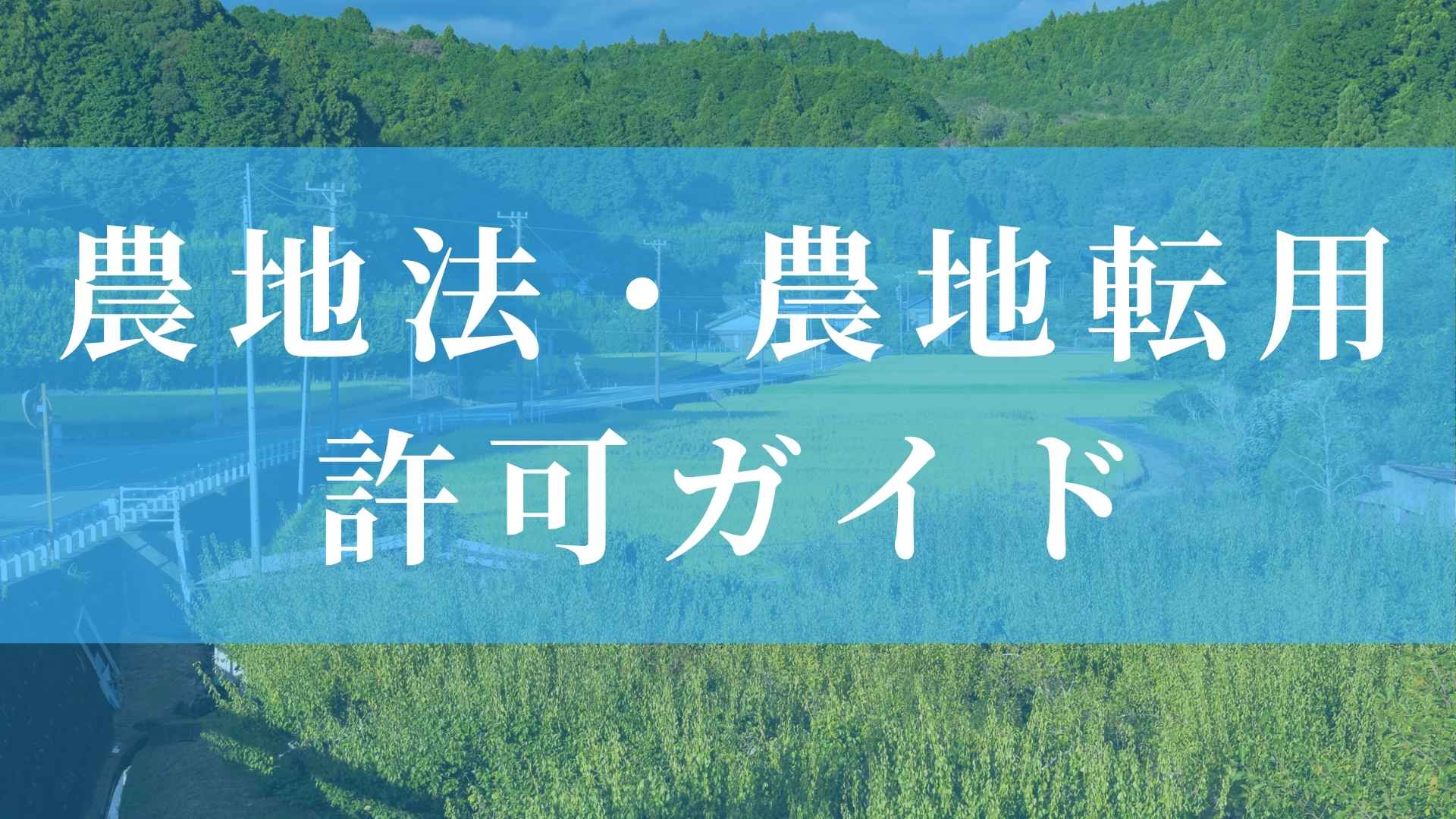こんにちは、行政書士の三澤です!
「自分の畑に家を建てたい」「所有地を駐車場として活用したい」——そんな思いで市町村の窓口を訪れたとき、最初に言われるのが「その土地は農用地区域(いわゆる青地)なので、まず『農振除外』の申出が必要です」という説明です。
「農振除外って何?」「どうすればいいの?」と戸惑われる方がほとんどです。言葉も手続きも聞き慣れないうえ、調べても難しい情報ばかり。どこから着手すべきか分からず、不安だけが膨らんでしまうのが実情です。
実は、農振除外の申出はとても厳格な制度であり、ちょっとした書類の不備や理由書の記載不足で、許可が下りずに何ヶ月、時には1年以上も計画が遅れてしまうこともあります。
しかし、ご安心ください。
本記事では、農振除外とは何かという基本から、実践的なポイント、申請書類の書き方のコは何かまで、現役行政書士が徹底的に解説します。読み終えるころには、制度の全体像と進め方がしっかりと頭に入り、どのように準備すれば良いかがクリアになるはずです。
農振除外は、単なる「書類を出すだけの手続き」ではなく、「あなたの計画を行政に理解してもらうためのプレゼンテーション」でもあります。この記事が、あなたの農地活用計画の道しるべとなれば幸いです。
1. 「農振除外」とは何か?まずは農地の「色分け」を理解しよう
農振除外の制度を正しく理解するには、まず農地がどのように分類されているかを知ることが重要です。実は、農地には大きく分けて「青地」と「白地」という2つの“色”があり、この違いが手続きの難易度を大きく左右します。
青地(農用地区域)――最も厳しく守られている農地
「青地」とは、「農業振興地域の整備に関する法律(農振法)」に基づいて、市町村が将来にわたって農業に使うべきと判断した土地を指します。いわば“スーパー保護農地”であり、次のような特徴があります:
- 集団的にまとまって存在し、土地改良などで整備された優良農地である
- 原則として、農業以外の目的で使うこと(転用)ができない
- 住宅や駐車場にしたい場合は、まず「農振除外」の手続きを経る必要がある
この青地を農業以外に利用できるようにするための第一ステップが、「農振除外の申出」です。これによってはじめて、農地転用の土俵に立つことが可能になります。
白地(農用地区域外)――除外手続きが不要な農地
「白地」は、農業振興地域の中にはあるものの、青地には指定されていない農地です。青地と比べて集団性や生産条件がやや劣ると判断された土地が該当します。
白地の農地では、「農振除外」の手続きは不要です。ただし、農地であることには変わりありませんので、住宅建設や駐車場整備などの目的で使う場合には、別途「農地転用許可」が必要です。
まず最初にやるべきこと:自分の農地の“色”を調べよう
ご自身の土地が「青地」か「白地」かを確認するには、市町村の農政担当課(農政課・農林課など)へ問い合わせるのが確実です。多くの自治体では、地図やGISシステムで区分を確認することができます。
農振除外が必要かどうかは、この“色分け”によって決まります。したがって、農地活用を考えるときは、まずこの確認からスタートすることが非常に重要です。
なぜ農振除外は“高いハードル”なのか?その制度的な背景と役割
「農振除外って、どうしてこんなに厳しいの?」と感じる方は多いかもしれません。しかし、この制度には日本の農業を守るための明確な理由があります。
農業振興地域制度は、「食料自給率の向上」と「持続可能な農業の維持」を目的として設けられたものです。特に「農用地区域(青地)」は、農業にとって最も重要な土地として保護されています。
この制度がなければ、住宅や工場が無秩序に建設され、農地が“虫食い状態”で失われていく恐れがあります。これを防ぐために、あらかじめ市町村が「農業に使うべき土地」と「開発を認める土地」とを明確に区分しているのです。
つまり、農振除外の申出は、国や自治体が定めた“農業重視のまちづくり計画”を、個別の事情によって変更してもらう行為。そう簡単に認められるものではなく、慎重かつ厳格な審査が行われるのは当然のことなのです。
手続きの順番!農振除外と農地転用の関係性
青地の農地を宅地や駐車場として使いたい場合、必要な手続きは一つではありません。実は「二段階の申請」が必要になります。
ステップ①:農振除外の申出(農業振興地域整備計画の変更)
まず行うべきは、「農振除外」です。これは、農業振興地域のうち農用地区域(青地)に指定された土地について、その指定を解除してもらうための手続きです。いわば、「この土地は今後農業に使わなくてよい」と市町村に判断してもらう段階です。
この申出が認められると、土地は「農振白地」と同じ扱いになり、農業以外の活用を検討できるようになります。
ステップ②:農地転用許可申請(農地法第4条・第5条)
次に必要なのが、「農地転用許可」です。これは、農地を宅地や駐車場、資材置場などに“用途変更”するための手続きで、農地法に基づいて都道府県知事等の許可を得る必要があります。
イメージで理解する「除外と転用」
農振除外は、たとえるなら「農地というスタジアム」から出るための退場許可です。スタジアムを出て初めて、別の場所(宅地や駐車場)で“プレイ”するための許可=農地転用が申請できる、という流れになります。
したがって、農振除外と農地転用の順番を間違えると、手続き自体が受け付けられないこともあります。計画は必ず「農振除外→農地転用」の順で進めてください。
2. 農振除外が認められるには?審査を通過するための「5つの要件」
農用地区域(青地)を除外するには、「農業振興地域の整備に関する法律(農振法)」第13条第2項に定められた5つの要件すべてを満たす必要があります。1つでもクリアできない要件があれば、原則として申出は認められません。
ここでは、その中でも特に重要な2つの要件をわかりやすく解説します。
要件1:必要性・代替性 ―「なぜこの土地でなければならないのか?」
【法的定義】
「農用地区域内の土地を農業以外の用途に供することが必要かつ適当であり、かつ代替する土地をもって目的を達成することが困難であること」(農振法第13条第2項)
【わかりやすく言えば】
「どうしてもこの青地を使うしかない、という正当な理由がありますか?」という問いに、論理的かつ客観的に答えられるかが問われます。
【審査でチェックされる主なポイント】
- 計画の具体性・緊急性があるか?
→「将来いつか…」ではなく、すでに計画が動いていて、除外後すぐに着手できるかどうかが重視されます。 - 申請面積が必要最小限か?
→事業や住宅建設に対して、無駄に広すぎる面積を申請していないかどうかも重要です。 - 他の土地(白地や宅地など)では代替できないことを証明できるか?
→例えば、自身の所有地に他の候補がないか、近隣の空き地が使えない理由を具体的に示す必要があります。
「この土地が一番安かった」「自分の土地だから使いたい」という理由は、法的根拠としては認められません。
要件2:集団性・効率性 ―「周囲の農地のまとまりを壊していませんか?」
【法的定義】
「除外によって、農地の集団化や農作業の効率、その他土地の農業上の総合的利用に支障を及ぼすおそれがないこと」
【わかりやすく言えば】
「あなたの計画が、周りの農地のまとまりをバラバラにしてしまわないか?」「農家が使っている機械作業などの効率を妨げないか?」という観点で審査されます。
【よくあるNGケース】
- 広大な田畑の真ん中にポツンと住宅を建てる
- 農道や用水路を挟んで両側に農地がある場所を分断する計画
こうしたケースは、農地の集団性を壊す「分断行為(スプロール化)」として、厳しくチェックされる傾向があります。
【許可されやすいケース】
- 宅地がすでに並ぶ市街地の端に接している農地
- 既存の住宅に隣接しており、農地利用への影響が限定的である計画
地域の地形や農業の実情に応じて、どの程度“支障があるか”が判断されるため、個別具体的な検討が必要です。
要件3:地域農業への支障がないこと ― 担い手農家の経営に悪影響はありませんか?
【法的定義】
「効率的かつ安定的な農業経営を営む者による農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと」(農振法第13条第2項)
【わかりやすく言えば】
この要件では、「あなたが除外を希望している土地を、現在地域の担い手農家が使っていないか?」「その農地が、地域の農業経営にとって重要な位置づけになっていないか?」が問われます。
たとえば、次のようなケースでは許可されにくくなります:
- 除外対象地が、地域の認定農業者などに賃貸されており、すでに営農に使われている
- 地域の農地集積計画の中で、重点的に保全・活用されているエリアに含まれている
市町村としては、こうした担い手農家の安定経営や農地の集約化を最優先とするため、申出が地域農業に“水を差す”ような内容であれば、厳しくチェックされるのです。
要件4:農業施設への悪影響がないこと ― 水路や農道に影響していませんか?
【法的定義】
「農用地の保全または利用のために必要な施設(用排水施設、農道など)の機能に支障を及ぼすおそれがないこと」(農振法第13条第2項)
【わかりやすく言えば】
「水路や農道といった農業に欠かせないインフラに悪影響が出ませんか?」という視点で審査されます。
たとえば、以下のような点がチェックされます:
- 建物を建てたことで水はけが悪くなり、水路に泥やゴミが流れ込まないか
- 工事によって農道が使えなくなったり、農機が通行しづらくならないか
- 計画地が水路や農道と接している場合、それらの維持管理に影響を与えないか
必要に応じて、排水計画や影響回避策の図面提出、施設管理者(例:土地改良区)との事前協議が求められることもあります。
要件5:土地改良事業への影響がないこと ― 整備されたばかりの農地ではありませんか?
【法的定義】
「当該農用地が、国または都道府県の補助を受けて行われた土地改良事業の完了年度の翌年度から起算して8年を経過していること」
【わかりやすく言えば】
「最近、税金で整備された農地をすぐ宅地などに変えてしまうのはNGですよ」というのがこの要件の趣旨です。
土地改良事業とは、圃場整備・暗渠排水・区画整理など、農業の生産性向上のために行われる公共事業です。こうした事業が入った農地は、原則として8年間は農業以外の用途への利用が認められません。
そのため、申出地に土地改良事業の履歴がある場合は、
- 事業の完了年度
- 農地台帳や土地改良区の資料による確認
- 必要に応じて除外適用除外(特例)申請の可能性
など、慎重な確認と対応が求められます。
3. 農振除外申請に必要な書類一覧 ― 準備は「証拠集め」から始まる
農振除外の申出では、単に「申請書を出せばOK」というわけではありません。申出理由の正当性を裏付けるため、さまざまな書類を収集・作成する必要があります。
これらの書類は、まさに“許可のための証拠資料”です。ここでは、一般的に求められる標準的な書類を一覧形式で整理し、取得先や作成時のポイントもあわせてご紹介します。
※実際に必要な書類は自治体によって若干異なるため、必ず事前に確認してください。
📌【基本的に必要な書類】
| 書類名 | 内容と目的 | 主な取得先 | 注意点・作成ポイント |
|---|---|---|---|
| 農用地区域除外申出書 | 申出の意思を正式に表す主たる申請書類 | 市町村の農政課 | 自治体指定の様式を必ず使用 |
| 申出理由書(事業計画書) | 5つの要件をクリアしていることを説明する最重要資料 | 申請者自身が作成 | 後述の「書き方のコツ」を必ず参照 |
| 登記事項証明書(登記簿謄本) | 土地の権利関係、地目、面積を確認 | 法務局 | 発行後3ヶ月以内の原本が必要 |
| 公図の写し | 土地の形状と隣接地との関係を確認する図面 | 法務局 | 隣接地の情報が必要な自治体もある |
| 位置図(案内図) | 申出地の場所が第三者にも分かるように示す地図 | 申請者作成 | 地図上に赤枠などで申出地を明示 |
| 配置図(土地利用計画図) | 建物・駐車場・出入口・排水の位置を記した図面 | 設計事務所または申請者 | 具体性・周辺配慮を示す重要資料 |
| 代替地検討資料 | なぜ他の土地では代替できないのかを示す資料 | 申請者作成 | 表形式で候補地と不適理由を整理 |
📌【場合によって求められる追加書類】
| 書類名 | 内容と目的 | 主な取得先 | 注意点・作成ポイント |
|---|---|---|---|
| 資金計画書・融資証明書 | 計画の実現性(資金の裏付け)を証明 | 金融機関・申請者 | 預金残高証明・融資内定通知などを添付 |
| 隣接地所有者の同意書 | 計画による近隣トラブルを防止する | 申請者作成 | 提出義務はないが、多くの自治体で推奨 |
| 土地改良区の意見書(同意書) | 水利施設への影響を確認・同意を得る書類 | 各土地改良区 | 協議のうえ、場合によって決済金が発生 |
| 関連する他法令の許可見込み書類 | 他の事業許可が前提となる場合の補足資料 | 関係行政庁・申請者 | 該当する事業計画がある場合のみ提出 |
📝ワンポイントアドバイス
農振除外の審査は、書類の整合性と説得力が大きなカギを握ります。特に申出理由書と代替地検討資料は、審査担当者の判断を左右する“核心資料”となるため、単なる形式的な記述にとどめず、根拠を示してロジカルに構成することが重要です。
また、配置図や排水計画図などの図面は、専門の設計事務所に依頼することで、より高い信頼性と審査通過率が期待できます。
4. 農振除外はすぐには終わらない ― 手続きの流れと想定スケジュール
農振除外の申出は、思い立ったその日に申請できるような手続きではありません。
審査には関係機関との協議や、公開手続(公告・縦覧)を含む複数のステップがあるため、事前の準備とスケジューリングが非常に重要です。
この章では、一般的な手続きの流れと、実際にどのくらいの期間を見込むべきかを解説します。
📋 申請から許可までの標準的な流れ
| ステップ | 内容 | 補足 |
|---|---|---|
| ① 事前相談 | 市町村の農政課に計画の概要を相談 | 除外の可能性や課題を早期に把握 |
| ② 書類の収集・作成 | 必要書類(第6章参照)の準備 | 設計図面や理由書の作成に時間を要する |
| ③ 申出書の提出 | 年に1〜2回の受付期間内に申請 | 最重要:締切を逃すと次回まで半年〜1年待ち |
| ④ 関係機関との調整・審査 | 農業委員会、土地改良区、都道府県との協議 | 最も時間がかかるフェーズ |
| ⑤ 公告・縦覧 | 市町村が計画変更案を公告し、一般に公開 | 通常は30日間。意見書提出も可能 |
| ⑥ 計画変更の決定通知 | 市町村長が農業振興地域整備計画の変更を告示 | 申請者に正式に通知される |
⏳ 全体スケジュールの目安:半年~1年以上の長期戦
多くの自治体では、農振除外の申請受付は「年1回〜2回(多くは夏・冬)」に限られており、申請タイミングを逃すと次のチャンスまで数ヶ月~1年待つことになります。
また、提出後も関係機関との協議や公告・縦覧期間などを含めると、許可が下りるまで半年~1年以上かかるのが一般的です。
🕰️【実務的な目安】
- 今すぐ相談 → 書類作成(1〜2ヶ月)
- 次回申請受付まで待機(0〜6ヶ月)
- 審査・協議・公告(約6ヶ月)
→ トータルで1年〜1年半
✅ 余裕あるスケジュール設定を
農振除外の手続きは、建物の設計や資金調達、農地転用手続きとの兼ね合いもあるため、「いつから使いたいか」から逆算して1年半〜2年程度の計画期間を確保しておくのが安心です。
早めの相談と書類作成の着手が、許可取得までの道のりを大きく左右します。
まとめ ― 農振除外を成功に導くために大切なこと
ここまで、農用地区域(青地)から土地を除外する「農振除外申出」について、制度の趣旨から審査のポイント、必要書類の準備方法まで詳しく解説してきました。
農振除外を成功させるためには、次の4点がとくに重要です。
✅ 押さえておくべき4つのポイント
- 法律で定められた「5つの要件」をすべてクリアすることが絶対条件
特に「代替性の不存在」は最も審査が厳しく、合理的かつ客観的に説明する必要があります。 - 申出理由書は「説得力のあるストーリー」として構成すること
事実をただ並べるだけでなく、生活背景や事業の具体性を丁寧に書き、審査官が納得できる内容に仕上げることが大切です。 - 申請受付のタイミングは限られているため、スケジュール管理が必須
多くの自治体では年1〜2回の受付となっており、提出の遅れは計画全体の大幅な遅延につながります。 - 除外後には「農地転用許可」が控えており、これは別手続きであることを忘れずに
農振除外はあくまで“前段階”であり、本来の目的(住宅建築や事業用地化)には転用許可も必要です。
🧭 一人で抱えず、行政書士と連携を
農振除外は、制度そのものが複雑で、審査基準も明文化されていない部分が多く、自己判断で進めるのは非常にリスクが高い手続きです。
「除外できると思っていたのに申出が却下された」
「準備に半年かけたのに受付対象外だった」
といったトラブルも現実に少なくありません。
こうした失敗を防ぐためには、早い段階から行政書士のような農地手続きに精通した専門家と連携し、客観的な視点でのアドバイスを受けることが、もっとも確実な道です。