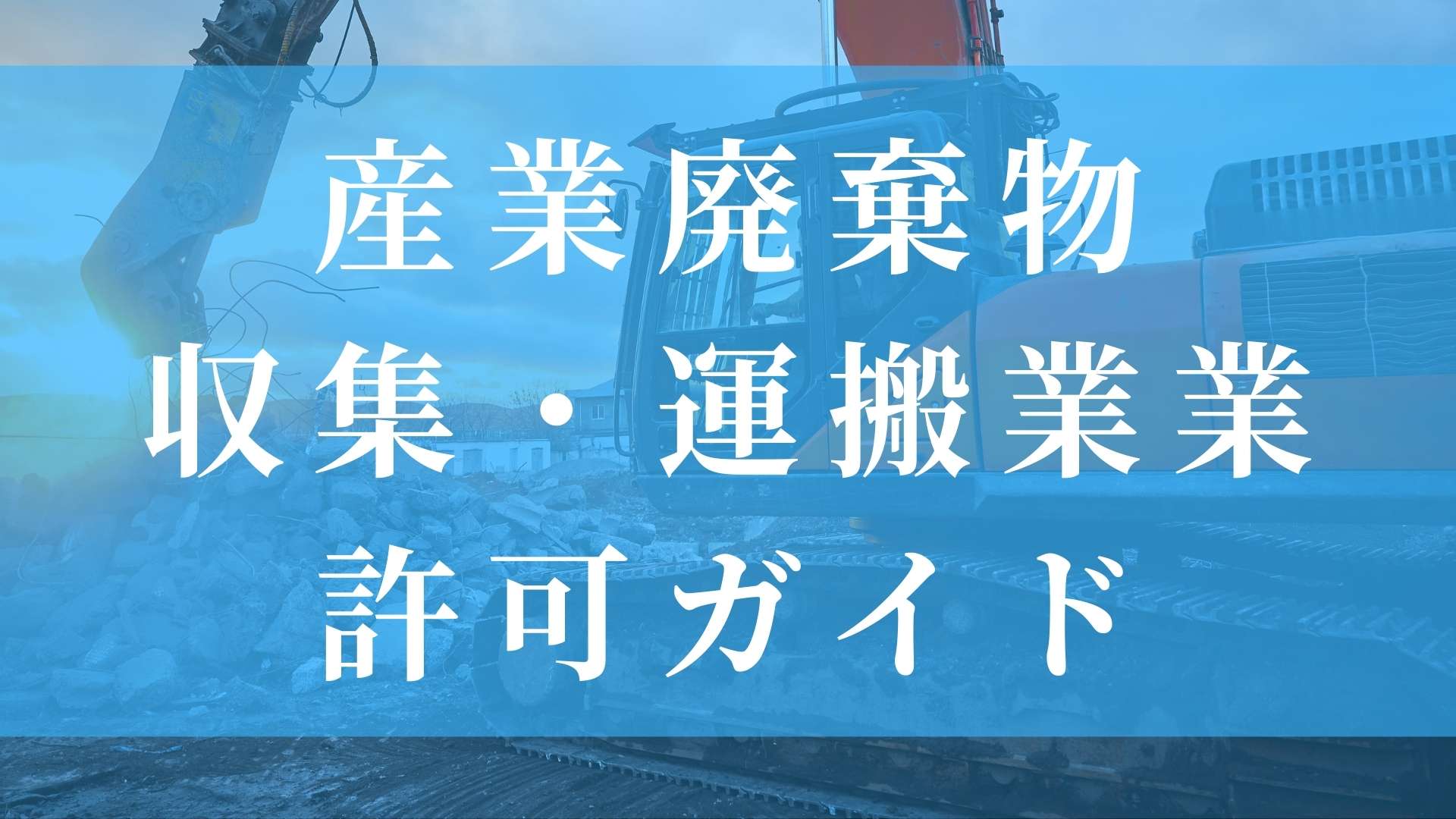こんにちは、行政書士の三澤です!
「産業廃棄物収集運搬業の許可を取りたい」「でも講習会って何をすればいいの?」
そんな疑問やお悩みを感じていませんか?
この記事では、
・建設業者として自社で産廃を運べるようにしたい方
・許可取得を検討しているが講習会の存在を最近知った方
・忙しくて講習の申し込みや受講の準備が後回しになっている方
といった方に向けて、「講習会受講の手順と注意点」について、初めての方でもわかりやすいよう実務の視点で丁寧に解説していきます。
この記事でわかること
- 講習会がなぜ必要なのか(法的義務と背景)
- 誰が受ければいいのか(役員?従業員?)
- どうやって申し込むのか(注意点や失敗例)
- よくあるトラブルの回避法
「うちでも取得できるの?」「まず何をすればいいの?」と迷われている方の道しるべとなるよう、ポイントを絞ってご紹介します。
それでは、さっそく見ていきましょう!
なぜ講習会が必要なのか?(義務の背景と失敗リスク)
産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するには、「講習会の受講」が法律で義務づけられています。これは単なる“お勉強”ではなく、廃棄物処理法に基づく法的な許可要件です。特に次のような場面で修了証が必要になります。
- 新たに許可を取得するとき(新規)
- 許可の有効期限が切れる前に更新するとき(更新)
- 特定の事業範囲を拡大・変更するとき(変更)
そして講習会を受講し、試験に合格すると「修了証」が交付されます。この修了証を提出できない場合、申請は受理されず、許可が取れない=事業ができないという致命的な結果につながります。
意外と多いのが、「講習会って必要なんですか?」という質問。実務的には、「知らなかった」では済まされません。講習会の受講は、廃棄物処理を行う者として最低限の知識と責任感を持っているかを判断するための“入口チェック”なのです。
つまりこんな状態では、ビジネスチャンスどころか、営業継続すら危うくなります。
- 修了証を持っていない=法的に適格性がない
- 修了証が有効期限切れ=更新もできない
だからこそ、講習会の計画と受講は、許可取得の最重要ステップだと理解しておく必要があります。
誰が受けるの?受講対象者のルール
産業廃棄物収集運搬業の許可を取るには、講習会を「誰が受けるか」が非常に重要です。適切な人が受講しなければ、せっかく講習会を修了しても許可は下りません。
法人の場合
法人が許可を取る場合、講習会の受講対象者は以下のいずれかです:
- 代表取締役などの役員(監査役は除く)
- 政令使用人(法令上の地位に基づき、契約を締結できる権限を持つ者)
例えば、本社以外の営業所で契約を取り扱う支店長なども、政令使用人に該当すれば受講者として認められます。ただし、その場合は「この人が政令使用人です」とわかる書類(辞令・組織図・健康保険証など)の添付が求められることもあります。
個人事業主の場合
基本的には、事業主本人が受講する必要があります。個人でも政令使用人を立てることは可能ですが、実務上は本人が受けるケースが大半です。
注意点|間違った人が受けても許可は下りない!
講習会は、誰が受けても許可申請に使えるわけではありません。たとえば、現場の若手社員が受講しても、その人が役員や政令使用人でなければ、修了証は許可要件として「無効」となります。
つまり、「誰に講習を受けさせるか」は、許可が取れるかどうかに関係しているということです。
社内の誰を受講させるか迷っている方は、行政書士に相談してから決定するのが安心です。
講習の種類と有効期限の違い(新規・更新・変更)
産業廃棄物収集運搬業に関する講習会には、大きく分けて3つのパターンがあります。申請の種類や目的に応じて、受講すべき講習の内容も変わってきます。
新規講習(新たに許可を取る場合)
初めて産廃の収集運搬業の許可を取る場合には、「新規講習」の受講と修了が必要です。この修了証の有効期限は5年間。申請日現在で有効なものである必要があります。
更新講習(許可の更新時)
すでに許可を持っていて、5年ごとの更新をする場合には、「更新講習」の受講が求められます。ただし注意点があり、更新講習の修了証は2年間しか有効ではありません。これが意外と落とし穴です。
「5年に1回更新するから、その直前に受ければいい」と思っていると、修了証の有効期限が切れていて申請できない、という事態が起こりえます。
更新講習を受けるタイミングは、許可の有効期間が切れる日の“2年前以内”に収まっていなければなりません。
変更申請でも講習が必要なケースがある
事業内容に大きな変更を加える場合(例:石綿含有廃棄物を扱う、積替え保管をするなど)は、「変更許可申請」が必要です。このときも、状況によっては改めて講習会の修了証が求められることがあります。
また、社内で修了証を持つ人物が退職してしまった場合、新たな受講者を立てて再度講習を受けてもらわなければ、申請自体が受理されないこともあるため注意が必要です。
このように、申請内容や組織の体制によって、必要な講習の種類や有効期限が異なります。講習スケジュールの遅れは、許可の遅れ=営業機会の損失にもつながるため、余裕をもった計画が不可欠です。
講習会の申し込み手順【オンラインが主流】
講習会の申し込みは、現在はJWセンターのオンライン申込が基本となっています。紙の申込書は原則廃止され、インターネットを利用した手続きが中心です。
ステップ①:JWセンターの専用ページにアクセス
JWセンター(日本産業廃棄物処理振興センター)の公式サイトから、「講習会・研修会申込」ページへ移動します。希望する講習の種類(新規 or 更新)、開催地、日程、形式(オンライン or 対面)を選びます。
ステップ②:マイページ作成&顔写真アップロード
受講者本人の情報(氏名・生年月日など)を入力し、「マイページ」を作成します。マイページには、顔写真(JPEG形式)のアップロードが必須です。
写真のサイズや背景に指定があります。不備があると受付されないため注意!
ステップ③:受講料の支払い
申し込み完了後、仮受付メールが届きます。支払い方法(クレジットカード・コンビニ・銀行振込)を選択して、期日までに受講料を支払います。
ステップ④:受講票の印刷と当日の準備
支払いが完了すると「正式受付」となり、マイページから受講票がダウンロード可能になります。当日はこの受講票を印刷して持参しましょう。
よくあるミスと注意点
- 写真データが規定外でアップロードできない
→ 推奨サイズや背景色に注意。不安な場合は撮影サービスを利用するのも手。 - 支払い期限を過ぎてしまう
→ 仮受付が無効になり、最初からやり直しに。メールを見逃さないよう注意! - 受講者が適格者でない(役員以外など)
→ 誰が受けるかは事前にしっかり確認!無効な受講にならないよう注意が必要です。
このようなミスは、行政書士に依頼すれば事前に防げるケースも多くあります。「パソコン操作が苦手」「書類が不安」という方は、ぜひご相談ください。
受講形式の違い:オンライン vs 対面
現在の講習会は、オンライン形式と対面形式の2種類から選べるようになっています。それぞれにメリット・デメリットがあるため、スケジュールや受講者の特性に合わせて選択することが大切です。
オンライン形式|時間の自由度が高いが自己管理がカギ
- 講義は動画配信:試験日までに、自分の好きな時間に何度でも視聴可能
- 講義後に会場で試験:受講自体はオンラインでも、修了試験は指定会場で受ける必要があります
- 受講料が安め:対面よりも数千円程度安い傾向あり
自宅や職場で空き時間に受講できるので、時間の都合がつきにくい方にはおすすめ。ただし、視聴を後回しにして忘れてしまわないよう注意……!
対面形式|集中力は高いがスケジュールに制約あり
- 2日間連続で会場受講+試験:講義と試験を一貫して受けられる
- その場で質問できる可能性あり:わからない点をその場で解決できる安心感
- 講義に集中しやすい環境:移動や時間の拘束が逆にメリハリになるケースも
まとまった時間を確保できる方や、自己学習が苦手な方には対面形式がおすすめです。
どちらを選ぶべき?あなたに合ったスタイルの選び方
| 特徴 | オンライン形式 | 対面形式 |
|---|---|---|
| 費用 | やや安い | やや高い |
| 学習スタイル | 自由/繰り返し視聴可 | 集中しやすい |
| スケジュール調整 | 自由(動画視聴)+試験日 | 丸1~2日の予定が必要 |
| ネット環境の必要性 | 必須(動画再生+手続き) | 不要 |
| 試験実施方法 | 別日に指定会場で実施 | 会場でそのまま受験 |
講習会の受講形式は、「自分の性格」「今の生活状況」「予算感」を踏まえて選ぶのがコツです。どちらにしても、試験を受けて合格しなければ修了証は出ませんので、どちらが“合格までの道のりをイメージしやすいか”で決めるのも一つの判断軸です。
不安な方は、行政書士と一緒に検討するのもおすすめです。
受講料と費用感、支払い方法
講習会の受講には当然ながら費用がかかります。金額は講習の種類(新規 or 更新)や開催形式(オンライン or 対面)によって異なりますが、以下が大まかな目安です。
受講料の目安
| 講習区分 | 開催形式 | 受講料(税込) |
|---|---|---|
| 新規講習 | オンライン | 約25,300円 |
| 新規講習 | 対面 | 約29,700円 |
| 更新講習 | オンライン | 約16,500円 |
| 更新講習 | 対面 | 約19,800円 |
※特別管理産業廃棄物などの専門講習や処分課程などは別途費用がかかる場合があります。
オンライン形式の方がやや安価ですが、会場での試験参加や通信環境なども含めて判断しましょう。
支払い方法
申し込み完了後に送られてくる「仮受付メール」に従って、以下の方法で受講料を支払います。
- クレジットカード決済
- コンビニ払い
- 銀行振込
支払い期限は厳格に定められており、期日を過ぎると予約が自動キャンセルになるため注意が必要です。
注意点
- 支払い完了後に受講番号が発行され、「正式な予約完了」となります。
- 支払い手続きを行わなかった場合、せっかく入力した情報も無効になってしまうので、仮受付メールは必ずすぐに確認するようにしましょう。
金額だけを見ると「結構高いな…」と感じるかもしれませんが、講習会修了は許可取得の絶対条件です。受講費用=事業のスタートラインに立つための投資と考えるのが良いでしょう。
受講前~当日の持ち物と注意点
講習会をスムーズに受講するには、事前の準備がカギです。特に忘れ物や時間管理のミスは、当日になってからでは取り返しがつかないこともあります。
持ち物チェックリスト
以下は講習会当日に必ず持参すべきものです。
- 受講票(マイページから印刷)
- 本人確認書類(顔写真付きのもの。運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 筆記用具(鉛筆またはシャープペンシル、消しゴム)
オンライン講習を選んだ方も、修了試験は指定会場で行われます。講義だけで満足せず、試験まで受けて合格しないと修了証は出ません。
特に本人確認書類は忘れた場合、試験を受けられず「欠席扱い」になることもあります。
時間厳守!遅刻やキャンセルの扱いは厳しい
- 遅刻:講習開始時間に1分でも遅れると入室不可。受講料も返金されません。
- 欠席:連絡なしの欠席は原則返金対象外。やむを得ない場合でも、必ず事前連絡を。
- キャンセル:開催日直前や受講開始後は、キャンセル料(もしくは全額負担)がかかるケースが多いです。
JWセンターは非常に厳格に運用しています。気軽にキャンセル・変更できるセミナーとは違います!
オンライン講義は「視聴完了」が前提
オンライン講習を選んだ場合、試験日までに指定の講義動画をすべて視聴する必要があります。視聴が完了していないと、試験を受けられません。
動画は何度でも見られますが、「試験日までに完了」しておくことが前提条件です。
仕事が忙しい方ほど、講習日から逆算して早めにスケジュールを確保しておくことが重要です。
ちょっとした準備ミスで講習を無駄にしないよう、チェックリストを活用して万全の体制で臨みましょう!
意外な落とし穴:修了証の有効期限と更新時期
講習会で無事に合格して「修了証」を受け取ったら安心…と思っていませんか?実はこの修了証、有効期限があることを知らずにトラブルになるケースが少なくありません。
更新講習は「2年」しか有効じゃない!?
更新講習で取得した修了証の有効期限はわずか2年間。これは、産廃の許可自体が5年で更新なのに対し、修了証の有効期間が短いため、次のような“ズレ”が起こることがあります。
「許可の有効期限があと数ヶ月だから、そろそろ更新講習を受けよう」
→ 修了証の有効期限が切れていて、更新申請に使えなかった! というような事例です。
許可更新の申請では、「更新後の許可開始日から見て2年以内に修了した講習会であること」が必要。つまり、更新日直前の受講では間に合わないこともあるのです。
修了証がまだ届いていないときの“救済措置”的対応
講習会を受けて試験に合格しても、修了証の発行には2〜3週間かかります。その間に申請期限が迫っている場合、どうしたらよいのでしょうか?
自治体によっては、以下のような柔軟な対応をしていただける場合があります:
- 受講票や試験結果通知の写しを提出
- 「修了証が届き次第、提出する」旨の誓約書を添付
このようにすれば、一時的に申請を受理してもらえるケースがあります。ただしこれは自治体によって対応が異なるため、事前に窓口に確認することが必須です。
更新講習の有効期間を正しく管理しておかないと、「せっかく受講したのに無駄になった…」という事態にもなりかねません。カレンダーやタスク管理ツールで定期的に確認し、早めの準備を習慣にしておくことが大切です。
予約できない!?講習会の申込み競争を勝ち抜くには
講習会は年中開催されているとはいえ、予約の争奪戦が激しい時期や地域があります。特に注意が必要なのは、4月〜7月の繁忙期と、名古屋市などの都市部です。
なぜそんなに混み合うの?
- 4月〜6月は新年度のスタート時期で申し込みが集中しがち
- 大都市は受講希望者が多く、席数があっという間に埋まる
- 一部の講習は年に数回しか開催されないため、逃すと数ヶ月待ちになることも
「そろそろ取っておこうかな…」と考えているうちに満席になり、希望時期に許可申請ができないというケースがよくあります。
対策①:講習日程は3月頃からチェック!
JWセンターの翌年度の講習スケジュールは、例年3月下旬ごろに公開されます。出たタイミングですぐに確認・仮予定を立てておくことが肝心です。
対策②:他県での受講も選択肢に
講習会は全国共通の内容と修了証なので、受講地に縛りはありません。地元が満席の場合は、
- 近隣県(静岡、三重、岐阜など)
- 地方都市(意外と穴場)
での受講を検討することで、早期取得につながります。ただし交通費や時間も考慮に入れましょう。
対策③:行政書士にスケジュール管理を依頼する
講習予約・申請・スケジュール管理まで一括して対応してくれる行政書士に依頼すれば、「気づいたら間に合わない…」という失敗を防げます。
講習予約の遅れは、許可取得そのものを大幅に遅らせてしまうリスクがあります。「準備8割」のつもりで、余裕を持った計画を立てておきましょう。
まとめ
産業廃棄物収集運搬業の許可取得において、“準備8割”は講習会の確保から始まっていると言っても過言ではありません。
受講者の選定、申し込み手続き、受講、試験合格、修了証の受領といった一連の流れのどこかでミスが起きれば、その後の申請全体が滞ってしまいます。
しかし、そうした手間や不安をすべて引き受けてくれるのが、行政書士という専門家の存在です。
「本業に集中したい」「手続きのことで悩みたくない」「確実に許可を取りたい」
そんな方には、講習から申請までトータルで支援できる行政書士に任せるのが、最も合理的かつ効率的な選択となります。
産業廃棄物に関する手続きで、こんなお悩みはありませんか?
- 初めての許可申請で何から始めていいかわからない…
- 行政の説明が複雑で、自分に当てはまるか不安…
- 元請業者から手続きや登録を求められて困っている…
そんなときは、建設系産業廃棄物処理業界出身の行政書士が対応する 三澤行政書士事務所にぜひご相談ください。
当事務所は、愛知県を中心に中小企業・個人事業主の建設業者様をサポートしており、 許可申請から更新・変更届、関連する各種制度(例:CCUSや経審など)まで幅広く対応可能です。
まずはお気軽にご連絡ください。