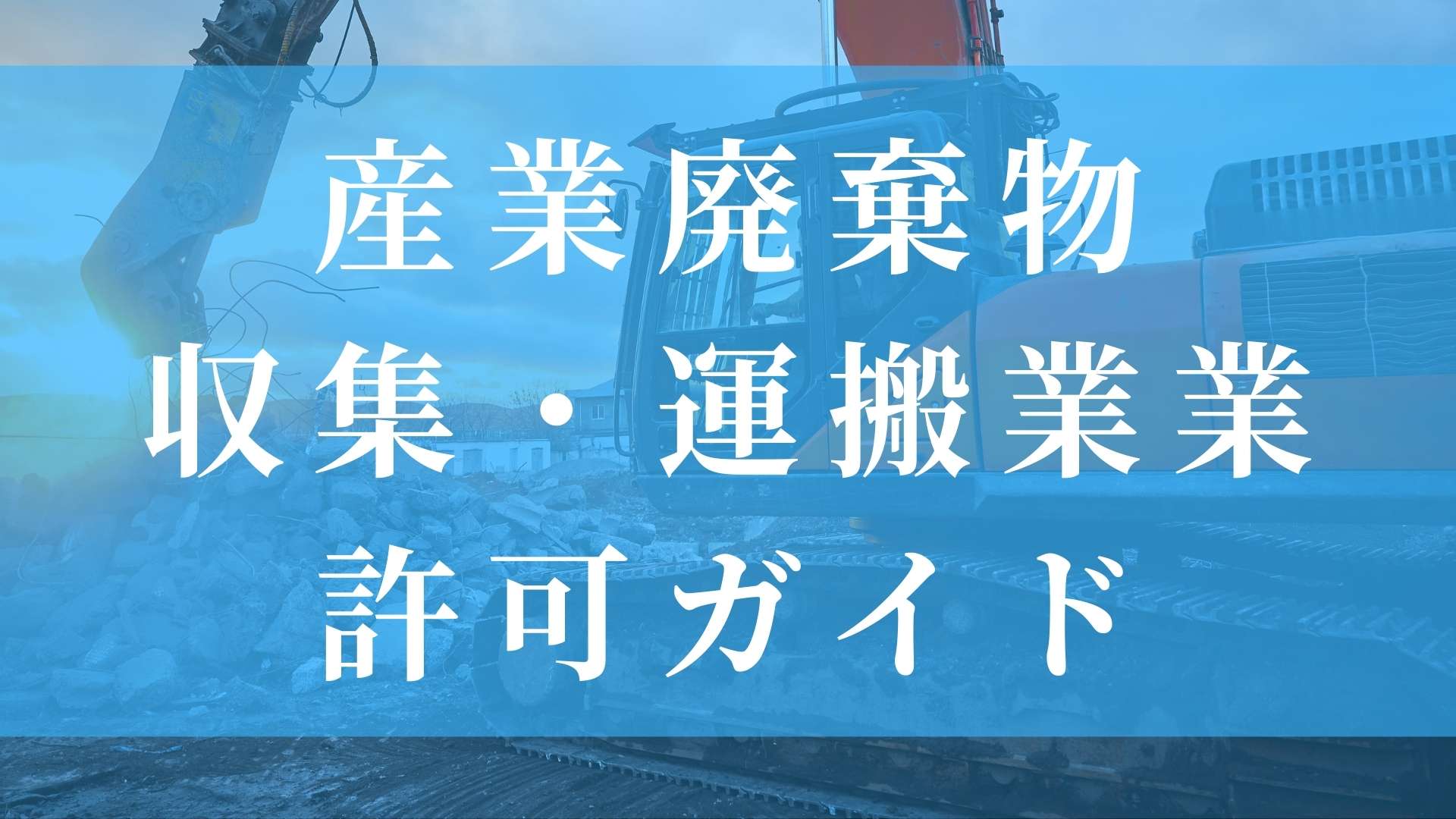こんにちは、行政書士の三澤です!
「そろそろ産業廃棄物収集運搬業の許可を取ろうか」「でも何から始めればいいのか分からない…」
そんな疑問やお悩みを感じていませんか?
この記事では、
・建設業として、現場で出る廃棄物を自社で運びたいと考えている方
・今後、産廃収集運搬業の許可を取得し、業務の幅を広げたいとお考えの方
・委託のコストを見直し、より柔軟な現場対応を目指したい方
といった建設業の事業者様向けに、「産業廃棄物収集運搬業とは何か?」という基礎から、許可取得に向けた前提知識までを、初めての方でもわかりやすく実務の視点で丁寧に解説していきます。
この記事を読むことで、
・産業廃棄物収集運搬業の基本的な仕組みと法制度の概要が分かる
・建設業者がなぜこの許可を取得する必要があるのか、その背景が理解できる
・自社運搬と許可業者としての運搬の違いと注意点が把握できる
ようになります。
「許可を取るべきかどうか迷っている」「自社の運搬が法的に問題ないか不安」と感じている方の判断材料となるよう、ポイントを絞ってご紹介します。
それでは、さっそく見ていきましょう!
第1章:そもそも「産業廃棄物」ってなに?
建設業で出る“あれ”は産業廃棄物かもしれません
建設現場では、コンクリートがらやアスファルト、木くず、金属くず、廃プラスチック類など、さまざまな廃棄物が発生します。これらは法律上「産業廃棄物」に該当するケースが多く、収集・運搬・処分には厳格なルールが定められています。
そもそも「産業廃棄物」とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法令で定められた20種類に該当するものを指します。建設業に関係の深い主な品目は以下の通りです:
- がれき類(解体現場など)
- 木くず(型枠や足場など)
- 廃プラスチック類(梱包材や養生シートなど)
- 紙くず(段ボールや紙管・図面など)
- 金属くず(鉄筋、配管など)
- 汚泥(掘削工事、洗浄作業など)
これらの廃棄物を「産業廃棄物」として適切に処理しなければ、法律違反になる恐れがあります。
一般廃棄物との違いとは?
「一般廃棄物」とは、家庭から出るごみなどが中心です。一方で、事業活動から出るものであっても、法で指定された20種類に該当しなければ「事業系一般廃棄物」に区分されることもあります。
ポイントは以下の通り:
- 産業廃棄物:法律で指定された20種類。産業廃棄物の収集運搬には原則として許可が必要。
- 一般廃棄物:家庭系+一部の事業系廃棄物。自治体での処理(処理の仕組みが異なる)。
建設業の場合、現場で出る廃棄物のほとんどは「産業廃棄物」に該当するため、収集・運搬には特に注意が必要です。
元請が責任を負う?「排出事業者責任」とは
廃棄物処理法では、「その廃棄物を出した事業者が、自ら責任を持って適切に処理しなければならない」とされています。これを「排出事業者責任」といいます。
建設現場においては、工事を発注者から直接請け負った“元請業者”が、この排出事業者と見なされます。つまり、実際にごみを出したのが下請け業者だったとしても、最終的な責任は元請にあるということです。
許可を持たない下請けに運搬を任せた場合、それが法律違反になるケースもあり得ます。このような背景から、「自社で許可を取って、責任ある処理体制を整えておきたい」と考える建設業者が増えているのです。
次章では、その「収集運搬業」とはどんな制度で、自社運搬と何が違うのかを詳しく見ていきます。
第2章:収集運搬業とは?自社運搬と何が違うのか
許可が必要なケース/不要なケース(自社運搬の注意点)
産業廃棄物の運搬を業として行うには、原則として「産業廃棄物収集運搬業の許可」が必要です。 ただし、自社で出した廃棄物を、自社の車両で自ら処理場へ運ぶ場合は「自社運搬」となり、許可は不要です。
しかし、注意すべきポイントがあります:
- 元請業者でなければ「収集運搬を委託された」と見なされる(=許可必要)
- 収集運搬中も処理基準に従う義務がある(飛散防止・表示・書面携帯など)
- 自社運搬であっても、処理先の施設の受入要件や契約などが必要
つまり、許可が不要だからといってどこへでも自由に運んでよいわけではないという点に要注意です。
許可を持つことでできること/できないこと
許可を取得すると、以下のようなことが可能になります:
できること
- 他の事業者(下請や協力会社など)から排出された産業廃棄物を収集・運搬し、報酬を得る
- マニフェストに基づく収集運搬業務を正規に請け負う
- 積替え保管施設の設置(別途許可が必要)
できないこと(許可があっても)
- 許可品目に記載のない廃棄物の運搬
- 許可区域外の運搬(たとえば他県またぎで未取得区域)
- 許可を取ったからといって処分までできるわけではない(処分業は別許可)
このように、許可によってできることの範囲は広がりますが、許可の範囲外の業務を行えば違法行為になります。
委託の限界と許可取得のメリット(コスト・柔軟性)
現場ごとに収集運搬業者へ委託する場合、
- 毎回の委託契約・マニフェスト発行が手間になる
- 小規模現場では業者が対応してくれないこともある
- 処理費用や運搬費が高くつく場合がある
といった課題があります。
一方、自社で収集運搬業の許可を持てば:
- 少量の廃棄物でも柔軟に対応できる
- 複数現場を横断的に自社で管理できる
- コストダウンにつながる可能性がある
もちろん、取得・維持には車両や講習、財務要件などコストも発生しますが、現場対応力とコスト面のバランスを見て検討する価値は十分にあります。
次章では、実際に収集運搬業の許可を取得するための要件や手続きを詳しく解説していきます。
第3章:許可取得のための条件と手続き
許可の種類(積替え保管あり/なし、品目、エリアなど)
産業廃棄物収集運搬業の許可には、いくつかの分類があります。申請前に、自社がどの範囲で業務を行いたいのかを明確にしておくことが重要です。
- 積替え保管なし:収集して「現場から直接」最終処分場や中間処理場へ運ぶ。比較的一般的で、初めて取得する場合はこちらが多いです。
- 積替え保管あり:いったん自社の保管施設に集めてから再運搬する。施設要件が厳しくなる。
さらに、
- 取り扱う品目ごとに許可が必要(例:がれき類、廃プラスチック類、木くずなど)
- 都道府県(場合によっては政令市)ごとに許可が必要(積込み・積下ろしそれぞれに該当)
建設現場が複数の自治体にまたがる場合、すべての自治体で許可が必要になる点に注意が必要です。
取得に必要な要件(講習・財務・設備・事務所など)
許可を取得するには、以下のような法定要件を満たす必要があります。
1. 講習の修了
- JWセンターが実施する「産業廃棄物収集運搬課程(講習会)」を修了していること
- 法人の場合は、役員や業務執行責任者が対象(基本は社長自身が取得します)。
2. 財務的基礎
- 債務超過でないこと、一定以上の自己資本比率があることなど
- 直近の決算書(3期分)提出を求められる自治体が多いです
3. 適切な設備・施設
- 運搬車両(密閉式・飛散防止構造など)を所有またはリースしていること
- 車両を保管する駐車場、業務を行う事務所を有していること
4. 欠格要件に該当しないこと
- 暴力団関係者でない、過去に法令違反で処分を受けていない など
手続きの流れ(事前相談~申請~許可取得)
愛知県を例にした一般的な流れは以下のとおりです:
- 事前相談(推奨)
- 管轄の県民事務所に相談し、必要書類や自社の要件適合を確認
- 必要書類の準備
- 申請書、定款、決算書、講習修了証、車両情報、誓約書など多数
- 申請書提出・手数料支払い
- 愛知県では、81,000円(積替え保管なし・新規・法人)の手数料(2025年現在)
- 審査・補正対応
- 形式要件・内容確認・補正対応。2~3ヶ月かかることも
- 許可証の交付
- 許可証を受けてはじめて業務開始が可能
なお、申請書の作成や添付書類の整備はかなり煩雑なため、行政書士に依頼することでスムーズに進めることができます。特に初めての方は、事前相談~申請~補正対応まで含めて一括で任せられる体制を整えておくと安心です。
次章では、建設業者が許可を取る際に特に注意すべき現場運用上のポイントを解説していきます。
第4章:建設業者が許可を取るときの現実的な注意点
定款の変更、運搬体制の整備
法人で許可を取得する場合、「産業廃棄物収集運搬業」が定款に記載された事業目的に含まれている必要があります。含まれていない場合は、株主総会での決議・法務局での登記変更が必要です。
また、運搬業務を実際に行うためには、以下のような体制整備が不可欠です:
- 使用車両の選定(運ぶ廃棄物の種類に応じた構造)
- 車両の管理・点検体制の構築
- ドライバーへの廃棄物処理法に関する教育(標識、飛散防止、書類携帯など)
社内での“責任の所在”を明確にし、運搬ルールが日常業務に根づくようにすることが、違反リスクを避ける鍵となります。
廃棄物の区分とマニフェスト運用
「これは何ゴミ?」という判断が曖昧なままでは、処理もマニフェスト記載もズレが生じます。 建設業では、多種多様な廃棄物が発生しますが、それぞれが産業廃棄物としてどの区分に該当するかを正しく把握しておく必要があります。
また、収集運搬業者として処理を請け負う場合、マニフェスト(産業廃棄物管理票)の運用が必須となります。
- マニフェストの記載項目の正確性
- 電子マニフェスト導入の検討(業務効率・コンプライアンス強化)
- 保管義務(5年間)と返却の管理
行政指導の現場では「マニフェスト運用のずさんさ」が違反のきっかけになることも多く、実務担当者への教育・運用フローの整備が求められます。
元請・下請構造との関係
建設業は元請・下請の多層構造になりがちですが、産業廃棄物の処理責任は原則として「元請業者」に一元化されています(排出事業者責任)。
そのため、たとえ自社が下請であっても、「自社で運ぶのが便利だから」といって許可なく産廃を運搬すれば、違法行為に該当する可能性があります。
また元請業者としても、下請に無許可での運搬を黙認すれば、排出事業者としての責任を問われかねません。
こうしたトラブルを避けるためにも:
- 自社が許可業者であるか(範囲・品目・エリア)を明示
- 契約書やマニフェストで元請・下請の責任範囲を明確に
- 必要に応じて、下請けに許可取得を促す
といった対応が求められます。
建設業における廃棄物管理は、「現場任せにしない体制づくり」が何よりも大切です。
第5章:無許可でやってしまうとどうなるか?
無許可運搬・不法投棄の罰則
許可を持たずに産業廃棄物を運搬すると、「無許可営業」として廃棄物処理法違反となり、非常に重い罰則の対象となります。
- 個人:5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(またはその両方)
- 法人:3億円以下の罰金(両罰規定により)
さらに、不法投棄や不法焼却などの行為があった場合、排出事業者(建設業者)側にも責任が問われる可能性があります。
「知らなかった」「下請けが勝手にやった」では済まされず、発注者である元請業者の管理責任が問われます。
責任は逃れられない(排出事業者責任)
廃棄物処理法では、排出した廃棄物について最後の処分までの責任を「排出事業者」が負うことが定められています。
委託先が許可を持っていたとしても、
- マニフェストが不適正に運用されていた
- 許可外の品目を委託していた
- 委託契約書を交わしていなかった といった不備があれば、最終的な責任を排出事業者が問われることになります。
建設業者が収集運搬の許可を取らずに「ついで運搬」をしてしまうと、悪意がなくても違法行為と判断されるケースがあり、リスクは非常に高いといえます。
実際のトラブル事例とリスク評価
以下のような事例が、実際に行政処分や刑事事件として扱われています:
- 無許可の下請業者に運搬を任せた結果、不法投棄され、元請に処理命令が下った
- 委託契約書が不備だったことで「委託基準違反」に問われ、罰金処分を受けた
- マニフェストの返却管理がずさんで、処理の完了を証明できず行政指導を受けた
これらは「想定外」ではなく、日常の現場運営で起こりうる問題です。
したがって、
- 委託先の選定・許可確認を徹底する
- 契約・マニフェスト運用を厳格に行う
- 自社で許可を取得して、安全な処理ルートを確保する
といった予防措置を講じておくことが、法的リスクの回避と企業の信頼維持に直結します。
次章では、委託先として信頼できる業者をどう見極めるか、その具体的なポイントを解説していきます。
第6章:信頼される業者になるには?(他社との差別化視点)
優良産廃業者認定制度とそのメリット
産業廃棄物処理業には、「優良産廃処理業者認定制度」があります。 これは、法令遵守や財務の健全性、環境配慮の取り組みなど、厳しい基準を満たした業者を都道府県等が認定する制度です。
認定されると:
- 許可の有効期間が5年から7年に延長される
- 許可証や名簿に「優良認定マーク」が表示される
- 発注者(元請、自治体、民間企業)からの信頼度が大幅に向上
自社でこの認定を目指すことで、他社との差別化が図れ、仕事の受注にもプラスに働く可能性があります。
行政・取引先からの信頼確保
建設業者として、
- 「許可をきちんと取得している」
- 「マニフェストも正しく運用している」
- 「優良認定まで受けている」
という実績は、元請や行政機関、発注者からの信頼に直結します。
特に、入札参加や公共工事、ゼネコンとの取引では、「コンプライアンスを守っているか」は大きな評価基準です。
「安い業者」ではなく「信頼できる業者」として選ばれるには、許可の取得とその運用が整っていることが欠かせません。
社内管理体制の整備と社外発信(コンプライアンス経営)
信頼される業者になるには、単に許可を取るだけでなく、日常的な管理体制の構築と情報発信がカギとなります。
社内で取り組むべきこと:
- 廃棄物の区分やマニフェスト処理などの教育研修
- 運搬車両・運転者の安全衛生管理
- 苦情・トラブル対応マニュアルの整備
社外へ発信すべきこと:
- ホームページでの許可情報・環境配慮方針の明示
- 優良認定取得や電子マニフェスト対応のアピール
「法令を守って当たり前」から、「選ばれる企業」へ。 そうしたブランディングは、地域の取引先や協力会社との関係強化にもつながります。
まとめ・サポート案内
ここまで、建設業者の皆さまが産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する際に知っておくべき基礎知識から、実務上の注意点、そして信頼される業者になるためのヒントまでを解説してきました。
最後に、あらためて「いまこの許可を検討すべき理由」を整理しておきます。
- コスト削減や柔軟な現場対応につながる可能性がある
- コンプライアンスを強化し、取引先からの信頼を得られる
- 違反リスクの回避や、業務拡大への布石になる
ただし、許可取得には一定の準備期間が必要です。 講習の予約や受講、書類収集、事前相談、申請書作成など、最短でも数ヶ月単位のスケジュールを要するケースがほとんどです。
「そのうち取ろう」と考えていたら、気づけば元請や自治体から「許可あるよね?」と求められた──というケースも珍しくありません。
そうしたトラブルを未然に防ぎ、スムーズかつ確実に許可を取得するには、行政手続きに精通した専門家のサポートを受けるのが効果的です。
産業廃棄物収集運搬業の許可取得で、こんなお悩みはありませんか?
- 初めての申請で、どの書類をどう集めればいいかわからない…
- 自社が対象になるのかどうか、行政に聞いてもよくわからない…
- 元請から「許可が必要」と言われたけど、間に合うか不安…
そんなときは、建設系産業廃棄物業界出身の行政書士が対応する
三澤行政書士事務所にぜひご相談ください。
当事務所は、愛知県を中心に中小企業・個人事業主の建設業者様をサポートしており、
産業廃棄物収集運搬業の許可申請から更新・変更届、講習手配、積替え保管のご相談まで、
実務に即した現場目線でのサポートを提供しております。
まずはお気軽にご連絡ください。
▼ お問い合わせはこちらから