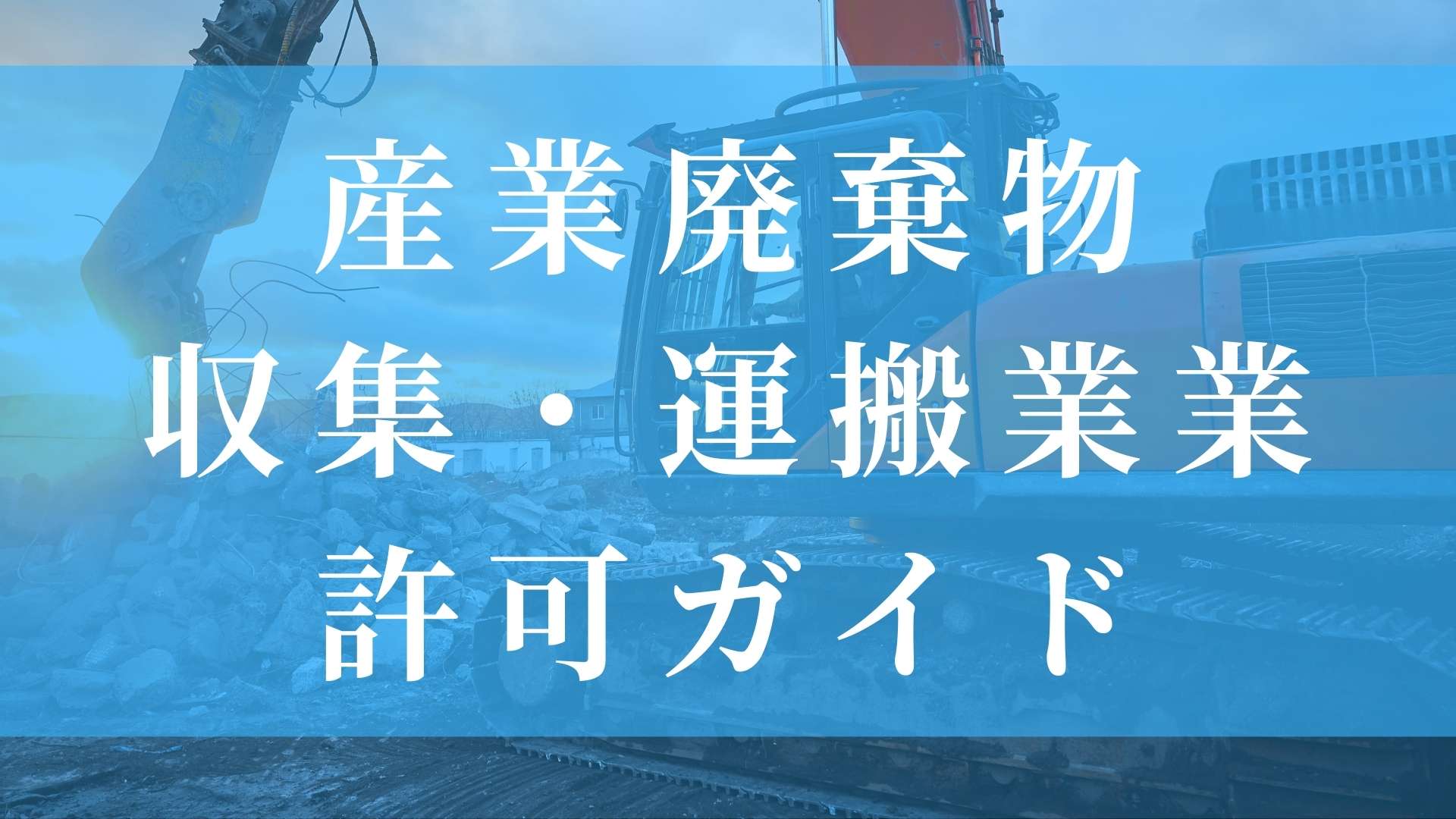こんにちは、行政書士の三澤です!
「うちの会社も産廃の許可が必要なのか…?」 「現場で出たゴミを下請け業者が持ち帰っても大丈夫?」 そんな疑問やお悩みを感じていませんか?
この記事では、
・産業廃棄物収集運搬業の許可が必要かどうか判断に迷っている建設業者の方
・下請け業者に任せている廃棄物処理が本当に合法か気になる現場責任者の方
・今後、元請として産廃の管理体制をしっかり整えたいと考えている方
といった皆様向けに、「産業廃棄物収集運搬業の許可が必要となるケース・不要なケース」について、初めての方でもわかりやすいよう実務の視点で丁寧に解説していきます。
この記事を読むことで、
・自社のケースが許可取得の対象に当たるのかを判断できるようになります
・許可が不要なケースでも守るべき注意点がわかります
・建設現場でありがちな「グレーゾーン」にどう対応すればよいかの考え方が身につきます
「うちでも取得が必要?」「何から始めればいいの?」と迷われている方の道しるべとなるよう、事例を交えてポイントを絞ってご紹介します。
それでは、さっそく見ていきましょう!
第1章|そもそも、産廃収集運搬業の許可って何?
■ なぜ許可が必要なのか?~制度の目的と違反リスク~
産業廃棄物を運ぶには、原則として「産業廃棄物収集運搬業の許可」が必要です。これは、ただの形式的な制度ではなく、環境保全と企業の社会的責任に直結する非常に重要なルールです。
もし無許可で産業廃棄物を運んでしまった場合、「知らなかった」では済まされません。5年以下の懲役や1,000万円以下の罰金、さらには法人として3億円以下の罰金が科されることもあり得ます。
また、廃棄物を適正に処理できないまま運んでしまうと、不法投棄や周辺環境への悪影響につながり、企業の信用や工事の受注にも大きなダメージが出る可能性があります。
だからこそ、「うちの会社の運搬行為が許可対象なのか」を正しく見極めることが、事業リスクを回避する第一歩なのです。
■ 「業として行う」ってどういう意味?基礎用語をざっくり解説
許可の要否を判断するカギとなるのが「業として行うかどうか」です。
この「業として」という言葉、法律では“反復・継続して行う意思をもって社会的に活動すること”とされています。つまり、1回限りの無償の手伝いなら該当しない可能性もなくはないですが、
- 複数回行う
- お金をもらって運ぶ
- 請け負った現場でいつもやっている
といった場合は、「業として」にあたり、許可が必要になります。
また、ここで出てくる基礎用語として、次のような点も押さえておくとわかりやすくなります:
- 産業廃棄物:事業活動から出る廃棄物のうち、法律で指定された20種類のもの(例:廃プラスチック類、汚泥、金属くず など)
- 排出事業者:その廃棄物を出したと法的にみなされる事業者(現場で出た=自分のではないケースもある)
- 収集運搬:単に持ち運ぶ行為だけでなく、積み込みや一時保管も含まれる
建設業の現場では、「現場で出たごみは自分のだと思って持ち帰っている」というケースが実はアウトであることも多いのです。
次章では、実際にどのようなケースで「許可が必要になるのか」を具体的に見ていきましょう。
第2章|【必要になるケース】ここに該当したら許可が必須!
■ 他人の産廃を運ぶときは「すべてアウト」
もっとも基本的なルールとして、「他人が出した産業廃棄物を運搬する場合」は、許可が必要です。たとえ無償であっても、何度も行っていれば「業として」扱われ、法律上は完全にアウトになります。
建設業者の方で、「元請のごみを下請が持って帰る」「仲の良い協力会社のゴミをついでに運ぶ」といったケースは、典型的な違反の例です。
■ 元請と下請の関係に要注意!
現場で出る産業廃棄物は、原則として元請業者が排出事業者とされます。そのため、たとえ下請業者自身の作業で出たゴミでも、それを下請業者が運搬すると「他人の産廃の運搬」に該当します。
「自分の作業で出たから自分のごみ」と思いがちですが、これは大きな誤解です。下請業者が無許可でゴミを搬出すると、下請自身だけでなく、元請側も「無許可業者に委託した」として処分対象になりかねません。
■ 委託契約を結んでいるなら、確実に許可が必要
建設現場などで産業廃棄物の運搬を他社に任せる場合、ほとんどが「委託契約に基づく運搬」に該当します。この場合、運搬を受託する事業者は必ず「産業廃棄物収集運搬業の許可」を持っていなければなりません。
委託契約がある時点で、「業として」産廃を扱っていることが明確なので、許可は100%必要です。もし契約を結んだ相手が無許可業者だった場合、契約を結んだ側(排出事業者)にも責任が及びます。
■ 都道府県をまたぐ運搬は、両方の許可が必要
もうひとつ重要なポイントが「運搬ルートの都道府県」です。産業廃棄物を別の県へ運ぶ場合、積み込む県と積み下ろす県の両方の許可が必要になります。
たとえば「名古屋の現場で積んで、三重の処理場に運ぶ」ようなケースでは、愛知県と三重県の両方で産業廃棄物収集運搬業の許可を取得していなければなりません。
複数エリアで建設工事を請け負っている事業者は、運搬先の自治体ごとに許可が必要になるため、営業エリアに応じて許可管理をしっかり行う必要があります。
次章では逆に、「許可が不要」となるケースについて見ていきましょう。
第3章|【不要なケース】例外もあるが注意が必要
■ 「自社運搬」なら許可はいらないが要注意
産業廃棄物収集運搬業の許可が不要となる典型的な例が、「自社運搬」です。これは、自分の会社が排出した廃棄物を、自社の車両で運搬するケースです。
たとえば、工場や建設現場から出た廃棄物を、自社の保管施設や処理場へ運ぶような場合がこれにあたります。このような運搬は「他人の廃棄物を運ぶ」ことにはならないため、許可は不要です。
ただし注意すべきは、「許可がいらない=何をしても自由」ではないという点です。以下のようなルールはしっかり守る必要があります:
- 飛散や流出が起きないように適切に運搬する
- 車両の側面に自社名と「産業廃棄物収集運搬車」である旨の表示をする
- 運搬する廃棄物の種類や量、運搬元と運搬先などを記載した書面を携帯する
これらを怠ると、たとえ許可不要の自社運搬でも行政指導や改善命令の対象になることがあります。
第4章|【グレーゾーン解説】よくある5つの誤解とその答え
■ 親子会社間の運搬は“自社運搬”ではない!
よくある誤解のひとつが「親会社と子会社は同じようなものだから、自社運搬でいいよね?」というものです。
しかし法律上、たとえ資本関係があっても法人格が異なる限りは“別の会社”です。したがって、親会社が子会社の排出した産業廃棄物を運搬すれば、「他人の産廃の運搬」に該当し、収集運搬業の許可が必要になります。
「グループ会社だから大丈夫」と思って運んでしまうと、無許可運搬として処分対象になる可能性があるため要注意です。
■ 協力会社の応援で代わりに運ぶと違反になる?
例えば「今日はA社のトラックが足りないから、うちが代わりに持っていきますよ」と、善意で協力会社の産廃を運ぶことがあるかもしれません。
ですが、他社が出した産廃を代わりに運搬する時点で“業として”の運搬行為に該当します。たとえ無償でも、反復継続的であれば法律の対象です。
こうした“ついで運搬”や“応援運搬”も、原則として許可が必要になるため、事前に確認しておくことが肝心です。
■ 「自分で出したから持ち帰る」は本当に大丈夫?
建設現場で多いのが、「自分の作業で出たごみだから、自分で持ち帰ります」というケースです。
しかし実は、建設現場では原則として“元請業者”が排出事業者とされるため、たとえ作業したのが下請けであっても、その廃棄物は元請のものと見なされます。
つまり、下請けがそのまま持ち帰ると「他人の廃棄物の運搬」として許可が必要になります。元請側も無許可業者に委託したと判断されれば責任を問われるため、十分な注意が必要です。
■ 廃棄物か有価物か?その判断が命運を分ける
廃棄物処理法の適用を受けるかどうかは、「それが廃棄物か、有価物か」で大きく変わります。
ポイントは、
- 処分費用がかかるかどうか(逆有償)
- 継続的な取引実績があるか
- 汚損・劣化がなくリサイクル可能か
などの複数要素を踏まえた総合判断が必要です。
例えば、「まだ使える資材を知り合いの業者に譲渡する」というような場合は有価物と評価される余地もありますが、単に処分するしかないゴミを「有価物だから大丈夫」として運ぶと、偽装有価物として違法になる恐れがあります。
■ 敷地内での移動はどこまでがセーフ?
最後に、工場や現場などの敷地内での移動について。
産業廃棄物を同一敷地内で運ぶだけであれば、収集運搬業の許可は不要です。例えば工場内で積み替え場所へ移動したり、敷地内保管施設まで台車で運んだりするのは問題ありません。
しかし、公道を少しでもまたぐと、それは「運搬」に該当し、許可が必要になる可能性があります。また、敷地内であっても飛散・流出・悪臭などのトラブルがあれば、別の行政指導を受けることも。
「境界を越えるか」「運搬として見なされるか」を慎重に見極める必要があります。
次章では、こうしたグレーゾーンの運搬行為が発覚した場合に、どのようなリスクや処分が待っているのかを事例をもとに解説します。
第5章|【知らなかったでは済まない】実際の違反事例とその結末
■ 無許可で下請けに運ばせていたら行政処分に
建設現場で非常に多い違反が、「下請け業者が現場の廃棄物をそのまま持ち帰ってしまう」ケースです。
この場合、法律上は元請業者が排出事業者とされますので、下請けがそれを無許可で運搬すれば、下請け業者は無許可運搬、元請業者は無許可業者への委託という二重の違反になる可能性があります。
実際、東京都内の公共工事で、区職員が許可のない下請け業者に廃棄物処理を任せたとして書類送検された事例があります。「違法だとは思わなかった」という職員の言い訳も、当然通用しませんでした。
■ 判例や摘発事例に学ぶ、リスクのリアル
・処分先が無許可業者だった → 委託元企業が罰則対象に
・自社運搬だと思っていたが、実は他社の廃棄物だった → 書類送検
・廃棄物をトラックで野焼きした → 会社代表者が逮捕
これらはすべて、「知らなかった」では済まされない重大な違反です。廃棄物の処理に関しては、排出事業者の責任が最後まで問われるのが法律のルール。
だからこそ、「このケースは大丈夫かな?」と少しでも迷った時点で、行政書士など専門家に相談することが、最大のリスク回避策となります。
次章では、許可の要否に迷ったとき、なぜ行政書士への相談が最適なのかを詳しくご紹介します。
第6章:許可が必要かどうか、自己判断するのは危険です
■ 判断ミスの責任は、最終的に“排出事業者”が負う
ここまで見てきたように、産業廃棄物の収集運搬においては、判断ミスがそのまま法令違反につながります。そして、その責任は最終的に「排出事業者」にあるというのが廃棄物処理法の基本ルールです。
つまり、「下請けが勝手にやった」「ついでに運んでもらった」という言い訳は通用せず、排出事業者自身が処分対象になるのです。
■ 地域によってルールや運用が微妙に違う?
もうひとつ見落とされがちなのが、都道府県ごとの運用の違いです。
廃棄物処理法は全国共通の法律ですが、実際の許可行政は各自治体の知事(または政令市の市長)に任されているため、
- 申請書類の様式や内容
- 審査の厳しさや基準
- 解釈の傾向 などが微妙に異なることがあります。
このため、「ネットで調べた内容」だけで判断してしまうと、実際の地域ルールに合わず、申請が通らなかったり、運搬行為が違法とされてしまう可能性があります。
■ 初回の許可取得に失敗すると再申請が大変
産廃収集運搬業の許可は、初回の取得時に「経理的基礎」や「技術的能力」などを厳しく審査されます。
一度不許可になると、次回の申請では「前回不許可となった理由の改善」が求められ、審査がより厳しくなる傾向にあります。場合によっては半年以上、許可取得ができないということも。
だからこそ、初回の申請で確実に通すためには、専門家の支援を受けることが極めて重要です。
■ 正確な判断と許可取得は、行政書士に任せるのが合理的
- 自社の廃棄物運搬が許可対象かどうか判断したい
- 許可が不要でも、どんなルールを守る必要があるのか知りたい
- 許可取得にあたって、必要書類や手続きを漏れなく準備したい
そんな方には、ぜひ行政書士への相談をおすすめします。
産業廃棄物に関する手続きで、こんなお悩みはありませんか?
- 初めての産業廃棄物収集運搬業許可申請で、何から始めていいかわからない…
- 下請けや協力会社との関係で、自社の責任範囲が不安…
- 行政の説明が難しくて、自分のケースに当てはまるか判断できない…
そんなときは、建設業と産業廃棄物業界に精通した行政書士が対応する、三澤行政書士事務所にぜひご相談ください。
当事務所は、愛知県を中心に中小企業・個人事業主の建設業者様をサポートしており、 収集運搬業の許可申請から更新・変更届、建設業許可やCCUS、経審対応まで幅広く対応可能です。
まずはお気軽にご連絡ください。
▼ お問い合わせはこちらから