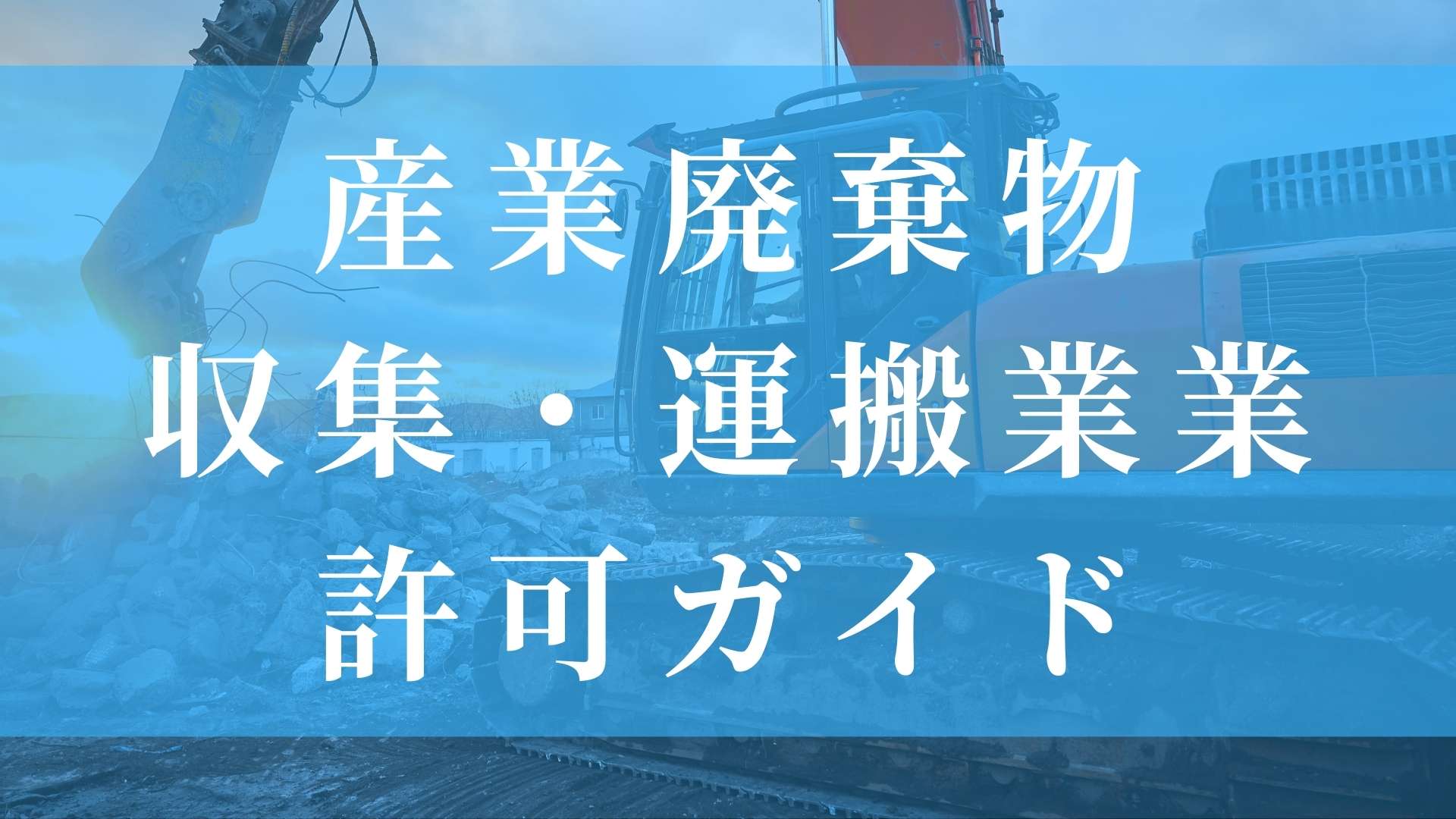こんにちは、行政書士の三澤です!
「積替え保管ってなに?」「積替え保管あり・なし、どっちで許可を取ればいいの?」
そんな疑問やお悩みを感じていませんか?
この記事では、
・産業廃棄物収集運搬業の許可を検討している建設業者の方
・初めて許可を取るけど、制度の違いがよくわからない方
・今後の事業拡大も視野に入れた許可取得を考えている方
といった方向けに、「積替え保管あり・なしの違いと判断基準」について、実務の視点からやさしく解説していきます。
この記事を読むことで、
・積替え保管の意味と法的な違いがスッキリわかる
・自社が「あり」と「なし」どちらの許可が必要なのか判断できる
・許可選びで失敗しないためのポイントが整理できる
ようになります。
「うちでも取得できるの?」「まず何をすればいいの?」と迷われている方の道しるべとなるよう、重要ポイントをギュッと絞ってお届けします。
それでは、さっそく見ていきましょう!
第1章|そもそも「積替え保管」とは?
産業廃棄物収集運搬業の許可には、「積替え保管あり」と「積替え保管なし」の2つの種類があります。 この“積替え保管”という言葉、初めて聞いた方には少し難しく感じるかもしれません。 でも実は、次のようにシンプルに理解できます。
積替えとは?
たとえば、小型トラックで集めた廃棄物をいったん自社の施設で降ろし、大型トラックに載せ替えて処分場に運ぶ──これが「積替え(つみかえ)」です。 車両から別の車両に荷物を移すこと、と考えてもらえばOKです。
保管とは?
収集した廃棄物を、すぐには運ばずに一時的に施設などに置いておく──これが「保管(ほかん)」です。 たとえば、週に一度まとめて運搬するために、数日分の廃棄物を溜めておく場合などが該当します。
どちらか一方でもやれば「積替え保管あり」
そして重要なのが、「積替え」または「保管」のどちらか一方でも行えば、それは“積替え保管あり”の扱いになるという点です。
つまり、
- 一時的にでも廃棄物を施設に置く →「保管」に該当
- 車両から一度降ろして別の車両に載せる →「積替え」に該当
こういったケースでは、「積替え保管あり」の許可が必要になります。
逆に言えば、「積替え保管なし」の許可でこれらの行為を行うと、無許可営業とみなされるリスクがあるので注意が必要です。
次の章では、「積替え保管なし」の許可で実際にできること・できないことを具体的に見ていきましょう。
第2章|「なし」の場合にできること・できないこと
「積替え保管なし」の許可は、もっとも基本的な形の許可です。 手続きや維持コストが比較的軽く、許可取得のハードルも低めですが、その分、できることには明確な制限があります。
できること:直行輸送のみ
許可の範囲内でできるのは、「排出事業場から処分場まで、廃棄物を運ぶこと」だけです。 ポイントは、廃棄物を積んだ車両を途中で止めず、何もせず、ただまっすぐ処分場まで走らせること。 これを“直行輸送”といいます。
できないこと:一時保管・車両乗せ換え・コンテナの長期留置
「少しの間、自社の敷地に置いておこう」 「コンテナに載せたまま駅で一晩待たせよう」 「小さい車から大きい車に載せ替えたい」
──こうした行為はすべてNGです。
これらはすべて「積替え」または「保管」に該当し、「なし」の許可では一切認められていないのです。
「ついでに置いとこう」は違反リスクに直結
実務上ありがちなのが、
- ドライバーの休憩中に会社の車庫に停めておいた
- 受け入れ先の処分場が閉まっていたので、朝まで車に積んだままにしておいた といった“車上保管”のケース。
一見すると「よくあること」に思えるかもしれませんが、時間の長さや常態化の程度によっては“実質的な保管”とみなされる可能性があります。
そして、そう判断された場合は無許可営業として、行政処分や罰則の対象になるリスクも。
「たった一日置いただけなのに…」と後悔する前に、制度の正確な理解が大切です。
次章では、「積替え保管あり」の許可があると何ができるのか、そしてどんな注意点があるのかを解説していきます。
第3章|「あり」のメリットとデメリット
「積替え保管あり」の許可は、少しハードルが高いですが、そのぶん得られるメリットも大きい制度です。 「運搬効率を上げたい」「今後の事業展開に柔軟性を持たせたい」と考える事業者には、非常に有力な選択肢となります。
メリット:運搬効率アップ・大量集約・長距離運搬対応
たとえば、
- 各現場から少量ずつ集めた廃棄物を、いったん拠点で集約して大型車両で処分場へ
- トラックから鉄道や船舶に積み替えて、長距離輸送に切り替える といった使い方が可能になります。
これにより、
- 車両の効率化(少ない便数で多く運べる)
- 輸送コストの削減
- 環境負荷の低減(CO2排出の削減) といった効果が期待できます。
デメリット:施設整備・許可手続きが重い
一方で、「あり」の許可には次のような大きな負担も。
- 施設基準(囲い、掲示板、防臭・防音設備等)の整備が必要
- 保管量や面積に関する細かい上限ルールがある
- 申請には詳細な図面、事業計画、土地の権利関係の書類などが求められる
- 許可にあたっては自治体との事前協議や住民対応が必要になる場合も
つまり、設備投資や行政対応など、手間もコストもかかります。
だけど将来的に事業を広げたいなら「あり」は有力な選択肢
一見ハードルが高いように思える「積替え保管あり」ですが、
- 複数現場を効率よく回る必要がある
- 今後、自治体や元請からより多様な運搬対応を求められそう
- 遠方の処分場を使う必要がある という方には、実は“伸びしろ”のある許可形態です。
最初から無理に取得する必要はありませんが、将来の展開を考えて「いつかはありも…」という視点を持っておくと、事業設計の幅がぐっと広がります。
第4章|判断に迷うケース?
産業廃棄物の運搬は、現場の事情によって様々なケースが想定されます。 そのため、「これは積替え保管に該当するのかどうか」で迷うことも少なくありません。 ここでは、代表的な例を3つ紹介し、注意点を解説します。
コンテナ輸送の例外
基本的に、車両から別の輸送手段に載せ替えると「積替え」に該当します。 ですが、コンテナを利用した輸送においては、密閉された状態で中身に触れずに移動手段を切り替える場合に限り、積替えにあたらないとする例外的な解釈があります。
たとえば、
- コンテナを開けずに、トラックから鉄道貨車へ載せ替える
- 港で船に積み替えるが、中の廃棄物には一切触れない といったケースです。
ただしこの場合でも、
- コンテナが現場で長時間“滞留”していないこと
- 過剰な量を溜め込まないこと など、厳格な条件を満たしていなければ「保管」とみなされる可能性があるため、注意が必要です。
車上保管は“短時間”ならOK?
「処分場が開くまでの間、ちょっと会社の駐車場で待機」──こういったケースは、現実にはよくあります。
このような車両に積んだままの一時的な停車については、
- 業務上やむを得ない短時間の範囲で
- 日常的に繰り返されていない
- 廃棄物の性状が変わらないよう適切に管理している といった条件を満たせば、「保管」とはみなされないと解釈されています。
ただし、
- 定期的に夜間ずっと積んだまま停車している
- 駐車場を事実上の保管場所として使っている といった状態になると、積替え保管と判断される可能性があるため、注意が必要です。
「仮置き」は便利な言葉だが、法的には“保管”かも
現場では「ちょっと仮置きしておこう」と軽く使われがちなこの言葉。 ですが、廃棄物処理法には「仮置き」という特別な免除規定はなく、実態として保管していれば、保管基準の適用対象になります。
たとえば、
- 分別作業のために現場内の一角に置く
- 搬出前に廃棄物を一時的に地面に下ろす といった行為も、掲示板や囲いの設置が求められる保管行為とみなされることがあります。
「仮置きだから大丈夫」と油断してしまうと、思わぬ法令違反につながることも。 「置く」行為には常に慎重な判断が求められます。
第5章|積替え保管ありにする場合のハードル
「積替え保管あり」の許可を取るには、「なし」と比べてはるかに多くの準備と手間がかかります。 ここでは、取得時に注意すべき主な3つのハードルをご紹介します。
1.設備基準(囲い・掲示板・防臭など)
積替えや保管を行うには、そのための施設が必要です。 そしてその施設には、法律で定められた構造基準を満たす義務があります。
たとえば、
- 周囲に囲いがあること(飛散・流出・臭気を防止)
- 掲示板の設置(廃棄物の種類、許可番号、連絡先などを記載)
- 害虫や動物が発生しないための管理(防虫、防鼠)
- 雨水や汚水を処理するための排水設備(油水分離槽など)
といった設備が求められます。 これらを満たしていない施設では、そもそも許可申請を受け付けてもらえません。
2.保管上限(1日平均搬出量の7日分)
保管できる廃棄物の量にも上限があります。 それが「1日平均の搬出量×7日分」というルールです。
たとえば、1日あたり平均で2トンを搬出しているなら、保管できるのは最大14トンまで。 この保管能力を超えてしまうと、違反と判断される可能性があります。
そのため、許可申請の際には、搬入・搬出計画を立てたうえで「保管面積」や「容器の大きさ」などを細かく計算して、図面や書類に落とし込む必要があります。
3.自治体によっては、説明会や近隣同意も必要
積替え保管施設を設けるにあたり、自治体によっては次のようなローカルルールが設けられていることがあります。
- 計画前に事前相談を行うこと(行政との協議)
- 近隣住民への説明会を開くこと
- 同意書を提出すること
- 用途地域(工業地域かどうか等)に関する制限
たとえば名古屋市や愛知県では、手引きの中でこれらの対応が求められることが明記されています。 自治体によっては、事前相談を通じて案内される場合もあります。
これらのハードルをクリアするためには、十分な準備期間が必要です。 また、構造基準や保管ルールに少しでも不備があると、申請が受理されなかったり、許可後に立入検査で是正を求められたりすることもあります。
第6章|実際どう決める?選択のポイント
これまでの章で、「積替え保管あり」と「なし」の違いや注意点を見てきました。 では、実際にどちらを選ぶべきかは、どう判断すればよいのでしょうか? 以下のポイントをもとに、自社に合った選択を考えてみましょう。
今の運搬方法に「途中で降ろす」工程があるか
現在の運搬ルートにおいて、
- 一時的に車庫や倉庫に置く
- 車両を入れ替えて対応する といった“途中で廃棄物を降ろす工程”が少しでもあるなら、「積替え保管あり」の許可が必要な可能性が高いです。
「今は直行しているから『なし』でいい」と思っていても、日常的にちょっとした仮置きや積替えがあると、それが法令違反につながるリスクがあります。
今後、処分場を変えたり拠点を作ったりする可能性はあるか
現在の運搬方法に問題がなくても、
- 新たな処分場との取引を始める
- 車両基地やストックヤードを新設する
- 他県への事業展開を検討している といった“将来的な動き”を視野に入れているなら、「積替え保管あり」を見据えた準備をしておく価値があります。
初めは「なし」で始め、事業の成長にあわせて「あり」へステップアップする方も多いですが、その際には設備投資・再申請・自治体協議などが必要になるため、余裕をもった判断が求められます。
安全に、柔軟に動ける体制にしたいなら「あり」も検討を
「積替え保管あり」の許可を取得すれば、
- 複数の現場を効率よく回れる
- 遠方の処分場にも対応しやすくなる
- 廃棄物の集約・保管ができることでコスト面でも有利になる など、運搬の自由度が一気に高まります。
一方で、申請準備・施設整備・行政対応など、手間もかかります。
許可の選択は、単なる“書類上の分類”ではなく、 事業の可能性をどこまで広げておきたいかという、経営判断でもあります。
最後に|“積替え保管”は事業の未来を左右する判断
「積替え保管あり」と「なし」は、単なる形式の違いではなく、事業の展開力や将来性にも大きく関わる重要な分岐点です。
現在の運搬形態に応じて正しい許可を取得することはもちろん、
- 将来どう事業を広げたいのか
- どの程度の自由度・柔軟性を持たせたいか といった中長期の視点でも判断することが求められます。
とはいえ、制度は複雑で、自治体ごとにルールや運用も異なるため、自己判断で進めるのはリスクが大きいのが実情です。
そんなときこそ、制度を熟知した行政書士に相談することで、
- 無駄な準備を避けてスムーズに進める
- 許可取得後の運用まで見据えたサポートが受けられる
- トラブルリスクを未然に回避できる といった安心感が得られます。
産業廃棄物に関する手続きで、こんなお悩みはありませんか?
・初めての許可申請で何から始めていいかわからない…
・行政の説明が複雑で、自分に当てはまるか不安…
・元請業者から手続きや登録を求められて困っている…
そんなときは、建設系産業廃棄物業界出身の行政書士が対応する
三澤行政書士事務所にぜひご相談ください。
当事務所は、愛知県を中心に中小企業・個人事業主の建設業者様をサポートしており、
許可申請から更新・変更届、関連する各種制度(例:CCUSや経審など)まで幅広く対応可能です。
まずはお気軽にご連絡ください。
▼ お問い合わせはこちらから