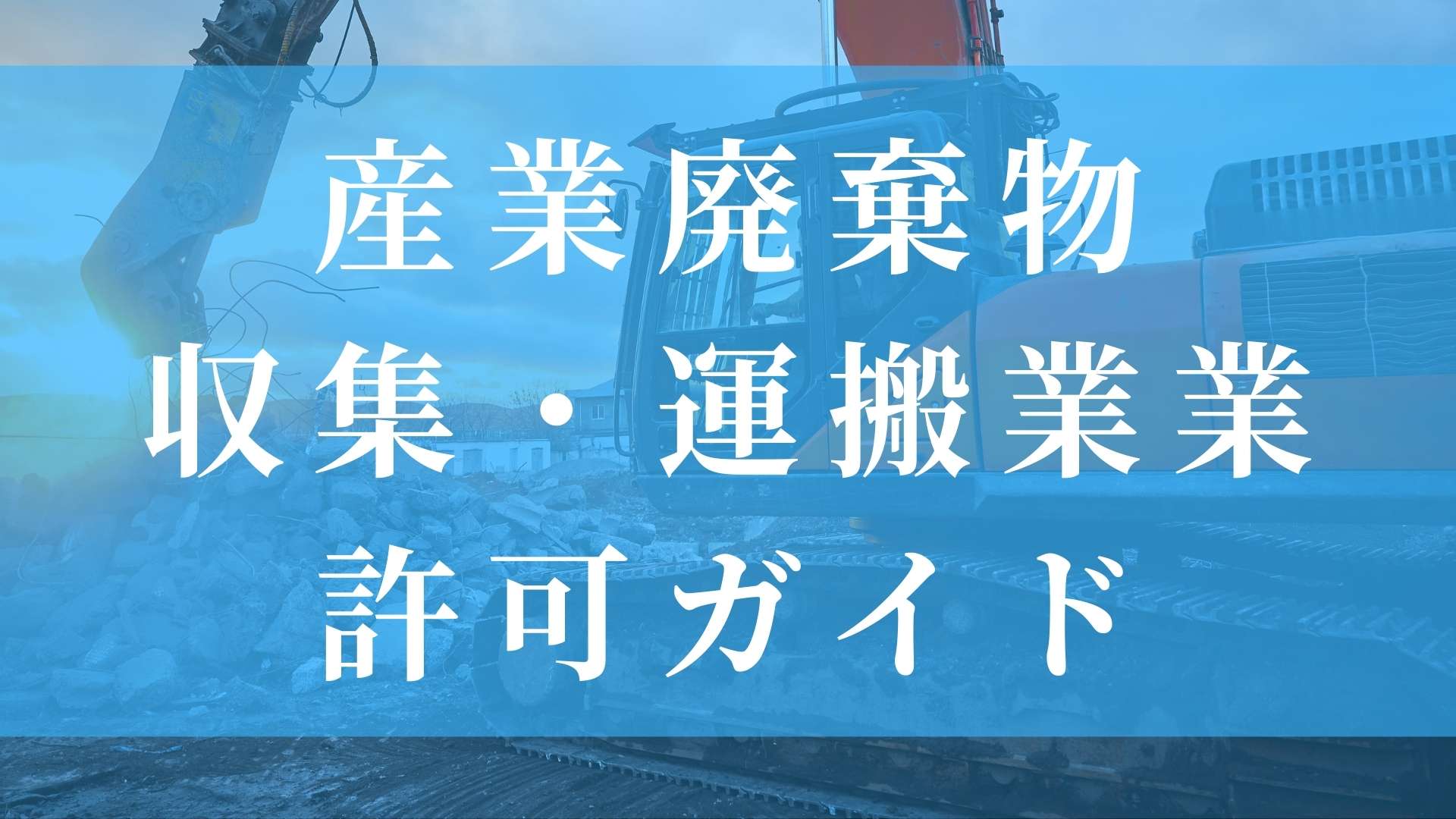こんにちは、行政書士の三澤です!
「産業廃棄物収集運搬業の車両って、どんな基準があるの?」「うちのトラックでも許可を取れるのか不安…」
そんな疑問やお悩みを感じていませんか?
この記事では、
- これから産業廃棄物収集運搬業の許可を取りたい建設業者の方
- すでに車両はあるけれど、使えるかどうか確認したい方
- 表示や書類など、細かいルールに不安を感じている方
といった事業者の方向けに、「運搬車両の基準と表示義務」について、初めての方でもわかりやすいよう実務の視点で丁寧に解説していきます。
この記事でわかること
- 許可を取るためにどんな車両が必要なのか
- 車両にどんな表示をしなければいけないのか
- 守らなかった場合にどんなリスクがあるのか
「うちでも取得できるの?」「まず何をすればいいの?」と迷われている方の道しるべとなるよう、ポイントを絞ってご紹介します。
それでは、さっそく見ていきましょう!
車両選び|使えるのはどんな車両?
▷ 所有・リース・レンタルの違いと注意点
産業廃棄物収集運搬業では、「どの車両を使うか」が実は大きなポイントです。
原則として、事業者自身が正当に使用権を持っている車両でなければなりません。
- 自己所有の車両であれば問題ありません。
- リース車両も、契約により継続的な使用権限があることが確認できれば使用可能です。
一方で、レンタカー(短期レンタル)については注意が必要です。
たとえば「急ぎで車を借りて運搬したい」といった場合でも、許可行政庁への事前確認は必須です。使用権限が不明瞭な車両での運搬は、違反とみなされることがあります。
▷ どんな構造・性能が必要か?
廃棄物運搬車両に求められるのは、「このトラックでなければいけない」という形式指定ではなく、 「この性能を満たしているかどうか」という機能重視の基準です。
以下のように、廃棄物の性状に応じた対策が求められます:
- 粉状の廃棄物 → シートでしっかり覆う/密閉コンテナを使う
- 液体状(廃油・廃酸など) → 漏れ出さないタンク型車両が望ましい
- 汚泥や有害物質を含むもの → 飛散・流出防止のため密閉構造が必須
- 石綿(アスベスト)含有廃棄物 → 破砕防止と分別確保が求められるため、専用容器や運搬方法に注意
これらはいずれも「飛散・流出・悪臭の防止」という目的を達成するための措置です。
つまり、車両の形式よりも、「積む廃棄物に応じた安全な運搬方法をとっているか?」が問われます。
そのため、車両の選定においては、許可申請前に行政書士や専門家と相談することが重要です。 「今あるダンプを使えるのか?」「密閉型に改造が必要か?」といった判断は、早めに明確にしておくのが得策です。
表示義務|「見える化」がコンプライアンスの第一歩
▷ 表示すべき内容
産業廃棄物を運ぶ車両には、外から見てすぐにわかるように、いくつかの情報を車両の両側面に表示する必要があります。
表示すべき内容は以下の通りです:
- 「産業廃棄物収集運搬車」という表示
- 業者名(正式名称)
- 許可番号(許可業者の場合のみ)
※自己運搬(自社で出た産業廃棄物を自社で運ぶ場合)の場合、許可番号の表示は不要です。
この表示により、誰が、どんな立場で廃棄物を運んでいるのかを、外から確認できるようにしています。
▷ サイズ・色・表示位置のルール
表示内容が決まっているだけでなく、そのサイズ・色・位置にも細かいルールがあります。
- 「産業廃棄物収集運搬車」:文字の大きさ140ポイント以上(約5cm角)
- 業者名や許可番号:90ポイント以上(約3cm角)
- 車両の両側面の見やすい位置に、対照的な色で表示すること(例:白い車体に黒文字)
- マグネットシートやステッカーでの貼付もOKですが、走行中に剥がれないよう確実に取り付ける必要があります
手書き表示や文字が小さすぎる表示はNGです。 また、積載物やシートで表示が隠れてしまうと、それも違反とみなされます。
▷ 表示ミスのリスク
「ちょっとぐらい表示が小さくてもいいでしょ」と油断していると、路上検査で一発アウトです。
- 表示が不鮮明
- 許可番号の記載ミス
- 表示位置が見えづらい
といった「形式違反」でも、改善指導や行政処分の対象になります。
繰り返し違反が続いた場合には、改善命令や事業停止命令、さらには許可取消という厳しい対応がなされるケースもあります。
表示義務は一見すると「形式的なもの」に見えますが、 行政から見れば、違反をしている事業者を“見分ける”ための重要な手段なのです。
だからこそ、「ちゃんと見える」「ちゃんと正しい」表示を常に心がけましょう。
▷ 表:車両表示義務の比較(許可業者 vs. 自己運搬)
| 表示項目 | 許可業者(収集運搬業者) | 自己運搬(排出事業者) | 根拠規定(参照) |
|---|---|---|---|
| 目的表示 | 「産業廃棄物収集運搬車」 | 「産業廃棄物収集運搬車」 | 施行規則 第7条の2の2 第1項第1号、第3号 |
| 氏名又は名称 | 許可を受けた者の氏名等 | 排出事業者の氏名等 | 施行規則 第7条の2の2 第1項第1号、第3号 |
| 許可番号 | 必要(下6桁以上) | 不要 | 施行規則 第7条の2の2 第1項第3号 |
| 文字サイズ(目的表示) | 140ポイント(約5cm以上) | 同左 | 施行規則 第7条の2の2 第1項 第11号 |
| 文字サイズ(氏名・番号等) | 90ポイント(約3cm以上) | 同左 | 施行規則 第7条の2の2 第1項 第11号 |
| 表示位置 | 車両の両側面 | 同左 | 施行規則 第7条の2の2 第1項 第4号 |
| 表示方法 | 鮮明に表示(マグネット等可) | 同左 | 施行規則 第7条の2の2 第1項 第10号 |
| 色 | 識別しやすい色 | 同左 | 第11号(一般的な行政解釈による) |
書類の携帯|車検証と同じくらい大事です
車両に表示をするだけでは不十分です。車内に書類を備え付けておくことも義務となっています。
▷ 許可業者が携帯すべき書類
- 産業廃棄物収集運搬業許可証の写し
- マニフェスト伝票(紙)
- または電子マニフェスト加入証と、受渡確認票などの書面(または電子データ)
特にマニフェストの不備や許可証の不携帯は、路上検査で頻繁に指摘される違反ポイントです。 ドライバーがその場で提示できるよう、常に最新版を携帯しておきましょう。
▷ 自己運搬(自社で排出した廃棄物を自社で運搬)の場合
以下の内容を記載した書面の携帯が必要です:
- 氏名または名称、住所
- 廃棄物の種類と数量
- 積載した日付
- 積載元と運搬先の所在地・名称・連絡先
※これらの内容がマニフェストや他の運搬伝票に記載されていれば、その書類をもって代用可能です。
▷ 電子マニフェストの運用例
電子マニフェストを導入している場合は、以下のような書類の備え付けが必要です:
- 電子マニフェスト加入証の写し
- 該当する廃棄物の受渡内容を確認できる帳票や画面(スマホ・タブレットでの提示も可)
これらの書類は「運搬している廃棄物が何なのか」を証明するためのものです。 車検証と同じく、「その場で提示できる」ことが大前提となります。
▷ 書類不備のリスク
- 許可証のコピーがない
- マニフェストの記載ミス
- 自己運搬での必要情報が不足している
こうした書類不備は、表示義務違反と並んで非常に多い違反項目です。 軽微な違反でも繰り返すと、改善命令や許可停止、最悪の場合は許可取消につながることも。
「書類の携帯なんて忘れがち…」という方こそ、チェックリスト化と社内教育の徹底がカギになります。
積替え保管の影響|表示ルールに変化は?
「うちは積替え保管もやる予定なんだけど、車両の表示は変わるの?」 そんな質問をいただくことがありますが、積替え保管をしていても、車両の表示義務は原則変わりません。
表示ルールは「積替え保管をするかどうか」ではなく、誰が運搬するのか(許可業者か、自己運搬か)によって決まります。 そのため、積替え保管の有無によって「産業廃棄物収集運搬車」や「許可番号」等の表示内容が変わることはありません。
ただし、積替え保管を行う場合は、マニフェストや委託契約書において、施設名や所在地を明記する必要があるなど、 運用面では追加の注意点が生まれます。
また、積替え保管施設そのものに対しても、
- 囲いの設置
- 不透水床面
- 排水処理設備
など、専用施設としての厳しい基準が求められます。つまり、積替え保管は「車両表示」ではなく、「マニフェスト管理」「施設整備」「契約書の記載事項」といった別の部分でルールが厳しくなると理解しておくとよいでしょう。
なお、積替え保管は処理業に近い行為として見られることもあるため、地域によって運用や指導内容が異なることも。 事前に自治体への確認を強くおすすめします。
よくある違反とその代償|許可取消は現実にある
運搬車両に関する違反は、ちょっとした見落としが大きなトラブルにつながることがある分野です。 以下のようなケースは、実際の現場でもよく見られます。
▷ 表示違反の例
- 表示が小さすぎて読めない
- マグネットが剥がれて走行中に紛失
- 略称や屋号だけの表示(正式名称でない)
- 許可番号の記載漏れ
▷ 書類不携帯の例
- 許可証のコピーを積み忘れている
- マニフェストを事務所に置き忘れてしまった
- 自己運搬で必要な情報が書かれていないメモだけを携帯していた
こうした違反は、路上検査で発覚しやすく、その場での是正や改善指導を受けることになります。
しかし、指導だけで済めばまだ良い方で、
- 違反を繰り返している
- 重大なミスを放置していた
- 不適切な運搬で環境被害が発生した
といった場合には、「改善命令」「事業停止命令」「許可取消処分」といった厳しい措置が科されることもあります。
「知らなかった」「ちょっと忘れていただけ」は、言い訳としては通用しません。日々の運用の中でルールを守り続けるには、
- 社内チェック体制の構築
- ドライバーへの教育
- 表示物や書類の定期点検 など、仕組みづくりがカギになります。
行政処分を避け、安定した運搬業務を継続するためにも、 「表示」と「書類」は常に整っている状態を維持しておきましょう。
まとめ|許可取得前に知っておくべき“車両のルール”
産業廃棄物収集運搬車両に関するルールは、手続きの最後に確認するものではなく、最初に押さえておくべき最重要ポイントです。
車両の表示、書類の携帯、構造の適合性。 どれも「軽視されがち」ですが、実務上の違反が最も多く、事業停止や許可取消につながるリスクも高い部分です。
「今ある車両が使えるか不安…」「表示の方法が正しいか確認したい…」 そう思った時が、まさに確認・見直しのチャンスです。
迷ったら、行政書士に相談して万全の準備で申請に臨むことが、結果として最短・最小コストでの許可取得につながります。
産業廃棄物に関する手続きで、こんなお悩みはありませんか?
- 初めての許可申請で何から始めていいかわからない…
- 行政の説明が複雑で、自分に当てはまるか不安…
- 元請業者から手続きや登録を求められて困っている…
そんなときは、建設系産業廃棄物業界出身の行政書士が対応する 三澤行政書士事務所にぜひご相談ください。
当事務所は、愛知県を中心に中小企業・個人事業主の建設業者様をサポートしており、 許可申請から更新・変更届、関連する各種制度(例:CCUSや経審など)まで幅広く対応可能です。
まずはお気軽にご連絡ください。
▼ お問い合わせはこちらから